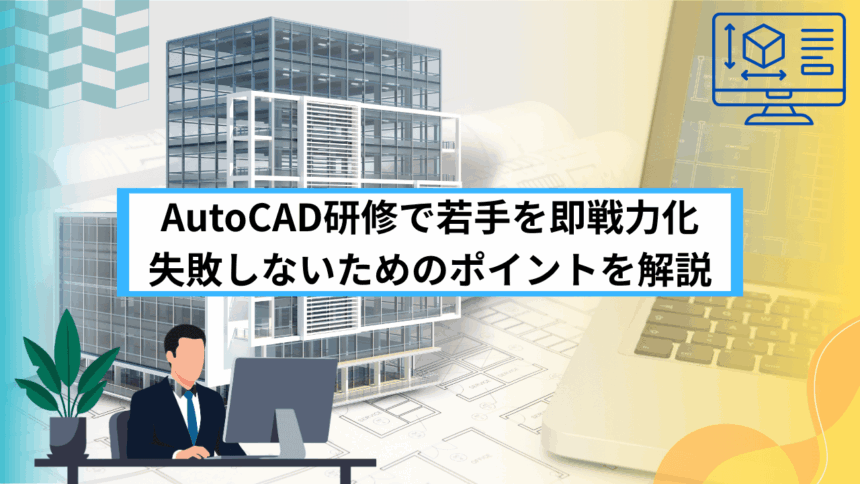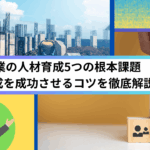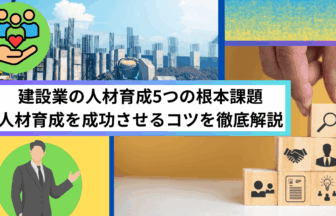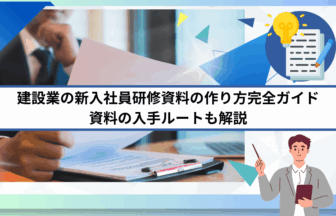「社内でAutoCAD研修を導入したいけど、何から始めればいい?」
「若手社員にAutoCADを教えているが、なかなか上達しない…」
このような悩みを抱える建設会社の教育担当者様に向けた記事です。
この記事でわかること
- AutoCAD研修の主な種類
- 失敗しないAutoCAD研修5つのポイント
- AutoCAD研修は内製化と外部委託どちらが効果的か
AutoCAD研修を導入することで、若手社員の即戦力化と組織全体の生産性向上が期待できます。
適切な研修はOJTだけでは教えられない体系的な知識、社内で統一された作図ルールを効率的に習得させられます。
「でも、研修の数が多くてどれを選べばいいかわからない…」と思いますよね?
この記事を読めば、自社の目的や課題に合うAutoCAD研修の選び方がわかります。
若手社員のスキルを底上げし、会社の生産性を向上させたい方は最後まで読んでみてください。
AutoCAD研修におすすめのeラーニング
AutoCADの研修には、私たちワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」がおすすめです。
3分程度の短時間で学べるeラーニング形式なので、忙しい現場でも効率的に基礎知識から実践的なスキルまで習得できます。
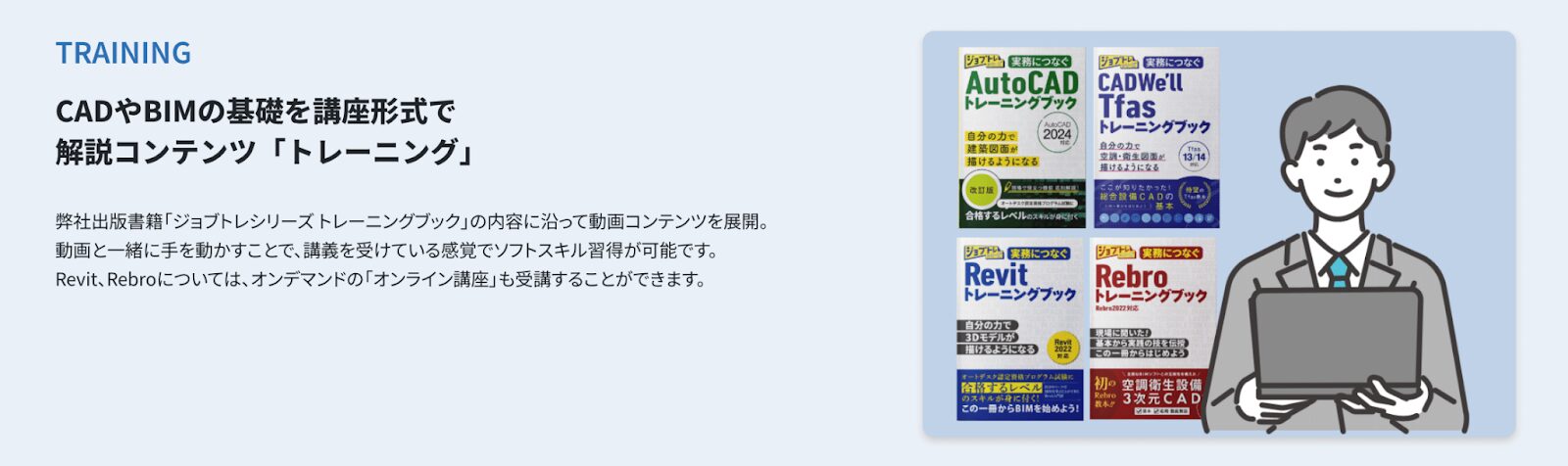
無料から気軽に始められるので、試しながら検討してみてください。
目次
AutoCAD研修をおすすめする3つの理由
企業にAutoCAD研修をおすすめする理由は、以下のとおりです。
AutoCAD研修をおすすめする3つの理由
- 現場の生産性向上が期待できるため
- 図面の品質を標準化できるから
- 技術継承と若手育成を促進できるから
AutoCAD研修を導入することで、スキルを習得する以外にもさまざまなメリットがあります。
それぞれのメリットを見ていきましょう。
現場の生産性向上が期待できるため
AutoCAD研修は社員の作図スキルを高め、現場全体の生産性を向上させます。
基本的な操作はもちろん、ショートカットキーや応用機能などの効率的な作図手順を学ぶことで、自己流の非効率な作業を改善できます。
また、研修を通じて操作スキルを標準化することは、組織全体の業務効率化につながるでしょう。
図面の品質を標準化できるから
研修を導入すると、社内における図面の品質を一定のレベルで保ちやすくなります。
作図ルールやレイヤーの管理方法などを統一し、全社員が共通の認識をもって作業にあたることで、担当者ごとの品質のばらつきを防げるためです。
図面の品質が標準化されると、以下のような効果が見込めます。
図面の品質標準化で期待できる効果
- 手戻りや修正作業の削減
- 協力会社とのデータ連携の円滑化
- 成果物に対する信頼性の向上
担当者が変わっても品質が落ちる心配がなくなり、プロジェクトをスムーズに進められるようになります。
技術継承と若手育成を促進できるから
AutoCAD研修はベテラン社員の高度な技術を若手へ継承し、体系的な人材育成を促進する仕組みとして機能します。
これまで個人の経験に頼りがちだった作図のノウハウを、研修を通じて社内の標準スキルとして活用できます。
また、OJT(現場教育)と研修を組み合わせることで、それぞれの利点を活かした育成も可能です。
| 教育方法 | 期待できる効果 |
|---|---|
| OJT(現場教育) | 現場ごとの特殊な事例や実践的な対応力を習得 |
| AutoCAD研修 | 体系的な知識と誰でも応用できる標準スキルを習得 |
それぞれの教育方法の長所を組み合わせると、若手社員は応用力を身につけながら早期に成長できます。
参考記事:なぜ建設業の技術継承は失敗するのか?よくある5つの課題と解決策を解説
AutoCAD研修の主な種類と比較|自社に合うのはどれ?
ここでは、AutoCAD研修の種類を解説します。
AutoCAD研修の主な種類
- 集合研修
- オンライン研修
- 講師派遣型研修
- eラーニング
それぞれ特徴が異なるため、自社の目的や環境に合わせて適切な研修を選びましょう。
参考記事:CAD研修で社員のスキルを底上げする方法|おすすめの研修も紹介
集合研修
集合研修は指定された会場に受講者が集まり、対面で講師から直接指導を受ける研修です。
その場で質問することで疑問点をすぐに解消できるため、未経験者や初心者が基礎から学ぶのに適しています。
ポイント
また、他の受講者と顔を合わせることで、学習意欲の向上や社員同士の連帯感を高める効果も期待できます。
ただし、会場までの移動時間や交通費が発生し、スケジュール調整が難しい点はデメリットです。
オンライン研修
オンライン研修は場所を問わずに参加できるため、複数の拠点をもつ企業やリモートワークを導入している企業にとって利便性が高いといえます。
オンライン研修の主なメリットとデメリットは以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| メリット | 遠隔地の社員も参加可能で、交通費や移動時間を削減できる |
| デメリット | 安定したインターネット環境が必須で、通信トラブルのリスクがある |
講師への質疑応答もリアルタイムで可能なため、集合研修に近い感覚で受講できます。
研修の様子を録画しておくと、後から繰り返し復習できる点もメリットです。
柔軟に学習できる環境を構築しつつ、双方向のコミュニケーションも行いたい企業にオンライン研修は向いています。
講師派遣型研修
講師派遣型研修は企業のオフィスなどに講師を招き、自社の環境で研修を実施するスタイルです。
受講者が移動する必要がなく、普段から使い慣れたパソコンやCADソフトで学べるため、研修内容をすぐに実務へ活かせます。
ポイント
また、自社の業務内容や課題に合わせてカリキュラムを細かく調整してもらえる点もメリットです。
派遣費用や研修を実施するために一定のスペースを確保する必要はありますが、実務に即した内容で集中的にスキルアップを図りたい場合に効果的です。
eラーニング
eラーニングは録画された講義動画を利用し、個人のペースで学習を進められる研修です。
時間や場所に縛られず業務の隙間時間などを利用して学習できるため、多忙な社員でも受講しやすい点がメリットです。
eラーニングは、以下のような特徴をもつ企業に適しています。
eラーニングが合う企業の特徴
- 社員の勤務時間が不規則で集合研修の日程調整が難しい
- 低コストで研修制度を導入したい
- 社員が自分のペースでくりかえし学習できる環境を整えたい
多くのeラーニングサービスは、集合研修などと比較して費用を抑えることが可能です。
コストを抑えつつ、柔軟な教育環境を構築したい企業に向いています。
AutoCADが見放題のeラーニング「Construction Boarding」

AutoCADのスキルアップには、Construction Boardingがおすすめです。
実際の現場映像やわかりやすいイラストを使いながら、AutoCADの基礎から実践まで体系的に学べます。
Construction Boardingの特徴
- 1つのコンテンツが3分前後で学べる短時間設計
- スマホやPCに対応し、いつでもどこでも学習可能
- AutoCADなど、建設業で必要な専門コンテンツが充実
- 理解度テストで学習の定着を確認できる
- 人材開発支援助成金の対象になる

マイクロラーニング形式のため、現場の休憩時間や移動中といった隙間時間を活用して学習を進められます。
2週間の無料トライアルもあるので、試しながら検討してみてください。
失敗しないAutoCAD研修5つのポイント
ここでは、研修選びで失敗しないためのポイントを解説します。
失敗しないAutoCAD研修5つのポイント
- 実務に合うカリキュラムか確認する
- 費用対効果の高さを比較検討する
- 受講形式の柔軟性をチェックする
- 研修後のフォローアップ体制を確認する
- サポート体制が充実しているかを調べる
目的や費用、サポート体制などを比較検討することで、自社に合う研修を見つけやすくなります。
失敗を防ぐためにも、それぞれのポイントを押さえておきましょう。
参考記事:成果が出る建設業の新人研修7ステップや具体的なカリキュラム内容を解説
実務に合うカリキュラムか確認する
研修を選ぶ際には、カリキュラムの内容が自社の実務に即しているかを確認することが大切です。
基礎的な操作方法だけでなく、実際の業務で直面する課題を解決できる技術を学べないと、研修の効果が限定的になるからです。
カリキュラムを確認する際は、以下の点に注目してみてください。
カリキュラムのチェックポイント
- 自社の業務分野(建築、土木など)に特化した内容か
- 実践的な図面作成の演習が含まれているか
- 業務効率化につながる応用機能の解説があるか
研修会社によっては、企業の要望に応じて内容を調整できる場合もあります。
事前に相談し、自社の課題解決に直結する研修を選びましょう。
費用対効果の高さを比較検討する
単純に価格が安いという理由だけで選んでしまうと、内容が不十分で期待した成果が得られない場合があります。
仮に受講料が高額でも、生産性向上による人件費削減や品質向上による手戻り工数の削減が見込める場合、長期的に見て有益な投資です。
複数の研修サービスから見積もりを取り、内容と費用、期待できるリターンを総合的に評価することで失敗を避けやすくなります。
受講形式の柔軟性をチェックする
社員の働き方や勤務体系に合わせて、柔軟に受講できる形式の研修を選ぶことも大切です。
多忙な業務をこなしつつ研修を受ける社員にとって、受講のしやすさは学習の継続性と効果に直結します。
自社の状況に合わせて、以下の研修が適しているか検討してみてください。
| 企業の状況 | 推奨される受講形式 |
|---|---|
| 勤務時間が不規則な社員が多い | eラーニング(オンデマンド型) |
| 複数の拠点に社員が点在している | オンライン研修(ライブ配信) |
| 新入社員を効率よく教育したい | 集合研修や講師派遣型研修 |
欠席した場合の振替受講が可能か、講義を録画して後から視聴できるかといった点も確認しておくと、より多くの社員が学びやすくなります。
社員が無理なく参加できる研修を選び、研修の効果を高めていきましょう。
研修後のフォローアップ体制を確認する
研修で学んだ内容を実務で活用しようとすると、新たな疑問点が出てくることも少なくありません。
研修の効果を高めるためにも、以下のようなフォローアップ体制が整っているか確認しましょう。
フォローアップ体制の例
- 研修後の質問受付サービス
- 理解度を確認するための復習テストの提供
- 応用スキルを学ぶためのアドバンス講座の用意
フォローアップ体制が充実していると学習内容が定着しやすくなり、研修の効果を長期的に維持しやすくなります。
サポート体制が充実しているかを調べる
フォローアップ体制だけでなく、サポート体制も確認してみてください。
学習のつまずきや事務手続き上の不明点をすぐに解決できる環境は、研修を円滑に進める上で不可欠だからです。
ポイント
例えば、技術的な質問にすぐ回答してくれる専門スタッフ、助成金申請の相談に乗ってくれる窓口などがあると担当者の負担が軽くなります。
また、受講者からの質問への回答スピードや対応時間なども事前に確認しておくと安心です。
助成金を活用してコストを削減できる「Construction Boarding」

研修コストを抑えたい場合は、人材開発支援助成金を活用できるeラーニングの導入が効果的です。
私たちワット・コンサルティングが提供するConstruction Boardingも、人材開発支援助成金の対象です。
ポイント
助成金を活用してコストを抑えながら、AutoCADの学習環境を整えられます。
「低コストの研修を導入したい」「まずはお試しで始めたい」という方は、お気軽に資料請求してみてください。
AutoCAD研修は内製化(社内研修)と外部委託どちらが効果的?
ここでは、AutoCAD研修の内製化と外部委託について詳しく解説します。
AutoCAD研修の内製化と外部委託について
- 内製化のメリット・デメリット
- 外部委託のメリット・デメリット
- 外部委託がおすすめな企業の特徴
それぞれのメリット・デメリットを比較し、外部委託がおすすめな企業を紹介します。
AutoCAD研修を内製化するか外部委託にするかで迷っている方は、参考にしてみてください。
参考記事:施工管理の新人教育で失敗しない!新人が成長する研修10ステップ
内製化のメリット・デメリット
研修の内製化は、自社の実務に特化した内容で教育できる点がメリットです。
社内のベテラン社員が講師を務めることで、独自のノウハウや過去の事例を交えた実践的な指導ができます。
また、外部に支払う費用を抑えられる点も大きなメリットです。
ポイント
一方、教材作成や準備などで講師役の社員に大きな負担がかかる可能性があります。
教える側のスキルによって教育の質にばらつきが出やすい点も、注意が必要です。
外部委託のメリット・デメリット
外部委託は、教育のプロによる質の高い研修を受けられる点がメリットです。
ポイント
専門の研修会社は体系的なカリキュラムやわかりやすい教材を備えており、研修の企画から運営まで一括して任せられます。
これにより、自社の研修担当者の負担を大幅に軽減できるでしょう。
ただし、内製化に比べて費用は高くなる傾向にあり、研修内容が汎用的で自社の業務と合わない可能性がある点はデメリットです。
外部委託がおすすめな企業の特徴
これまでの内容を踏まえると、以下に該当する企業は外部委託が適しています。
外部委託がおすすめな企業
- 社内にAutoCADを教えられる適任者がいない
- 拠点や部署ごとで教育の質を均一に保ちたい
- 研修の教材作成や準備に時間を使う余裕がない
- 専門家の視点から最新の技術や知識を取り入れたい
外部の専門知識を活用することで、効率的かつ効果的に人材育成を進められます。
外部委託するかで迷う場合は、自社のリソースや課題と照らし合わせると、外部委託が最適な選択肢かを判断しやすくなるでしょう。
AutoCAD研修に関するよくある質問
最後に、AutoCAD研修についてよくある質問にお答えします。
AutoCADを習得するのにどれくらい時間がかかる?
AutoCADの習得に必要な時間は、目標とするスキルによって異なります。
作図や修正、寸法記入といった基本操作であれば、研修などを利用して30〜40時間程度で身につけることが可能です。
実務で応用機能を不自由なく使いこなせるようになるには、3ヶ月から半年程度の時間がかかります。
Jw_cadとAutoCADはどちらを優先して学ぶといい?
Jw_cadとAutoCADのどちらを優先するかは、自社の業務分野や取引先の状況によって決まります。
それぞれのソフトに特徴があり、得意な分野や国内での普及率が異なるためです。
| ソフト名 | 主な特徴 | よく使われる分野・企業 |
|---|---|---|
| AutoCAD | 世界的なシェアが高く3D機能やカスタマイズ性が豊富 | ゼネコンや大手設計事務所、海外企業との連携 |
| Jw_cad | 無料で利用でき2Dの建築図面に特化した機能が充実 | 日本国内の建築設計事務所や工務店 |
世界標準のAutoCADは汎用性が高く、大規模プロジェクトや将来的なBIMへの展開を視野に入れる場合におすすめです。
一方のJw_cadは、日本の建築業界で広く普及しています。
取引先が使用しているソフトに合わせて、どちらを優先するか選びましょう。
AutoCAD関連の資格の難易度は?
AutoCAD関連資格の難易度は、資格の種類によってさまざまです。
開発元であるオートデスク社が認定する公式資格は世界共通の基準でスキルを証明するもので、実務経験者でも十分な対策が必要になります。
ポイント
代表的な資格は「AutoCAD 認定ユーザー」とより上位の「AutoCAD 認定プロフェッショナル」です。
前者は基本的な操作スキルを証明するもので、比較的取得しやすいです。
後者は高度で専門的なスキルが問われるため、難易度は高くなります。
まとめ
最後にもう一度、研修選びで失敗しないためのポイントをまとめておきます。
失敗しないAutoCAD研修5つのポイント
- 実務に合うカリキュラムか確認する
- 費用対効果の高さを比較検討する
- 受講形式の柔軟性をチェックする
- 研修後のフォローアップ体制を確認する
- サポート体制が充実しているかを調べる
AutoCAD研修を成功させるには、自社の目的や課題に合うサービスを選ぶことが重要です。
この記事で紹介したポイントを参考に、若手の育成と生産性向上を実現しましょう。
AutoCAD研修を効率的に進めたい方には、Construction Boardingがおすすめです。
いつでもどこでも学べるeラーニングなので、現場が忙しくて研修時間を確保できない企業様の悩みを解決できます。
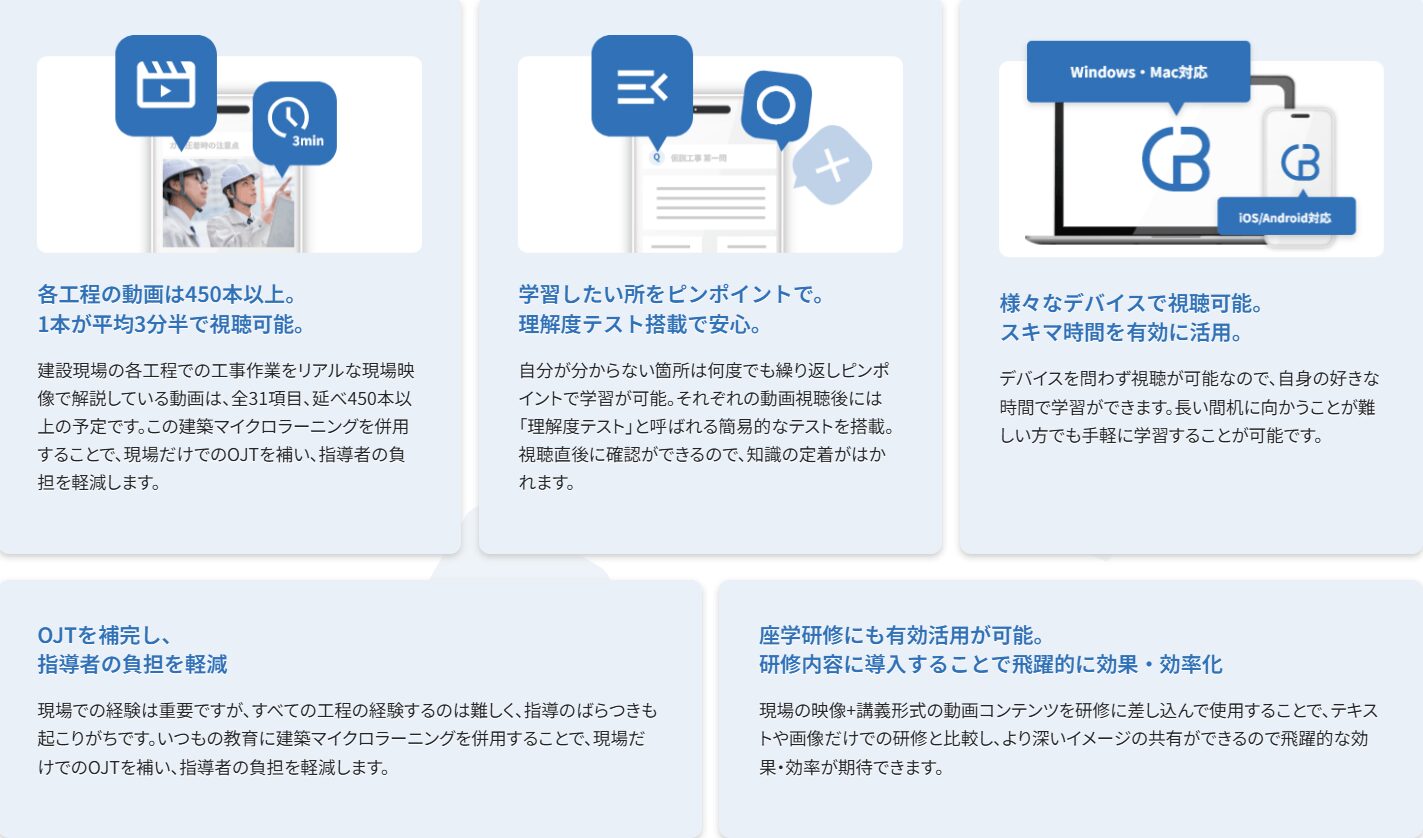
無料で2週間のトライアルができ、さらに人材開発支援助成金の対象となるため、低コストで質の高いAutoCAD研修を導入できます。
2週間の無料トライアルで、実際の使い勝手を確かめてみてください。
貴社のAutoCAD研修の参考になれば幸いです。