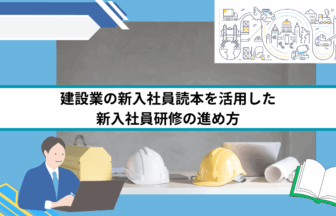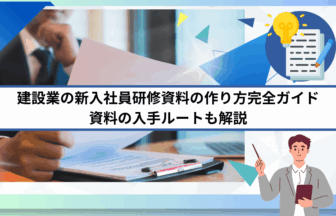「社内のCAD技術者をうまく育成できない…」
「CAD研修を実施したいけど、時間と資金に余裕がない…」
こういった悩みを持つ建設会社様や設計事務所様に役立つ記事です。
この記事でわかること
- CAD研修を実施しないリスク
- 自社でCAD研修を実施する手順
- おすすめの外部CAD研修
自社に合ったCAD研修を導入すれば、作業効率と人材育成を同時に進めやすくなります。
新人からベテランまでスキルを高められて、業務の質やスピードが底上げされるでしょう。
しかし「忙しくて育成時間がない…」「外部研修は高そう…」と感じる方もいると思います。
この記事を読むことで、CAD研修を整備する方法やおすすめの研修サービスがわかります。
コストや時間不足の課題を乗り越えられるので、さっそく研修制度を整備していきましょう。
CAD研修は、株式会社ワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」がおすすめです。
いつでもどこでも学べるeラーニングなので、現場が忙しくてCADを使う担当者を育成する時間がない企業様の悩みを解決できます。
Construction Boardingが合う企業様の特徴
- 人材育成に割く資金が足りない
- 残業を減らしながら人材育成する時間を捻出できない
- 社内で研修制度を作るノウハウがない
無料で2週間のトライアルができて、さらに助成金の対象となるeラーニングです。
「まずはお試しで始めたい」「低コストで研修を整えたい」という場合は、お気軽に資料請求してみてください。
この記事の監修者
施工管理の技術者派遣を行う会社。これまで1500名以上の未経験者を施工管理として育成した実績あり。
- 労働者派遣事業許可番号 派13-304593
- 有料職業紹介事業許可番号 13- ユ-304267
- 特定建設業 東京都知事許可 (特-1) 第150734号
CAD研修を実施しない4つのリスク
研修を導入せずに業務を続けると、生産性や品質、対外的評価など多面的に悪影響を受けます。CAD研修を実施しない主なリスクは以下の4つです。
CAD研修を実施しないリスク
- 作業効率が低下する
- 図面やデータの品質が低下する
- スケジュールが遅延しやすい
- 競合他社との技術格差が広がる
それぞれの回避策や研修を導入するメリットも含めて説明していきます。
作業効率が低下する
CADの機能を正しく把握しないまま作業を進めると、図面修正や再描画の回数が増えて、作業効率が低下します。
例
操作に必要なショートカットを知らないと、担当者ごとの手戻りが重なり、全体の進捗が停滞するでしょう。
CAD研修を導入すれば、全員が効率的な操作手順を理解しやすくなり、プロジェクト全体で作業時間を減らせます。以下の一覧は、CAD研修の導入で期待できる主なメリットです。
| メリット | 具体例 |
|---|---|
| 作業時間の削減 | ショートカットや定型コマンドの活用で、1件あたりの作業を半分程度に圧縮しやすい |
| 品質の維持 | レイヤー管理の基準が統一され、図面ミスの発生頻度を下げられる |
| 教育コストの軽減 | 全員が同じ教材で学ぶ仕組みにより、新人や異動者の教育負担を減らしやすい |
研修によって、作業効率の向上だけでなくミスも最小化しやすいです。
図面やデータの品質が低下する
操作に未熟なまま作図や編集を進めると、寸法ズレやレイヤー設定の誤りが起こりやすいです。
仕上がりに一貫性がなく、次工程や協力会社で混乱が生じる可能性があるでしょう。
ポイント
CAD研修を導入すれば、正しい記号や配色ルールを理解し、統一感のある図面を作成しやすくなります。
例えば、設計事務所とのデータ共有がスムーズになり、トラブルを減らせます。さらに、品質を意識した図面管理を学べば、検査や書類対応の精度も上がり、信頼性の高いプロジェクト運営が期待できるでしょう。
スケジュールが遅延しやすい
CADスキルが不足した状態だと、プロジェクトの進行が遅延しがちです。特に大型案件では図面の修正だけでなく関連資料の更新も多く、スキルが足りないと納期に遅れる危険性もあります。
研修を実施すれば、CAD操作に慣れてスピーディーに業務が進むでしょう。
CAD研修で業務がスピードアップする例
- ショートカットを活用して業務スピードが上がる
- 優先度の高い業務から始めて納期に間に合いやすくなる
- 複数の案件を同時進行するスキルがアップする
業務全体がスムーズに進めば、クライアントとのコミュニケーションも円滑になり、信頼関係を築きやすいです。
競合他社との技術格差が広がる
設計や施工の現場では、高度な3D機能や連携ツールを活用する動きが加速しています。周囲がBIMやARを導入し、打ち合わせや検討のスピードを上げている中、自社だけが旧来の方法を続けていると技術格差が広がってしまいます。
CAD研修のメリット
研修で新しい機能やツールの操作方法を学べば、他社に後れを取らずに済むでしょう。
以下の表は、研修で習得したい先端技術の例です。
研修で最新技術を習得すると、提案力や管理精度の面でも優位性が増し、受注機会の拡大につながります。
自社でCAD研修を実施する手順
自社でCAD研修を導入するときは、以下のステップに沿って研修を整備していきましょう。
自社でCAD研修を実施する手順
- 社員の現状スキルの把握
- 研修プログラムの設計
- 講師の選定
- 教材の作成
- CAD研修の効果測定
- 研修後のフォローアップ
1ステップずつ解説していくので、さっそく準備を始めてみてください。
社員の現状スキルの把握
まずは、担当者のCADスキルを確認しましょう。アンケートや簡易テストで理解度を測定します。スキルを把握する方法は以下のとおりです。
CADスキルを把握する方法
- 図面作成の回数やソフトの使用歴を聞く
- 操作テストを実施し、レイヤー設定や寸法入力の精度を見る
- 過去の図面データを抽出し、共通のミスや改善点を確認する
- 上長に普段の作業スピードや苦手な部分を聞く
メンバー全体のスキルを把握すれば、研修で重点的に補うポイントが見えてきます。スキルの偏りがある場合は、グループを分けて研修を進めましょう。
研修プログラムの設計
全員が同じペースで研修を進めると、初心者と上級者の両方に無理が生じやすいです。レベルや目的別に区切ったカリキュラムを作れば、スキルを習得しやすくなります。以下はスキル別の研修プログラムの例です。
初歩から徐々にレベルを上げていく流れにすると良いでしょう。実務に合わせてモジュールを組み替えたり、一定期間おきに再受講させる方法も検討してください。
ちなみに
研修プログラムを自社で作るのが難しい場合は、外部研修を活用しましょう。
冒頭でも触れましたが「Construction Boarding」は、低コストでCADを学べるeラーニングです。
無料で2週間のトライアルもあるため、お気軽に資料請求してみてください。
講師の選定
次にCAD研修の講師を選定していきましょう。社内講師と外部講師で得られる効果が変わります。以下の表は社内講師と外部講師の比較表です。
さらに、社内講師と外部講師を組み合わせたハイブリッド型だと、現場感と専門知識を両立しやすいです。コストと効果のバランスを見て決定してみてください。
教材の作成
研修の教材は、自社の業務に即した教材を作る方法と、市販の教材をアレンジする方法があります。以下は教材の具体例なので参考にしてみてください。
わかりやすい教材があれば、研修後の復習もスムーズです。過去の案件を定期的に教材化すれば、実務に活きるノウハウを共有しやすいです。
CAD研修の効果測定
研修が終わったら、効果を検証して次の計画につなげるとCADスタッフが成長しやすいです。数値や具体的な成果を残しておくと、研修への投資価値が見えやすいでしょう。以下は効果測定の例です。
CAD研修の効果測定の例
- 研修前と同じ図面を作成してもらい精度を確認
- 寸法ミスやレイヤー管理の不備件数の減少を確認
- アンケートで操作や理解度の自己評価を数値化してもらう
- プロジェクト単位で成果を振り返る
これらを継続して実施すれば、弱点を補強できて、全体的な作業精度が高まっていきます。
研修後のフォローアップ
研修が終わると使い方を忘れてしまう人もいます。定期的な復習や質疑応答の場を設けて、習得度を保ちましょう。以下は主なフォローアップの手段です。
研修後のフォローアップの例
- 定例ミーティングや勉強会で不明点に答える
- 気軽に質問できる社内チャットを作る
- 新しい機能が増えたら追加研修を実施する
- ベテランが後輩をサポートするメンター制度を組む
現場で生じた事例を共有できる仕組みを維持していけば、学びが定着しやすくなります。学習環境を継続的にアップデートしていけば、より強いCAD活用力が期待できるでしょう。
CAD研修の集合研修・オンライン研修・eラーニングの違い
研修スタイルには主に以下の3つがあります。
| 研修スタイル | 特徴 |
|---|---|
| 集合研修 | 受講者が一堂に集まり、講師が対面で講義する |
| オンライン研修 | ウェブ会議システムなどでリアルタイムに学習する |
| eラーニング | 動画や教材をオンデマンドで視聴しながら学習する |
どの研修スタイルを選ぶか迷う場合があるでしょう。それぞれのメリット・デメリットを解説していくので、研修スタイルの参考にしてみてください。
各スタイルが合う企業の特徴もまとめています。
集合研修
就業研修とは、全員が同じ場所に集まり、講師が対面で教えるスタイルです。目の前で操作例を見せたり、疑問点をその場で質問できるため、初学者の不安を早期に解消できます。
チーム内のコミュニケーションが活発になり、同期メンバーの結束を深める機会にもなるでしょう。会場費や移動手段の確保、日程調整などの準備が必要なので、大規模な組織ほど計画段階で時間がかかるのがデメリットです。
| メリット | 講師が直接指導しやすく、受講者同士で情報を交換しながら理解を深めやすい |
| デメリット | 会場や移動の負担が増え、日程の自由度が低くなる |
| どんな企業に合っているか | 新人が多く対面サポートの優先度が高い企業、同期研修で一体感を育てたい組織 |
オンライン研修
ウェブ会議ツールを使い、遠隔地から同時に参加するやり方です。多拠点を抱える企業に適しており、交通費の負担を減らしながら一斉に研修を進められます。
回線が途切れる恐れがあるため、安定した通信環境が必要です。
| メリット | 離れた拠点からでもリアルタイムで質問しやすく、録画を使って後から復習も可能 |
| デメリット | 通信障害が起きると集中力を維持しづらく、画面共有が途切れて作業が進まない場面が出る |
| どんな企業に合っているか | 各地に支店が多い、あるいは在宅勤務が常態化していて、集合研修を設定しにくい組織 |
チャットを活用すれば質問の敷居が下がり、個別の疑問も解消しやすいです。また、アーカイブを残して、くりかえし見直してもらうことで理解度を高められます。
eラーニング
オンデマンドで動画や教材を視聴するスタイルです。好きなタイミングで学習できるため、多忙な社員が多い職場におすすめです。
学習スピードが担当者ごとでバラバラになるのがデメリットですが、学習進捗をチェックできるeラーニングもあるため管理しやすくなっています。
| メリット | 都合の良い時間帯に複数回学習でき、再生や停止を繰り返しながら理解を深めやすい |
| デメリット | 学習スピードに差が出る |
| どんな企業に合っているか | シフト勤務がある職場や海外拠点が多い組織、低コストで研修を整えたい企業 |
eラーニングはコストが低いのも魅力です。研修制度を整えるのが難しい企業にも良いでしょう。
また、eラーニングによっては確認テストや質問チャットがあるため、知識が定着しやすいです。
おすすめのeラーニング
くりかえしですが「Construction Boarding」は、低コストでCADを学べるeラーニングです。
無料で2週間のトライアルもあるため、お気軽に資料請求してみてください。
外部CAD研修の選び方
外部の専門家へ任せる際は、研修メニューや費用感などを比較すると失敗しにくいです。
外部のCAD研修を選ぶときのコツ
- カリキュラムの内容が自社に合っているか調べる
- コストパフォーマンスの良さをチェックする
- 受講しやすさを確認する
1つずつ解説していくので、外部研修を検討する場合は参考にしてみてください。
カリキュラムの内容が自社に合っているか調べる
研修会社ごとに強みや対応範囲が違うため、自社の目的に合った研修を探しましょう。新人が多いのか、それとも高度な3D活用を狙うのかで、求めるテーマが変わってきます。
例は以下のとおりです。
| 自社の特徴 | 選ぶと良いカリキュラムの例 |
|---|---|
| 新人が多い | 操作の基礎2D図面作成簡易チェックリストの導入 |
| 施工管理が中心 | 図面と工程表の連動改修プロジェクトで起きやすいトラブル回避 |
| 設計に3Dを取り入れたい | モデリングの概念干渉チェック手順BIMソフトの活用ポイント |
| 大規模案件が増える | データ共有の標準化大人数向けの共同作図検査プロセスの効率化 |
自社の業務領域と課題を先に洗い出しておけば、無駄な内容を省きやすいです。検討段階で複数候補から資料を取り寄せ、講座の詳細を比べてみてください。
コストパフォーマンスの良さをチェックする
外部研修を頼むときは、費用に見合うリターンを得られるかが大切です。高額の研修でも、収益に直結する内容であれば投資価値があるでしょう。
また、研修によっては助成金を受給できる可能性があります。要件を満たせばCAD研修費用と賃金の一部を補助してもらえるため、コストカットできます。
以下は代表的な助成金の例です。
参考:厚生労働省|人材開発支援助成金|建設事業主等に対する助成金
助成金を申請する場合は、行政機関へ問い合わせてみましょう。
ちなみに
私たちが提供する「Construction Boarding」は人材開発支援助成金の対象です。
コストカットしながら研修を整えたい企業は、お気軽に資料請求してみてください。
受講しやすさを確認する
現場の働き方や拠点数に合わせた外部研修を選びましょう。研修会場までの移動が多いと負担が増すため、オンライン研修やeラーニングも検討してみてください。以下は受講しやすい研修スタイルの具体例です。
受講しやすい研修スタイルの例
- オンラインラ配信で遠方から参加可能
- ライブ講義を録画して、欠席者が後日視聴できる
- eラーニングで好きなときに学び、進捗を講師がフィードバック
連続した時間が確保しにくい場合は、eラーニング中心の研修を検討すると良いでしょう。
おすすめのCAD研修
CAD研修は「Construction Boarding」がおすすめです。
以下に該当する企業様の悩みを解決します。
Construction Boardingが合う企業様の特徴
- 人材育成に割く資金が足りない
- 残業を減らしながら人材育成する時間を捻出できない
- 社内で研修制度を作るノウハウがない
Construction Boardingは、CAD利用者が自分のペースで学べるeラーニングです。
社内のCAD利用者を集めて研修する必要がないため、まとまった研修時間を確保しなくて大丈夫です。
さらに、ご要望に応じて研修内容をカスタマイズできるため、貴社で補強したい部分を効果的に研修できます。
無料で2週間のトライアルができて、助成金も受けられるため、低コストで研修を実施したい企業様におすすめです。
「まずはお試しで始めたい」という場合は、お気軽に資料請求してみてください。
まとめ
最後にもう一度、自社でCAD研修を実施する手順をまとめておきます。
自社でCAD研修を実施する手順
- 社員の現状スキルの把握
- 研修プログラムの設計
- 講師の選定
- 教材の作成
- CAD研修の効果測定
- 研修後のフォローアップ
自社でCAD研修を整備できない場合は、外部研修を検討しましょう。
くりかえしですが、CAD研修は「Construction Boarding」がおすすめです。
無料で2週間のトライアルができて、助成金も受けられるため、低コストで研修を実施したい企業様におすすめです。
「まずはお試しで始めたい」という場合は、お気軽に資料請求してみてください。
貴社のCAD研修の参考になれば幸いです。