「新入社員研修の資料を毎年準備するのが大変…」
「何から手をつければいいのか、構成がわからない…」
「内容がマンネリ化していて、新人に響いているか不安…」
このような悩みを抱える、土木・建設業の教育担当者様に向けた記事です。
この記事でわかること
- 土木の新入社員研修資料に必要な項目
- 土木の新入社員研修カリキュラムの設計方法
- 土木の新入社員研修資料の具体的な作成手順
質の高い研修資料は、既存のテンプレートと自社独自の一次情報(現場の写真や事例)を組み合わせることで作成できます。
テンプレートで作成の効率を上げつつ自社のリアルな情報を盛り込むことで、新入社員の当事者意識を高め、より実践的な学びを促せます。
「でも、具体的にどんな項目を盛り込んで、どういう手順で進めればいいのかわからない…」と思いますよね?
この記事を読めば、土木の新入社員研修資料の作成手順がわかり、新人が即戦力として活躍するための土台を築けます。
質の高い研修で新人の成長をサポートしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
新入社員研修を効率化するeラーニング
「Construction Boarding」は、土木・建設業に特化したeラーニングサービスです。
1本3分程度の動画で測量やCADの基礎から安全衛生教育まで、スマホやPCでいつでもどこでも学べます。
2週間の無料トライアルですべてのコンテンツをお試しいただけますので、まずはお気軽に資料請求してみてください。
目次
土木の新入社員研修資料の基礎
効果的な新入社員研修を実施するには、まず研修資料の役割や法的根拠となる基礎を正しく理解しておく必要があります。
基礎知識を押さえることで、内容に一貫性のある質の高い資料を作成できます。
土木の新入社員研修資料の基礎
- 研修資料が果たす3つの役割
- 法令・ガイドラインと安全衛生教育
- 研修センターの概要(期間・対象・部門)
それぞれのポイントを1つずつ解説します。
研修資料が果たす3つの役割
新入社員向けの研修資料は、新人の成長と定着を促す上で重要な3つの役割を担います。
役割を意識して資料を作成することで、研修の効果を最大限に高められます。
研修資料の3つの役割
- 安全意識の徹底
- 基礎知識・スキルの標準化
- 早期離職の防止と組織への適応促進
これらの役割を果たす資料は新入社員がスムーズに職場に適応し、長期的に活躍するための土台となります。
自社の状況に合わせて、特にどの役割を重視するかを明確にして資料作成を進めましょう。
法令・ガイドラインと安全衛生教育
土木業における新入社員研修では、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育が義務づけられています。
法令を遵守した研修資料を作成することは企業の責任であり、従業員を災害から守るための基本です。
特に、雇入れ時の安全衛生教育に関する項目は、省略が認められていません。
「労働安全衛生規則第35条」で定められている教育項目は、以下のとおりです。
| 項目 | 教育内容 |
|---|---|
| 機械に関する知識 | 機械や原材料の危険性・有害性・取り扱い方法 |
| 安全装置・保護具 | 安全装置や保護具の性能・点検・正しい使用方法 |
| 作業手順に関する知識 | 仕事の進め方・作業手順・安全な作業方法 |
| 作業開始時の点検 | 作業を始める前に行うべき点検事項や手順 |
| 疾病の原因及び予防 | 当該業務に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防に関する情報 |
| 整理・整頓・清掃 | 現場の整理・整頓・清潔の維持(3S活動) |
| 事故時の応急措置 | 災害発生時の応急手当・退避の方法・連絡体制 |
| その他、安全衛生に必要な事項 | 上記以外に、その事業場の業務に関して必要な安全衛生知識(ヒューマンエラー、有害物質、メンタルヘルスなど) |
これらの法定項目を網羅した資料を用意し、研修記録を保管しておく必要があります。
参考:厚生労働省 職場のあんぜんサイト|安全衛生教育
安全衛生教育を効率よく学習できる「Construction Boarding」
安全衛生教育を効率よく実施したい方には、Construction Boardingがおすすめです。
建設業に特化したeラーニングで、労働安全衛生法で定められた教育項目を網羅したカリキュラムを提供しています。
ポイント
人材開発支援助成金の対象にもなるため、コストを抑えながら法令を遵守した質の高い安全教育を実現できます。
2週間の無料トライアルで、実際の使い勝手を試してみてください。
研修センターの概要(期間・対象・部門)
研修資料を作成する前に、自社が実施する研修の全体像を明確にしましょう。
「いつ、誰に、何を教えるのか」という基本方針を固めることで、資料の内容が充実します。
一般的に、研修は以下のような要素で構成されます。
| 要素 | 概要 |
|---|---|
| 期間 | 1~3ヶ月程度の期間を設定して座学と現場実習を組み合わせる企業が多い |
| 対象 | 主に4月に入社する大学卒・高校卒の新入社員が対象。中途採用者向けに別途プログラムを用意する場合もある |
| 部門 | 土木施工管理職・測量技術者など、配属される部門や職種に応じた専門研修を組み込む |
最初に研修の全体計画を設計することで、その後の資料作成がスムーズに進みます。
会社の規模や育成方針に合わせて、最適な研修の形を検討しましょう。
参考記事:建設業の安全教育ネタ47選|マンネリを解消する事例完全ガイド
土木の新入社員研修資料に必要な項目
新入社員研修の資料には社会人としての心構えから専門知識まで、幅広く具体的な項目を盛り込む必要があります。
ここでは、土木業界の研修資料に必要な項目を紹介します。
土木の新入社員研修資料に必要な項目
- 測量・土木基礎知識のポイント
- 雇入れ時安全衛生教育の構成
- CAD/Excel基本操作マニュアル
- 新入社員の仕事の流れと心得
- プライベート支援&チームビルディング
これらの項目を網羅することで、新入社員が現場で即戦力として活躍するための土台を築けます。
測量・土木基礎知識のポイント
現場作業の基本となる測量と土木の基礎知識に関する項目を資料に入れます。
専門用語や基本的な作業内容を事前にインプットしておくと、現場でのOJTがスムーズに進みます。
新入社員がつまずきやすいポイントを重点的に解説するのが効果的です。
新入社員がつまずきやすいポイント
- 丁張り・墨出しの手順
- レベル・トランシットの据え方と使い方
- TS(トータルステーション)の基本操作
- 土質試験(標準貫入試験など)の種類と目的
- コンクリートの種類と打設時の注意点
これらの知識はすべての土木技術者にとって重要な知識です。
図や写真を多く用いて、視覚的に理解しやすい資料作りを心がけましょう。
雇入れ時安全衛生教育の構成
安全な職場環境を維持するために、法令で定められた安全衛生教育の項目は必ず資料に記載します。
「法令・ガイドラインと安全衛生教育」で解説した労働安全衛生規則第35条の内容を網羅したカリキュラムを作成しましょう。
座学だけでなく「保護具の正しい使い方」「足場からの転落防止措置」などの実技を交えた研修も必要です。
CAD/Excel基本操作マニュアル
現場での作図や書類作成に便利なCADソフトとExcelの基本操作マニュアルを用意します。
建設業界でよく使う機能に絞って解説するのがポイントです。
自己学習できるマニュアルがあれば、配属後のスキルアップもスムーズになります。
マニュアルに含めるべき基本操作の例は、以下のとおりです。
| ツール | 基本操作の例 |
|---|---|
| CADソフト | ・基本的な作図 ・寸法記入 ・図面の尺度設定 ・レイヤーの概念 ・編集コマンド(線分・円・トリムなど) |
| Excel | ・四則演算 ・SUM ・絶対参照・相対参照 ・表・グラフの作成 ・AVERAGE・IFなどの基本関数 |
また、ショートカットキーの一覧やよくあるトラブルの対処法なども記載しておくと、より実用的なマニュアルになります。
参考記事:CAD研修で社員のスキルを底上げする方法|おすすめの研修も紹介
CADを学習できるeラーニング「Construction Boarding」
CADの基礎スキル習得には、Construction Boardingの活用が効果的です。
建設業界で使われる基本的な操作に特化した研修コンテンツを用意しており、新入社員が自分のペースで学習を進められます。
Construction BoardingのCAD研修の特徴
- 実務で必要な操作を動画でわかりやすく解説
- つまずきやすいポイントを丁寧にフォロー
- OJTの補助教材として配属後のスキルアップに活用可能
Construction Boardingは、2週間の無料体験でCAD研修を始められます。
まずは一度、その使いやすさを体験してみてください。
新入社員の仕事の流れと心得
新入社員が現場配属後の1日をイメージできるよう、具体的な仕事の流れを時系列で示します。
また、社会人としての基本的な心構えも合わせて教えることで、職場への適応を促します。
「何をしていいかわからない」という新入社員の不安を解消することが目的です。
例えば、仕事の流れとして以下を紹介します。
新入社員の仕事の流れと心得
- 朝礼での挨拶
- KY活動
- 現場巡回
- 写真管理
- 書類作成
加えて、報連相やメモを取る習慣などの基本的な仕事の進め方を記載しましょう。
プライベート支援&チームビルディング
業務だけでなく、新生活を支える福利厚生や社内コミュニケーションに関する情報も記載します。
新入社員のプライベートな不安を軽減し、組織への帰属意識を高める効果が期待できます。
特に、地方から出てきた新入社員にとっては生活面のサポート情報が重要です。
プライベート支援の例
- 社宅
- 住宅手当
- 資格取得支援制度
- 奨学金返済支援制度
また、チームビルディング施策として歓迎会や社内イベント、メンター制度などを案内して同期や先輩との交流を促しましょう。
土木の新入社員研修カリキュラム設計
効果的な研修には、体系的なカリキュラム設計が不可欠です。
ここでは、具体的なモデルケースや長期的な育成体制など、カリキュラムを設計する上でのポイントを解説します。
土木のカリキュラムを設計する上でのポイント
- 2ヶ月モデルケース:座学+実習
- ステップアップ体制:1~5年目
- 実物大模型を使った現場実習
- 評価とフィードバック方法
これらの要素を組み合わせ、自社に合った育成計画を立てましょう。
2ヶ月モデルケース:座学+実習
新入社員研修の期間として、座学と現場実習を組み合わせた2ヶ月間のモデルケースを紹介します。
最初の1ヶ月で基礎知識を学び、次の1ヶ月で実践的なスキルを身につける流れが効果的です。
このバランスが、新入社員のスムーズな現場デビューを後押しします。
具体的な研修内容は以下のとおりです。
| 期間 | 主な研修内容 |
|---|---|
| 1ヶ月目:座学中心 | ・社会人マナー・会社の理念・就業規則 ・測量・土質・材料など土木の基礎理論 ・CADソフトやExcelの基本操作 ・労働安全衛生法などの関係法令 |
| 2ヶ月目:実習中心 | ・先輩社員とのOJT ・測量実習、丁張り実習 ・複数の工事現場の見学 ・日報や簡単な報告書の作成演習 |
座学で学んだことを実習で試す機会を設けることで、知識の定着を図ります。
ステップアップ体制:1~5年目
新入社員研修だけでなく、入社後1年から5年目までを見据えた長期的なステップアップ体制を整えることが重要です。
年次ごとに明確な目標を設定することで、社員の学習意欲やモチベーションの維持につながります。
年代別の育成目標の例は、以下のとおりです。
| 年次 | 育成目標の例 |
|---|---|
| 1年目 | ・現場の雰囲気に慣れ、一連の仕事の流れを覚える ・先輩の指示のもと、基本的な作業を確実にこなす |
| 2~3年目 | ・小規模な作業の責任者を担当する ・2級土木施工管理技士の資格取得を目指す |
| 4~5年目 | ・後輩への指導役を始める ・1級土木施工管理技士の資格取得を目指す |
このようなキャリアパスを示すことで、若手社員は将来の目標を具体的にイメージできます。
実物大模型を使った現場実習
安全性を確保しつつ、リアルな現場感覚を養うために、実物大の模型を使った現場実習が有効です。
研修センターなどに設置された模型を使い、実際の現場では危険な作業も安全に体験できます。
特に、高所作業や仮設構造物の組み立てといった、事故リスクの高い作業の教育に適しています。
実物大模型で体験できる実習の例
- 足場の組み立て・解体作業
- 土留め支保工の設置手順
- 型枠の組み立てと配筋の確認
- フルハーネス型墜落制止用器具のぶら下がり体験
危険性を疑似体験することで、安全ルールを守る意識が高まります。
座学で学んだ知識と実際の現場作業とのギャップを埋める上で、効果的な方法です。
評価とフィードバック方法
研修の成果を客観的に評価して個々の課題を明確にするためにも、評価とフィードバックを行いましょう。
具体的な評価とフィードバックの方法は以下のとおりです。
| 方法 | 具体例 |
|---|---|
| 評価 | ・研修内容の理解度を確認するテストの実施 ・研修日報やレポートの提出 ・実技演習でのスキルチェック |
| フィードバック | ・上司やメンターとの定期的な1on1面談 ・目標管理シートを用いた進捗確認と課題共有 |
一方的に評価するだけでなく面談を通じて本人の意見を聞き、次の目標を一緒に設定する姿勢が大切です。
土木の新入社員研修資料|作成手順
質の高い研修資料を効率的に作成するには、手順を踏んで進めることが大切です。
ここでは、資料作成の具体的な手順を3つのステップで解説します。
土木の新入社員研修資料の作成手順
- テンプレート・既存資料の棚卸し
- 一次情報(写真・動画・事例)の挿入
- PDF・PPTエクスポートと共有設定
この手順に沿って作業を進めることで、抜け漏れなく分かりやすい資料を作成できます。
参考記事:建設業の新入社員研修資料の作り方完全ガイド|資料の入手ルートも解説
テンプレート・既存資料の棚卸し
研修資料を作成する際はゼロから始めるのではなく、まず社内にある既存の資料やテンプレートを整理します。
テンプレートや資料を活用することで、作成時間を短縮しつつ内容の一貫性を保てます。
整理する資料の例
- 過去の研修で使用したPowerPoint資料
- 作業手順書や各種マニュアル
- 過去の工事で撮影した写真や動画
- 安全教育に関する資料
これらの既存資料をベースにすることで、構成の骨子をスムーズに作れます。
一次情報(写真・動画・事例)の挿入
既存資料に自社ならではの一次情報を加えることで、資料の質は格段に向上します。
テキストだけの資料よりも、写真や動画を盛り込むほうが新入社員の理解を促進可能です。
特に、自社の現場で撮影した写真や先輩社員が登場する動画は、研修内容の説得力を高めます。
| 一次情報の種類 | 具体的な活用例と効果 |
|---|---|
| 写真・図 | 自社の現場写真や使用機械の写真を用いる。良い例・悪い例を対比で見せるとわかりやすい |
| 動画 | 作業の流れや機械の操作方法を動画で見せる。先輩社員のインタビューなども効果的 |
| 社内事例 | 過去の成功事例やヒヤリハット事例を共有する。研修内容がより自分事として捉えやすくなる |
自社の一次情報を活用して、新入社員の成長につながる資料を作成しましょう。
PDF・PPTエクスポートと共有設定
完成した研修資料は適切な形式でファイルに書き出し、共有設定を行います。
誰がどのように資料を使うのかを想定して、最適な形式を選びましょう。
主なファイル形式の特徴と適切な用途は、以下のとおりです。
| 形式 | 特徴と適切な用途 |
|---|---|
| レイアウトが崩れず、意図しない編集を防げる。配布・閲覧用の最終版として適している | |
| PowerPoint | 発表者や各部署で内容を追記・編集しやすい。テンプレートとしての共有に適している |
作成した資料は、クラウドストレージなどで共有し「閲覧のみ」「編集可」といった権限を適切に設定します。
これにより、資料のバージョン管理がしやすくなり常に最新の状態で研修を行えます。
研修後のフォロー・成長支援
研修で学んだ知識を定着させて新入社員の成長を促すには、研修後のフォロー体制が重要です。
ここでは、新入社員の定着と成長を支援するための仕組みを紹介します。
研修後のフォロー・成長支援
- OJTとメンター制度の設計
- キャリアパスと目標管理シート
- チームワーク醸成・社内SNS活用
これらの仕組みを組み合わせ、新入社員が安心して働ける環境を整えましょう。
OJTとメンター制度の設計
研修後のフォローアップとして、OJTとメンター制度は中心的な役割を果たします。
現場での実践的な指導と、精神的なサポートを両立させることが、新入社員の早期離職防止につながります。
それぞれの制度の目的を理解し、適切に設計・運用することが大切です。
各制度の目的と役割は、以下のとおりです。
| 制度 | 目的と役割 |
|---|---|
| OJT | 実務を通じて、仕事に必要な知識や技術を指導する。トレーナーは主に同じ部署の先輩社員や上司が担当する。 |
| メンター制度 | 仕事の進め方から人間関係の悩みまで、新入社員の不安を解消する精神的な支えとなる。メンターは他部署の先輩社員が担当することも多い。 |
この2つの制度を連携させることで、業務とメンタルの両面から新入社員を支えられます。
参考記事:建設業OJTを始める前にやるべき準備と8つのテクニックを完全解説
キャリアパスと目標管理シート
新入社員が将来の目標を具体的に描けるよう、キャリアパスの提示と目標管理シートの活用が有効です。
自身の成長ステップを可視化することで、日々の業務に対するモチベーションを高めます。
中長期的な視点での成長を促すための重要な仕組みです。
各ツールの内容と目的は、以下のとおりです。
| ツール | 内容と目的 |
|---|---|
| キャリアパスの提示 | 数年後にどのような役職やスキルを身につけられるのか、具体的なモデルを示す。「5年後には現場のサブリーダー」「10年後には所長」など |
| 目標管理シートの活用 | 本人と上司が面談し、四半期や半年ごとの短期的な目標を設定・共有する。「◯◯の資格を取得する」など、具体的な目標を記載 |
これらのツールは、社員の成長を客観的に評価し、次のステップへ導くための道しるべとなります。
チームワーク醸成・社内SNS活用
新入社員が職場で孤立しないよう、チームワークを育むための取り組みも大切です。
同期や先輩社員との良好な人間関係は、仕事への意欲や定着率に直結します。
定期的な交流の機会を設け、コミュニケーションの活性化を図りましょう。
チームワークを醸成するための取り組み
- 歓迎会や定期的な懇親会
- BBQなどの社内レクリエーション
- 社員旅行
また、社内SNSを活用して、他の現場の様子や日々の成功事例を共有するのも有効な手段です。
他の社員の頑張りを知ることで会社全体の一体感を醸成し、新入社員の孤立感を和らげることにつながります。
参考記事:建設業の人材育成が変わる!若手確保から定着までの6つのコツ
「Construction Boarding」の活用法
新入社員研修の質と効率を両立させたい方は、Construction Boardingの活用をご検討ください。
建設業界に特化した多彩なコンテンツで、貴社の研修を強力にサポートします。
Construction Boardingの導入メリット
- 体系的な知識習得
- 学習の効率化
- 教育の標準化
- 進捗管理の容易化
- コスト削減
集合研修の事前学習やOJTの補完教材として組み合わせることで、新入社員の早期戦力化と定着率向上に貢献します。
2週間無料トライアルですべての機能をお試しいただけるので、ぜひその効果を実感してください。
土木の新入社員研修についてよくある質問(FAQ)
最後に、土木の新入社員研修についてよくある質問にお答えします。
土木新入社員研修資料は何ページ必要?
研修資料に必要なページ数に決まりはありません。
研修期間や内容によって適切なボリュームは変わります。
ポイント
ページ数を目標にするのではなく、必要な情報を網羅できているかを重視しましょう。
目安として1ヶ月~2ヶ月程度の研修の場合は、主要なテキストが50〜100ページ程度に収まることが多いです。
ただし、図や写真を多く使うとページ数は増える傾向にあります。
量よりも質を優先し、新入社員が理解しやすい構成を心がけることが大切です。
無料テンプレートと自社独自資料の違いは?
無料テンプレートと自社独自資料には、それぞれメリットとデメリットが存在します。
両者の違いを理解し、目的に合わせて使い分けることが効果的です。
一般的な内容はテンプレートを使い、専門的な内容は自社で作成するのが良いでしょう。
それぞれの違いは以下のとおりです。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 無料テンプレート | ・作成コストが低い ・準備時間を短縮できる | ・内容が一般的で、自社の実情に合わない場合がある ・新入社員の当事者意識が芽生えにくい |
| 自社独自資料 | ・自社の事例や写真を使え、内容が実践的 ・企業理念や文化を伝えやすい | ・作成に時間と手間がかかる |
社会人マナーなどはテンプレートを活用し、専門技術や安全教育は自社独自で作成するなど、ハイブリッドで運用する方法もおすすめです。
安全衛生教育をPDFとPPTどちらで配布すべき?
研修資料を配布する際は、用途に応じてPDFとPPT(PowerPoint)を使い分けることをおすすめします。
使い分けることで、利便性の向上と意図しない編集の防止を両立できるからです。
具体的な使い分け方は以下のとおりです。
| 形式 | 適切な用途 |
|---|---|
| 新入社員への配布用。端末によるレイアウト崩れがなく、誤って内容を編集されるのを防ぐ | |
| PPT | 講師への共有用。講師が内容を追記・修正したりスライドを再利用したりしやすい |
マスターデータはPPTで管理し、研修の都度PDFに書き出して配布するとスムーズです。
研修センターが遠方の場合のオンライン代替策は?
研修センターでの集合研修が難しい場合、オンライン研修を代替策として活用できます。
座学や知識のインプットが中心の研修は、オンラインでも十分に実施可能です。
近年では、様々なオンラインツールが研修に導入されています。
オンライン研修で活用できる主な手法は以下のとおりです。
eラーニングシステムによる知識習得
- Web会議システム(Zoomなど)でのリアルタイム講義
- 動画マニュアルを用いた作業手順の学習
- VR(仮想現実)技術を使った安全体感教育
ただし、実技やチームビルディングなど、対面でないと効果が薄い項目もあります。
すべてをオンラインで完結させるのではなく、集合研修と組み合わせる「ブレンディッドラーニング」が効果的です。
eラーニングは「Construction Boarding」がおすすめ
eラーニングを新入社員研修で活用したい方は、Construction Boardingがおすすめです。
座学をオフラインの研修からeラーニングに置き換えることで、研修の効率を大幅に改善できます。
現場が忙しい場合は、まず無料でeラーニングの使用感を試してみてください。
研修後のアンケートは必須ですか?
法律で義務づけられているわけではありませんが、研修後のアンケートは実施することをおすすめします。
研修内容を改善するための貴重な情報源になるからです。
受講者の正直な意見を集めることで、研修の課題や改善点が見えてきます。
アンケートに含める質問項目の例
- 研修全体の満足度
- 役に立った、印象に残った研修項目
- 講師の説明のわかりやすさ
- 研修内容の難易度
- 研修の時間配分や設備などに関する意見
アンケート結果を真摯に受け止め、次回の研修に活かす姿勢を見せることが大切です。
資料改訂の推奨サイクルは?
研修資料は少なくとも年に1回、定期的に見直しと改訂を行うことが望ましいです。
資料を毎年改訂したい理由
- 関連法令や各種基準の改正に対応するため
- 前年度の研修アンケートの結果を反映するため
- 新しい技術や工法に関する情報を追加するため
- 社内で発生した新しい事故事例やヒヤリハットを共有するため
一度作成した資料を何年も使い続けると情報が古くなり、実情と合わなくなります。
建設業界の変化に対応するためにも、法改正や新しい技術の情報などを定期的に更新しましょう。
まとめ
最後にもう一度、質の高い研修を実現するためのポイントをまとめておきます。
新入社員研修成功のポイント
- 既存資料を整理してテンプレートとして活用する
- 自社の現場写真や成功事例を資料に盛り込む
- PDFやPowerPointなど用途に応じて形式を使い分ける
- OJTやメンター制度を設計して中長期的な成長を支援する
土木の新入社員研修を成功させるには、計画的な資料作成と中長期的なフォロー体制が重要です。
この記事で紹介した手順を参考に、新入社員の成長を力強く後押しする研修を実現してください。
新入社員研修の準備や運用にはConstruction Boardingが効果的
Construction Boardingは1本3分程度の短時間で学べる設計で、スマホやPCから気軽にアクセスできます。
実際の現場映像やわかりやすいイラストで、土木の基礎から実践まで効率的に学習できるため、若手の早期戦力化と定着率向上に役立ちます。
無料で2週間のトライアルができ、人材開発支援助成金の対象となるため、低コストで質の高い研修を実施できます。
今すぐ資料請求して、貴社の人材育成にお役立てください。
貴社の新入社員研修の参考になれば幸いです。
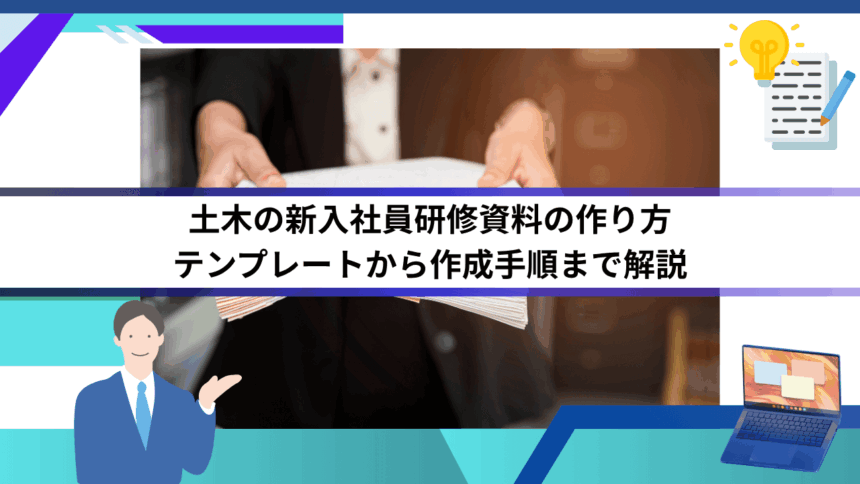
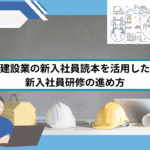
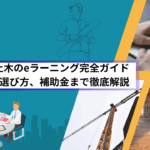

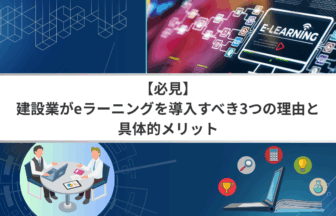


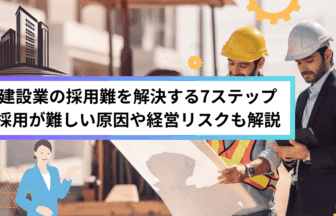
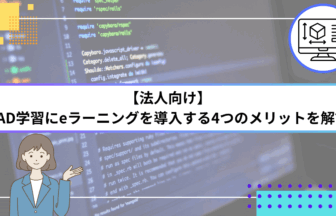










この記事へのコメントはありません。