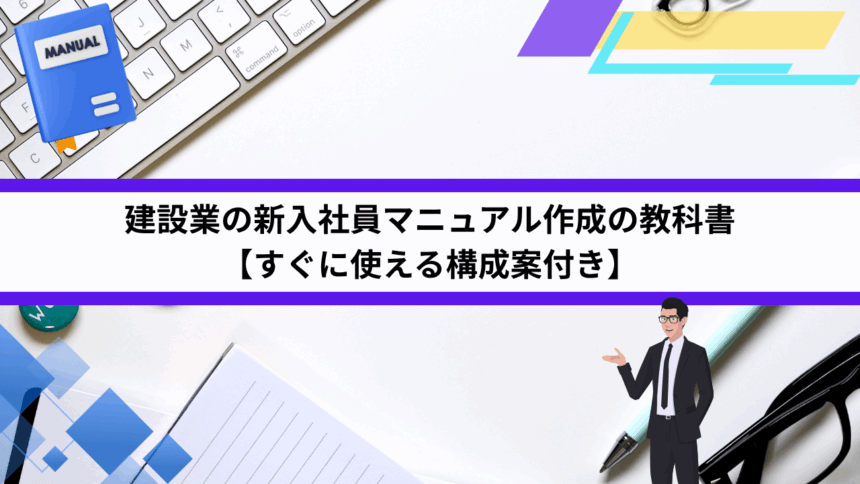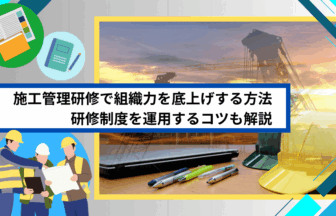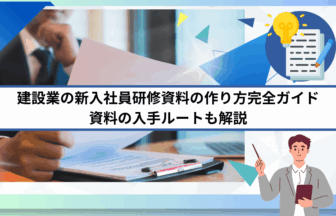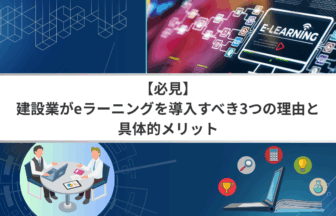「新入社員向けのマニュアルを作りたいけど、何から手をつければいい?」
「指導者によって教え方がバラバラで困っている…」
「読まれないマニュアルを作るのは避けたい…」
このような悩みを抱える建設会社の教育担当者様に役立つ記事です。
この記事でわかること
- 建設業の新入社員マニュアルの基本構成
- 新入社員マニュアルを作成する5つの手順
- マニュアルの内容でツールを使い分けるポイント
効果的な新入社員教育を実現するには、誰が読んでも理解できてかつ現場で使えるマニュアルの作成が重要です。
標準化されたマニュアルを作成すると教育の質が均一になり、指導者によって教え方がバラバラになることを避けられます。
良質な新入社員教育を実現できると、社員の安全意識と定着率の向上につながります。
「でも、具体的にどんなマニュアルを作ればいいのかわからない…」と思いますよね?
この記事では、建設業に特化した新入社員マニュアルの作り方を構成案から作成手順、失敗しないためのポイントまで解説します。
記事を読めば「社員に重宝されるマニュアル」を作成できるでしょう。
建設業の人材教育を効率化するeラーニング
新入社員教育の効率化には、私たちワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」がおすすめです。
1本3分程度の動画で学べるeラーニング形式なので、新入社員が基礎知識から実践的スキルまで効率的に習得できます。
無料で2週間のトライアルができるので、まずは研修で試してみてください。
目次
建設業の新入社員マニュアルとは
建設業の新入社員マニュアルとは、新入社員が建設業界の一員として安全かつ円滑に業務をスタートするための「総合的な手引書」です。
これは単なる業務手順書ではなく、以下の要素で構成されています。
新入社員マニュアルの構成要素
- 企業の理念・ルール
- 安全衛生に関する知識
- 専門技術の基礎
- ビジネスマナー
特に、建設業は現場の状況が日々変化し、多様な専門家と連携して仕事を進める特殊な環境です。
そのため、教育担当者による指導のばらつきをなくし、知識と安全の基準を全社で統一するという役割が大きくなります。
マニュアルは新入社員にとっていつでも立ち返れる存在であり、企業にとってはリスクを管理し、人材を育てるための優れたツールです。
離職率・事故率を下げる効果
標準化されたマニュアルは教育担当者による指導のばらつきを防ぎ、新入社員に一貫した知識と安全基準を提供できます。
誰から教わっても同じ水準の安全行動が身につくため、危険な作業への理解が深まります。
マニュアルがもたらす効果
- 企業理念やキャリアパスの明示による定着促進
- KY活動事例の共有による安全意識の向上
- ヒューマンエラーに起因する労働災害リスクの抑制
マニュアルは新入社員が安心して働ける環境を構築し、結果的に離職率と事故率の低下につながります。
最新法令と2024年問題への対応ポイント
新入社員マニュアルは、法改正や「2024年問題」のような業界全体の課題に対応する上でも大切な資料です。
特に、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制は、すべての従業員が知っておくべき内容です。
ポイント
マニュアルに規制内容を明記し、社内ルールや勤怠管理システムの利用方法などもまとめます。
マニュアルを通じて法令遵守の体制を周知徹底しましょう。
研修の効率化で生産性を上げるメリット
指導者によって教え方や内容にばらつきがあると、新入社員の理解度に差が生じます。
標準化されたマニュアルがあると新入社員研修を効率化でき、組織全体の生産性向上につながります。
マニュアルがもたらす研修効率化のポイント
- 教育担当者の指導負担を軽減
- 教える内容のばらつきを防いで教育レベルを均質化
- OJT(実地研修)と組み合わせることで相乗効果を発揮
- 新入社員が自分のペースで予習・復習できる環境の構築
教育担当者は本来の業務に集中でき、新入社員は自律的に学習を進められます。
建設業の新入社員マニュアルの基本構成
建設業の新入社員マニュアルの基本構成は、以下のとおりです。
建設業の新入社員マニュアルの基本構成
- 会社概要と業界全体像
- 安全衛生教育
- 作業手順・チェックリスト
- ビジネスマナー
- 評価基準
- キャリアパス
それぞれの項目を1つずつ解説します。
会社概要と業界全体像
新入社員の帰属意識と目的意識を高めるために、自社がどのような会社で、建設業界の中でどういう立ち位置にいるのかを記載します。
自分が働く会社の理念や歴史、社会的な役割を理解すると、日々の業務に意義を見いだしやすくなります。
ポイント
会社の沿革や経営理念、主な事業内容なども紹介しましょう。
新入社員が「この会社で頑張りたい」と思えるような情報を提供し、組織の一員としての自覚を形成することが目標です。
安全衛生教育
建設業のマニュアルにおいて、安全衛生教育は欠かせません。
新入社員の命と健康を守るためにも、安全に関する基礎知識を徹底的に教えます。
ポイント
建設現場には多くの危険があり、知識不足は重大な事故につながる可能性があります。
具体的なルールや注意点を記載し、いつでも確認できるようにしておきましょう。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 安全衛生の基本方針 | 会社の安全に対する考え方や目標を明示 |
| 労働安全衛生法 | 雇入れ時教育で定められた必須項目を解説 |
| 危険予知活動 | リスクアセスメントの考え方と具体的な進め方を説明 |
| 保護具・安全装備 | 正しい着用方法や点検手順を図や写真で紹介 |
| 緊急時の対応 | 事故発生時や自然災害時の連絡体制と行動手順 |
具体的な教育項目をマニュアルに落とし込むことで、新入社員は安全に行動するための知識を体系的に学べます。
実物の写真やイラストを多用し、視覚的に理解しやすい工夫も大切です。
参考記事:建設業の安全教育ネタ47選|マンネリを解消する事例完全ガイド
作業手順・チェックリスト
具体的な作業手順やチェックリストをマニュアルに含め、業務の標準化を図ります。
これにより、誰もが一定の品質で安全に作業を進められるようになります。
また、業務内容に応じて複数のマニュアルやチェックリストを用意すると効果的です。
作業マニュアル・チェックリストの例
- 主要な建設機械の操作手順書
- 各工程における品質管理チェックリスト
- 始業前点検や安全パトロールの確認リスト
- 高所作業や重機作業の安全基準書
経験の浅い社員でも確実に業務を遂行できるサポート体制を整えましょう。
ビジネスマナー
施主や近隣住民に対しての言動は、会社の評価に直結します。
新入社員に自社で活躍してもらうためにも、以下のビジネスマナーを教育する必要があります。
基本的なビジネスマナー
- 挨拶
- 名刺交換
- 正しい言葉遣い
- 朝礼での適切な振る舞い
- 職人さんとのコミュニケーションの取り方
マニュアルで教育するだけでなく、日々の業務で実践していくことで、新入社員の円滑なコミュニケーション能力の習得を促します。
評価基準
新入社員が何を目標にすれば良いのかを明確にするため、評価基準を記載します。
どのような行動や成果が評価されるのかを具体的に示すことで、新入社員は主体的にスキルアップを目指せます。
評価項目の例
- 資格取得目標
- 習得すべき技術項目
- 業務姿勢
- 安全行動
明確な評価基準と定期的なフィードバックを組み合わせることで、新入社員は成長を実感できます。
人材定着にもつながるため、公正な評価制度を設けてみてください。
キャリアパス
自社で働き続けることで、将来どのような専門家になれるのかを示す必要があります。
将来の姿を具体的にイメージできると、目の前の仕事に対する意欲が高まります。
ポイント
例えば、5年目・10年目で担当する業務内容や役職、取得できる資格などを示しましょう。
また、現場の施工管理者から工事部長や支店長へ進む道など、複数のキャリアモデルを提示することも考えられます。
新入社員に明確なキャリアを示すとモチベーションが高まり、結果として早期離職を防ぎやすくなります。
建設業の新入社員マニュアルを作成する5つの手順
建設業の新入社員マニュアルは、以下5つの手順で作成します。
新入社員マニュアル作成の5ステップ
- 目的・到達目標を設定する
- 既存資料と公的リソースを収集する
- 構成の設計を作成する
- 構成を基にマニュアルを作成する
- マニュアルを定期的にフィードバックする
手順に沿って1つずつ解説します。
①目的・到達目標を設定する
ゴールが曖昧だと内容が散漫になり、マニュアルの効果が薄れてしまいます。
そのため、以下のような目的や到達目標を最初に設定しましょう。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 目的の例 | ・新入社員の不安を解消して入社後3年以内の離職率を改善する ・安全意識を高めて労働災害の発生リスクを低減する |
| 到達目標の例 | ・入社1ヶ月で雇入れ時安全衛生教育の主要項目を説明できる ・入社3ヶ月で現場の頻出用語の意味を理解し、職人さんとの会話で使用できる |
到達目標は「何を、いつまでに、どのレベルまで習得してほしいのか」を具体的に言語化することがポイントです。
現場のOJT担当者や配属先の上司にもヒアリングし、現場が新入社員に求めるスキルや知識を明確にすると、実用的なマニュアルを作成できます。
②既存資料と公的リソースを収集する
次に、マニュアル作成の材料となる情報を社内外から幅広く収集します。
| 収集する資料のカテゴリ | 収集する資料の例 |
|---|---|
| 社内資料 | 過去の研修テキストや作業手順書、ヒヤリハット報告書 |
| 公的リソース | 厚生労働省や国土交通省の資料 |
| その他 | 業界団体のテキスト、メーカー提供の施工手順書 |
公的機関の資料は、法令遵守の観点からも目を通しておきましょう。
これらの情報を集めて整理することで、信頼性と網羅性の高いマニュアルを作成できます。
参考記事:建設業の新入社員研修資料の作り方完全ガイド|資料の入手ルートも解説
③構成の設計を作成する
集めた情報を基に、マニュアル全体の構成を作成します。
情報が整理されていないマニュアルは、知りたい情報にすぐたどり着けません。
ポイント
大見出し・中見出し・小見出しと階層を意識して、論理的な流れになるよう組み立てます。
構成案が完成したあとは複数の部署で見てもらい、内容の過不足やわかりにくさがないかを確認しましょう。
誰が読んでも理解しやすく、必要な情報へすぐにアクセスできる構成にすることが大切です。
前述した「建設業の新入社員マニュアルの基本構成」も参考にしてみてください。
誰が読んでも理解しやすく、必要な情報へすぐにアクセスできる構成にすることが大切です。
④構成を基にマニュアルを作成する
この段階で意識したいのは「新入社員が読んで理解できるか」という点です。
マニュアル作成時のポイント
- 専門用語にはふりがなや注釈を入れる
- 具体的な数字を用いて抽象的な表現を避ける
- 一文を短くして結論から書くことを心がける
- 図やイラスト、現場で撮影した写真などを多用する
経験者の常識で書くのではなく、専門用語はわかりやすく解説し、図解や写真などを用いて視覚的に読みやすくしましょう。
読み手の負担を減らして「わかりやすい」と感じてもらえると理想的です。
⑤マニュアルを定期的にフィードバックする
マニュアルは一度作成して終わりではありません。
定期的な見直しと更新によって価値を維持・向上させられます。
ポイント
建設業界の最新技術や法令は常に変化するため、古い情報のままでは役に立たないばかりか、誤った知識を教えてしまう可能性があります。
こうしたミスを防ぐためにも、定期的にフィードバックすることが大切です。
| フィードバックのタイミング | 概要 |
|---|---|
| 研修後 | 新入社員へアンケートを実施して課題を洗い出す |
| 現場配属後 | OJT担当者や先輩社員から内容の過不足について意見を聞く |
| 定期的 | 年に1回を目安に法改正や新技術の情報を反映する |
「誰が、いつまでに改訂するのか」という運用ルールを決めておくと、継続的な改善の仕組み作りにつながります。
現場の声を反映し続け、マニュアルの価値を高めていきましょう。
マニュアルの内容でツールを使い分けるポイント
新入社員マニュアルは、内容に応じてツールを使い分けると、学習効果が高まります。
マニュアル作成で活用できるツール
- PDF・パワーポイント
- 動画
- eラーニング
- Excel
- VR/AR教材
それぞれのツールの特徴と、効果的な活用場面を解説します。
PDF・パワーポイント:雇入れ時の安全衛生教育に最適
PDFやパワーポイントは、体系的な知識を伝える「雇入れ時の安全衛生教育」のような座学研修に適しています。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 汎用性 | ほとんどのPCで閲覧・作成が可能 |
| 更新の容易さ | 法改正などにあわせて内容の一部を修正しやすい |
| 配布のしやすさ | メール添付・サーバー共有で一斉に配布できる |
| 最適な内容 | 就業規則・法令知識・企業の基本理念など |
PDFやパワーポイントは多くのPCに標準搭載されており、簡単に作成して配布できます。
また、印刷して手元に保管できるため、新入社員がいつでも復習できる点も便利です。
テキストと図が中心となる基礎知識の伝達には、この2つのツールを利用してみてください。
動画:5S・リスクアセスメントを視覚化
動画は文字だけでは伝わりにくい作業の流れ、危険なポイントなどを視覚的に伝えるのに効果的です。
実際の現場映像や正しい動作を見せることで、新入社員の理解を直感的に促します。
特に、安全に関わる教育では危険な状況をリアルに伝えられます。
動画の活用例
- 5S活動:正しい整理・整頓の手順を映像で示す
- NG行動例:やってはいけない危険な行動を具体的に示す
- 工具の正しい使い方:ベテランの動きをスロー再生で見せる
- リスクアセスメント:ヒヤリハット事例を再現映像で共有する
スマートフォンで撮影・編集できる手軽なものから始められます。
安全教育や技術伝承の質を高めるのに、動画は有効なツールです。
eラーニング:学習の効率化
eラーニングは、基礎知識のインプットから理解度の確認までを一貫して行えます。
個々の進捗に合わせてフォローできるため、教育の質の均一化にもつながる点がメリットです。
ポイント
また、時間や場所を選ばずに学習できるため、多忙な現場でも研修時間を確保しやすくなります。
体系的な知識習得と学習管理を両立させたい場合は、eラーニングが適しています。
参考記事:【必見】建設業がeラーニングを導入すべき3つの理由と具体的メリット
建設業に特化したeラーニング「Construction Boarding」
建設業に特化したeラーニングは、私たちワット・コンサルティングが提供するConstruction Boardingがおすすめです。
マニュアルだけでは伝えきれない現場のリアルな動きや専門知識を、動画とイラストでわかりやすく学べます。
Construction Boardingの特徴
- 建設業に特化した実践的な講座内容
- 1つの動画が3分前後と短く、隙間時間を活用可能
- スマホ・タブレット・PCでいつでもどこでも学習できる
- 現場のリアルな映像やイラストで初心者もわかりやすい
- 理解度テストで知識の定着を確認できる
- 人材開発支援助成金の対象になる場合がある
eラーニングとマニュアルを組み合わせることで、社員は「見て学ぶ」「読んで学ぶ」を両立でき、より学習効果が高まります。
2週間の無料トライアルがあるため、マニュアルと併用しながら貴社の研修で試してみてください。
Excel:教育記録の管理に便利
Excelは研修の受講履歴や資格取得状況を記録・管理するのに便利なツールです。
| 管理項目 | 活用方法 |
|---|---|
| 受講履歴 | 研修ごとに受講日と理解度テストの点数を記録する |
| 資格情報 | 保有資格と有効期限を一覧化して更新時期を管理する |
| 面談記録 | 定期面談の内容や次の目標を時系列で記録する |
関数やフィルター機能を活用すると、必要な情報を素早く抽出したり未受講者をリストアップしたりできます。
また、法令で記録が義務になっている教育履歴の管理にも役立ちます。
VR/AR教材:高所作業の危険体験シミュレーション
VRやARは、現実では体験が難しい危険な状況をシミュレーションできる教育ツールです。
座学では得られない「危険への感度」を安全な環境で高められます。
VR・ARの活用例
- VR:高所作業や足場の組立・解体時の危険を疑似体験できる
- AR:機械にスマートフォンをかざすと点検手順が表示される
導入コストはかかりますが、安全教育においてほかのツールでは得られない高い学習効果が期待できます。
マニュアルと新入社員研修カリキュラムの連携方法
作成したマニュアルは新入社員研修カリキュラムと連携させることで、より学習効果を高められます。
ここでは、研修のフェーズごとにマニュアルを効果的に活用する方法を解説します。
研修のフェーズ
- 座学期:基礎知識のインプット
- 実地期:OJTとマニュアルの併用
- フォロー期:テスト・アンケートでフィードバック
それぞれのフェーズの連携方法を見ていきましょう。
座学期:基礎知識のインプット
座学期はマニュアルを「公式テキスト」として活用します。
この時期の目標は、社会人としての基本や業界の専門知識など、今後の土台となる情報をインプットすることです。
座学期でのマニュアル活用法
- 予習教材として研修前にマニュアルを読むよう指示する
- 講義の補助資料として活用する
- 復習ツールとして研修後にマニュアルの確認を指示する
マニュアルに沿って研修を進めて教育の質を標準化し、新入社員がいつでもどこでも復習できるマニュアルを作成しましょう。
実地期:OJTとマニュアルの併用
現場でのOJTが中心となる実地期は、マニュアルを「実践的な手引書」として活用します。座学で学んだ知識を実際の業務と結びつけることが目標です。
現場で不明点が出た際に、すぐに疑問を解決できるマニュアルを作成することが重要です。
| 活用場面 | 具体的な連携方法 |
|---|---|
| 作業前の準備 | マニュアルの作業手順やチェックリストで段取りを確認する |
| 作業中の疑問 | 先輩に聞く前にまずマニュアルで該当箇所を探す習慣をつけさせる |
| 作業後の報告 | マニュアルのフォーマットを参考にして日報や報告書を作成する |
OJT指導者は「まずマニュアルの〇ページを見てみよう」と促すことで、新入社員の自己解決能力を育てられます。
参考記事:建設業OJTを始める前にやるべき準備と8つのテクニックを完全解説
フォロー期:テスト・アンケートでフィードバック
研修の総仕上げとなるフォロー期は、マニュアルを「理解度を測る物差し」として活用します。
これまでに学んだ知識がどれだけ定着しているかを確認し、個々の課題を明確にすることが目的です。
また、マニュアルの改善点を見つけるためのフィードバックも行います。
| 活用場面 | 具体的な連携方法 |
|---|---|
| 習熟度テストの作成 | マニュアルの内容からテスト問題を作成する |
| アンケートの実施 | マニュアルでわかりにくい箇所をヒアリングし、次年度の改訂に活かす |
| 面談の実施 | マニュアルの評価基準やキャリアパスのページを基に、個人の目標設定や課題を話し合う |
このフィードバックのサイクルを回すことで、新入社員の成長と教育プログラムの改善を同時に進められます。
建設業の新入社員マニュアルでよくある失敗例
建設業の新入社員マニュアルでよくある失敗例を解説します。
よくある失敗例
- 専門用語の解説が不十分で内容がよくわからない
- 文字ばかりで内容がわかりにくい
- 情報を探しにくい
- 情報過多で読まれない
- マニュアルの内容が現場に合わない
失敗例を事前に把握して「読まれないマニュアル」になるのを防ぎましょう。
専門用語の解説が不十分で内容がよくわからない
未経験者は専門用語の意味を知らないため、解説が不十分だとマニュアルを読み進める意欲を失います。
マニュアル作成者は「これくらい知っているだろう」と思っても、未経験者にとってはまるで意味がわからないというケースはよくあります。
ベテラン社員が無意識に使っている略語や現場特有の言い回しは、新人にとっては外国語のようなものです。
そのため、以下のように専門用語をわかりやすく解説しましょう。
専門用語を解説する際のポイント
- 巻末に用語集を作成する
- 専門用語には必ず注釈やふりがなを付ける
- 社内だけで通じる略語や隠語の使用は避ける
新人が1人で読んでも理解できる言葉選びを徹底することが「読まれるマニュアル」を作成するために大切です。
文字ばかりで内容がわかりにくい
文字ばかりのマニュアルは内容が理解しにくく、記憶にも残りません。
特に、安全確認のような一連の動作は、文章だけで正確に伝えるには限界があります。
新入社員は頭の中で想像する必要があり、誤った解釈をしてしまう可能性が高くなります。
誤った解釈を防ぐためにも、以下のような視覚的要素を含めることが重要です。
| 視覚的要素 | 具体的な活用例 |
|---|---|
| 写真・イラスト | 保護具の正しい装着状態とNG例の比較、工具の各部名称の図解 |
| 図・グラフ | 組織図や指揮命令系統の図、安全成績の推移を示すグラフ |
| 動画 | ベテランによる手元の作業風景、危険予知活動の模擬実演 |
文字と視覚的要素を組み合わせることで、新入社員はより早く正確に業務内容を学べます。
情報を探しにくい
マニュアルは業務中に「あれ、どうするんだっけ?」と困ったときにすぐ調べられることで価値を発揮します。
どこに何が書かれているかわかりにくい構成は、いざという時に使えません。
実務でマニュアルを役立ててもらうためにも、以下のような工夫が必要です。
検索性を高める対策
- 章・節・項のレベルまで階層を分けて詳細な目次を作成する
- 専門用語から該当ページを探せる索引を巻末に設ける
- よくある質問のページを作成する
社員が知りたい情報へすぐたどり着けるように、詳細な構成を設計しましょう。
情報過多で読まれない
「詳しく解説したい」という気持ちが強すぎると、情報を詰め込みすぎて社員の学習意欲を下げがちです。
分厚いマニュアルを渡された社員は情報量に圧倒され、どこから手をつけていいかわからなくなります。
この失敗を防ぐためにも、マニュアルの範囲を明確に決めましょう。
ポイント
例えば「入社3ヶ月で自立するために必要な情報に限定する」「必須知識と補足知識を明確に分ける」などが考えられます。
より専門的な情報はOJTや別の専門資料で解説します。
すべての情報をまとめるのではなく「必要なことだけをわかりやすく伝える」という視点がマニュアル作成のポイントです。
マニュアルの内容が現場に合わない
マニュアルに書かれているルールや手順が現場仕事と異なると、社員は「マニュアルは役に立たない」と判断します。
マニュアルへの信頼が失われると、ほかの情報まで読まれなくなります。
誤った手順で作業を行うことにもなりかねず、事故につながる恐れがあるため注意が必要です。
| マニュアルの内容が現場と合わない原因 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 作成者が現場を知らない | 複数の現場から若手・ベテランをメンバーに加えて、共同でマニュアルを作成する |
| 特定の現場のルールしか反映していない | 全社共通ルールと現場ごとの個別ルールを明確に区別して記載する |
| 作成後のメンテナンスが不足している | 年1回のフィードバックを制度化し、改訂の責任者と期限を明確にする |
マニュアルの内容を「現場の実態」に合わせ続けると、価値の高い情報として社員から重宝されます。
建設業の新入社員マニュアルでよくある質問
最後に、建設業の新入社員マニュアルでよくある質問にお答えします。
建設業の新入社員マニュアルは誰が作成するといい?
特定の部署や担当者に任せるのではなく、複数の関係者でプロジェクトチームを組んで作成することをおすすめします。
人事部だけでは現場の実態がわからず、現場の担当者だけでは教育的な視点が抜け落ちる可能性があるからです。
| メンバーの例 | 役割 |
|---|---|
| 人事・教育担当者 | プロジェクト全体の進行管理、教育的視点からの構成案の作成 |
| 現場のベテラン社員 | 専門的な知識や実践的なノウハウの提供 |
| 現場の若手社員 | 「新入社員がどこでつまずきやすいか」という読者視点からの意見の提供 |
多様な視点を取り入れることで、マニュアルの質は向上します。
雇入れ時の安全衛生教育で必要な項目は?
雇入れ時の安全衛生教育で必要な項目は、以下のとおりです。
法令で定められた主な教育項目
- 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法
- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法
- 作業手順
- 作業開始時の点検
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
- 整理、整頓及び清潔の保持
- 事故時等における応急措置及び退避
- その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
雇入れ時の安全衛生教育は「労働安全衛生法」で定められた事業者の義務であり、省略できません。
これらの項目をマニュアルにまとめ、自社の業務内容に合う具体的な事例を加えて解説しましょう。
PDFと動画はどちらが効果的?
どちらか一方が優れているわけではなく、伝える内容によって使い分けると効果的です。
| ツール | 適した内容 | メリット |
|---|---|---|
| PDF・パワーポイント | 就業規則・法令などの文章情報や体系的な知識 | 検索性が高く更新が容易 |
| 動画 | 工具の正しい使い方のような動作、危険感受性を高める内容 | 直感的に理解しやすく記憶に残りやすい |
両方をうまく組み合わせるために「マニュアルに動画のQRコードを埋め込む」「理解度テストの動画をマニュアルに設置する」などの方法もおすすめです。
マニュアルを更新する頻度の目安は?
年1回の定期的な見直しを基本として、随時更新することが望ましいです。
法改正や新技術導入などの変化に迅速に対応しないと、マニュアルの情報はすぐに陳腐化します。
随時更新が必要になるタイミングの例
- 関連する法律が改正されたとき
- 新しい機械や工法を導入したとき
- 新入社員へのアンケートで改善要望が多いとき
- 社内で労働災害や重大なヒヤリハットが発生したとき
「年に〇回」と形式的に決めるだけでなく、常に最新の状態を保つためのルールを設けましょう。
まとめ
この記事では、建設業の新入社員マニュアルの作成方法を解説しました。
最後に、マニュアル作成の5つの手順をもう一度確認しましょう。
新入社員マニュアル作成の5ステップ
- 目的・到達目標を設定する
- 既存資料と公的リソースを収集する
- 構成の設計を作成する
- 構成を基にマニュアルを作成する
- マニュアルを定期的にフィードバックする
現場で役に立つマニュアルを作成し、新入社員の早期戦力化と定着率向上を目指しましょう。
マニュアルと並行して新入社員教育を進める際は、eラーニングConstruction Boardingの活用が効果的です。
体系的な動画コンテンツでマニュアルの内容を補完し、新入社員の理解をさらに深めます。
ポイント
スマートフォンやPCからいつでも学習でき、1本3分程度の短時間設計なので、忙しい現場でも無理なく続けられます。
Construction Boardingは人材開発支援助成金の対象となるため、コストを抑えながら質の高い研修を実現できます。
「まずは無料で試してみたい」という方は、お気軽に資料請求してみてください。
貴社の新入社員教育の参考になれば幸いです。