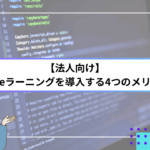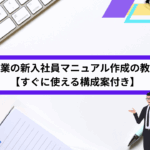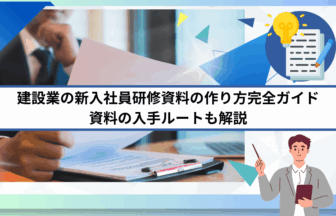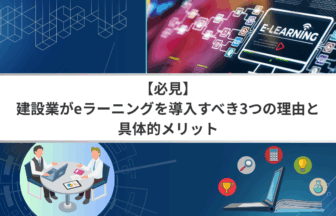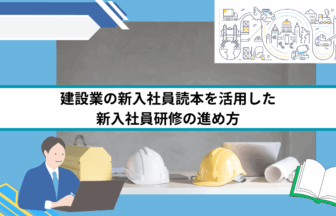「建設業の研修はどんな内容にすればいいの?」
「若手の離職を防ぐ効果的な研修を設計したい」
「研修を計画的に進めるための具体的な手順が知りたい」
このような悩みを抱える建設会社の経営者様、研修担当者様に向けた記事です。
この記事でわかること
- 建設業の研修内容の種類と対象別カリキュラム
- 建設業の研修がもたらす3つのメリット
- 効果を最大化する建設業の研修設計5ステップ
効率的に育成を進めるためにも、社員のレベルに合わせて研修を提供することが大切です。
「でも、何から手をつければいいのかわからない…」と思いますよね?
この記事を読めば、現場の課題を解決できる効果的な研修を設計できるようになります。
若手の育成を効率的に進めたい方は、最後まで読んでみてください。
建設業におすすめのeラーニング
建設人材の教育には、私たちワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」がおすすめです。
1本3分程度の動画で学べるeラーニング形式なので、忙しい現場でも効率的に基礎知識から実践的なスキルまで習得できます。
1本3分程度の動画で学べるeラーニング形式なので、忙しい現場でも効率的に基礎知識から実践的なスキルまで習得できます。
無料から始められるので、研修で試してみてください。
目次
建設業の研修の現状と課題
最初に、建設業の研修の現状と課題を解説します。
建設業界が抱える主な課題
- 技能労働者の不足が続く背景と影響
- 若手離職率・人手不足倒産のリスク
- DX・自動化の遅れ
- 安全管理の強化
公的なデータを交えながら1つずつ解説するので、研修内容を考える際の参考にしてみてください。
技能労働者の不足が続く背景と影響
建設業において技能労働者は慢性的に不足しており、業界全体が抱える根深い課題です。
国土交通省の調査によると、建設技能者のうち29歳以下は約12%であるのに対し、60歳以上が約26%を占めています。
この深刻な高齢化と若者離れは、技術継承を困難にします。
ベテランがもつ熟練の技術が若手へ伝わる前に退職してしまうため、将来的には工事の品質低下や工期の遅延につながる恐れがあります。
技能労働者の確保と育成は、企業の存続に直結する重要な課題です。
参考記事:建設業の人材育成が変わる!若手確保から定着までの6つのコツ
若手離職率・人手不足倒産のリスク
若手社員の離職率が高い点も、建設業が長年にわたって抱える課題です。
国土交通省の調査では、建設業における新卒3年以内の離職率は大卒者で約30%、高卒者で約40~50%です。
ご覧のように、製造職よりも離職率が高い傾向にあります。
人手不足の現場では新入社員への教育が手薄になりがちで、負担の大きさから早期離職につながるケースが多くあります。
若手離職が引き起こす悪循環
- 社員の業務負担が増加
- 研修やサポート体制がさらに手薄になる
- 職場の雰囲気が悪化して新たな離職者を生む
- 生産性が低下して企業の競争力が落ちる
- 人手不足が原因で倒産のリスクが高まる
こうした悪循環を断ち切るには、若手が安心して働けて成長を実感できる研修制度の整備が不可欠です。
参考記事:施工管理の新人教育で失敗しない!新人が成長する研修10ステップ
DX・自動化の遅れ
DXや自動化への対応の遅れが、生産性や安全性の向上を阻む原因となっています。
| 課題項目 | DX・自動化の遅れによる影響 |
|---|---|
| 生産性 | 紙の図面や書類での管理が多く、情報の共有や修正に時間がかかる |
| 安全性 | ドローン・センサーなどを活用すれば避けられる危険な高所作業や監視業務が残る |
| 人材確保 | デジタルに慣れた若手にとって、アナログな職場は魅力を感じにくい |
DXや自動化の推進は単なる効率化だけでなく、社員の負担軽減や安全確保、そして若手人材にとって魅力ある職場作りにもつながります。
参考記事:施工管理DXで人材不足を解消!建設業の成功事例と導入5ステップ
安全管理の強化
労働災害のリスクを低減させるためにも、安全管理の強化は欠かせません。
厚生労働省の調査によると、2023年の労働災害による死亡者数が最も多かったのは建設業で、全産業の約30%を占めています。
経験の浅い若手社員や外国人労働者が増える中で、安全教育の重要性は高まっています。
ポイント
人手不足を理由に危険予知訓練(KYT)のような安全活動を行わないと、重大な事故につながりかねません。
事故の発生は企業の信頼を失墜させるだけでなく、社員の命にも関わります。
研修で安全教育を徹底し、リスクを低減していきましょう。
建設業の研修内容の種類と対象別カリキュラム
効果的な人材育成を実現するには、社員の階層や役職に応じて最適な研修を提供する必要があります。
画一的な内容ではなく、それぞれの立場で求められるスキルや知識を体系的に学べるカリキュラムを設計しましょう。
研修カリキュラム例
- 新入社員向け基礎研修
- 中堅技術者向けスキルアップ研修
- 管理職向けマネジメント研修
- 全社員共通:安全衛生・コンプライアンス教育
各カリキュラムを1つずつ解説します。
新入社員向け基礎研修(ビジネスマナー・施工管理)
新入社員は社会人としての基礎と建設業界で働く上での土台を築く研修が必要です。
| 研修項目 | 主な研修内容と目的 |
|---|---|
| ビジネスマナー | 挨拶・言葉遣い・報連相などの社会人としてのマナーを習得する |
| 建設業の基礎知識 | 業界の全体像・基本的な専門用語などを学び、全体像を把握する |
| 安全衛生教育 | 労働災害事例・危険予知活動などの基本を学ぶ |
| 施工管理の基礎 | 4大管理の初歩的な考え方を理解する |
現場での業務をスムーズに開始するには、ビジネスマナーから専門知識の入り口までを網羅した内容が求められます。
これらの基礎研修を通じて、新入社員は建設技術者として成長していきます。
参考記事:建設業の新入社員読本を活用した新入社員研修の進め方
中堅技術者向けスキルアップ研修(DX・資格取得)
企業の技術力の中核を担う中堅技術者には、専門性を深めて次世代のリーダーとして活躍するためのスキルアップ研修が効果的です。
日々の業務に加えて新たな知識や技術を学ぶ機会を提供し、成長を後押しします。
| 研修カテゴリ | 主な研修内容 |
|---|---|
| DX関連技術 | BIM/CIM・ドローンなどの操作・活用方法の学習 |
| 高度な専門技術 | 積算・測量・原価管理などの専門分野の学習 |
| 資格取得支援 | 1級施工管理技士や建築士など上位資格取得に向けた講座や費用補助 |
| 後輩指導力 | OJT指導者としての心構えや効果的な指導方法を学ぶメンター研修の実施 |
主体的な学びを促す研修は、中堅技術者のモチベーションを高めます。
企業の競争力を直接的に強化するだけでなく、後進の育成にもつながる重要な取り組みです。
管理職向けマネジメント研修(QCD・安全管理)
管理職は個人の技術だけでなく、現場全体を統括しプロジェクトを成功に導くマネジメント能力が求められます。
担当する工事のQCD(品質・コスト・工期)を管理し、利益を確保する視点を養う研修が必要です。
ポイント
また、多くの作業員をまとめる立場として、現場の安全管理に対する最終的な責任を負う意識も高めます。
部下の育成や労働環境の整備など、組織の成果を最大化するための研修を行います。
参考記事:施工管理研修で組織力を底上げする方法|研修制度を運用するコツも解説
全社員共通:安全衛生・コンプライアンス教育
安全衛生とコンプライアンスに関する教育は役職や職種を問わず、全社員が定期的に受けるべき研修です。
建設現場では常に労働災害のリスクが伴うため、安全に対する意識は繰り返し徹底する必要があります。
また、以下の法律や社会規範も遵守する必要があります。
守るべき法律や社会規範
- 建設業法
- 労働基準法
- ハラスメント防止
「知らなかった」では済まされない問題であり、1人の軽率な行動が会社の信頼を大きく損ないます。
全社で共通の認識をもつことが、社員と会社を守ることにつながります。
建設業の研修がもたらす3つのメリット
研修を実施するメリットは以下のとおりです。
建設業の研修がもたらす3つのメリット
- 若手定着率の向上と離職コストの削減
- 生産性・利益率の向上
- 事故・法令違反リスクの低減
それぞれのメリットを1つずつ解説します。
若手定着率の向上と離職コストの削減
スキルアップを実感できる環境は仕事への満足度を高め、結果として会社への定着につながります。
研修による定着率向上の仕組み
- スキル習得による業務不安の解消
- 成長実感によるモチベーションの向上
- 円滑なコミュニケーションの促進
社員が会社に長く定着すると、採用や再教育にかかるコストを削減できます。
育成した人材が長く活躍してくれることは、企業にとって大きな財産です。
生産性・利益率の向上
社員のスキルアップは、組織全体の生産性向上に貢献します。
生産性が向上する理由
- 作業効率の改善と手戻りの減少
- 新技術・新工法への対応力強化
- 品質アップによる顧客満足度の向上
個人の能力が上がることで、チームとしての対応力も強化されます。
生産性の改善は企業の利益率を高め、無駄のない効率的な業務体制を構築できます。
事故・法令違反リスクの低減
研修は労働災害やコンプライアンス違反といった経営リスクを低減できます。
また、定期的な安全教育の徹底は、ヒューマンエラーによる事故の防止にも効果的です。
会社と社員を守るためにも、研修でリスク管理を徹底しましょう。
参考記事:建設業の安全教育ネタ47選|マンネリを解消する事例完全ガイド
効果を最大化する建設業の研修設計5ステップ
研修は設計次第で効果が大きく変わります。
やみくもに進めるのではなく、効果を最大化するためには計画的なアプローチが必要です。
建設業の研修設計5ステップ
- 現場の課題を洗い出してゴール設定する
- カリキュラムを設計する
- 教材を選定する
- 定期的にフィードバックする
- フィードバックを基に研修を改善する
このステップに沿って進めることで、社員にとって魅力的な研修を設計できます。
各ステップを1つずつ見ていきましょう。
①現場の課題を洗い出してゴール設定する
最初に「研修で何を解決したいのか」という現場が抱える課題を具体的に洗い出します。
現場の職長や若手社員へのヒアリング、あるいは匿名アンケートなどを通じて、現状の問題点を明確にしましょう。
ポイント
課題が明確になると、研修で目指すゴールも具体的に設定できます。
ゴールを決める際には「SMARTの法則」というフレームワークが便利です。
| ゴール設定のポイント | 概要 |
|---|---|
| 具体的(Specific) | 誰が何をするのかを明確にする |
| 測定可能(Measurable) | 数値で達成度を測れるようにする |
| 達成可能(Achievable) | 現実的に達成できる目標を設定する |
| 関連性(Relevant) | 会社の経営目標と関連しているか確認する |
| 期限(Time-bound) | いつまでに達成するのか期限を決める |
例えば「若手の離職率を1年で10%改善する」のように、具体的で測定可能なゴールにすることが大切です。
このようなフレームワークを活用してゴールを設定し、関係者全員が共通の目標を目指せるようにしましょう。
②カリキュラムを設計する
続いて、ゴールを達成するためのカリキュラムを設計します。
ただ研修項目を並べるのではなく、どの知識をどの順番で学ぶと社員が効率的に成長できるかを考えることが大切です。
特に、現場でのOJTと座学でのOff-JTとの連携がポイントです。
例えば、座学で学んだ安全知識を翌日の現場ですぐに実践するような流れを組むと、知識が定着しやすくなります。
③教材を選定する
設計したカリキュラムに合わせて、最適な教材を選びます。
教材にはそれぞれ特徴があるため、コストや研修効果を考慮して複数の教材を組み合わせましょう。
| 教材の種類 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| eラーニング | 時間や場所を選ばず学習でき、進捗管理が容易 | 実技の習得には不向きで、受講者の意欲維持に工夫が必要 |
| 集合研修 | 受講者同士の連帯感が生まれやすく、質疑応答を活発に行える | 会場費や講師料などのコストが高く、日程調整が難しい |
| VRシミュレーター | 危険な作業を安全に体験でき、リアルな感覚で学べる | 導入コストが高く、コンテンツの種類が限られる場合がある |
例えば、基礎知識の習得はeラーニングを活用し、専門技術の習得は外部のプロを招いた集合研修を行うといった組み合わせが考えられます。
自社の予算や育成方針に合う教材をお選びください。
参考記事:【必見】建設業がeラーニングを導入すべき3つの理由と具体的メリット
建設業に特化したeラーニング「Construction Boarding」
建設業に特化したeラーニングは、Construction Boardingがおすすめです。
施工管理の基礎から安全管理、DX関連技術まで社員の成長に必要なスキルを包括的にカバーしています。
Construction Boardingの特徴
- 実際の現場映像とわかりやすいイラストで直感的に学習できる
- 理解度テストで知識の定着を確認できる
- 人材開発支援助成金の対象となる場合がある
2週間の無料トライアルで実際の使い勝手を確認できるため、貴社の教材候補として検討してみてください。
④定期的にフィードバックする
研修は実施して終わりではありません。
社員の成長を促して研修の質を高めるためにも、定期的なフィードバックが必要です。
ポイント
研修直後に内容の理解度をアンケートで確認し、1ヶ月後、3ヶ月後に「学んだことを現場でどのくらい実践できているか」をチェックしましょう。
また、アンケートだけでなく指導役の先輩や上司を交えた面談の場を設けると、より深く課題や成長度合いを把握できます。
⑤フィードバックを基に研修を改善する
最後に、フィードバックを基に研修を改善しましょう。
例えば「専門用語が多すぎて理解できなかった」という意見が多い場合、以下のように改善します。
フィードバックを基にした改善例
- 用語解説の時間を設ける
- 研修前に用語集を配布して予習を促す
- 研修後に理解度を確認する小テストを実施する
- 図やイラスト、写真を多用した資料を用意する
このように具体的な対策を立てて、研修内容を改善します。
また「実技の時間が足りなかった」という声があればOJTの時間を増やし、ほかの意見にも対応していきましょう。
建設業の研修にオンラインを活用する方法
オンライン研修は、多忙な現場作業と学習を両立するのに効果的です。
建設業のオンライン研修活用法
- 動画教材とマイクロラーニングの効果
- VR・ARシミュレーション演習
- LMS連携で研修効果を数値化
研修にオンラインを活用する方法を見ていきましょう。
動画教材とマイクロラーニングの効果
動画教材は、いつでもどこでも学習できる点がメリットです。
特に、1本あたり数分程度の短い動画で学ぶ「マイクロラーニング」という手法が注目されています。
ポイント
スマートフォンやタブレットでアプリを活用すると、現場への移動や休憩などの隙間時間を活用して、効率的に知識を習得できます。
業務の負担を増やすことなく、継続的な学習を促すのに効果的です。
VR・ARシミュレーション演習
VR・ARを研修に活用すると、リアルなシミュレーション演習が可能です。
例えば、VRゴーグルを装着することで高所作業や重機操作に伴う危険な環境を体感できます。
また、AR技術を活用すると実際の現場映像にCGの足場や配管を重ねて表示でき、施工手順を容易に確認できます。
文章や写真だけでは伝わりにくい作業には、VR・ARシミュレーション演習の導入を検討してみてください。
LMS連携で研修効果を数値化
LMS(学習管理システム)とは、eラーニングの受講状況やテストの成績などを一元管理できるシステムを指します。
このLMSを導入すると、研修の成果をデータで可視化できて便利です。
| LMSの主な機能 | 研修担当者のメリット |
|---|---|
| 学習履歴の管理 | 誰がどの研修を終えたか、進捗状況をすぐに把握できる |
| テスト・アンケート機能 | 研修の理解度を点数で客観的に評価できる |
| レポート機能 | 部署や個人の成績を分析し、新たな課題を発見できる |
担当者はこれらのデータを基に、研修内容の改善や社員への追加指導などを的確に行えます。
勘や経験だけに頼らない、データに基づいた人材育成を進めましょう。
建設学習サイト「Construction Boarding」で解決できること
建設業向けのeラーニングは、私たちワット・コンサルティングが提供するConstruction Boardingがおすすめです。
建設業に特化した人材サービスのノウハウが詰まっており、現場の実態に即した教育を実現しています。
貴社が抱える若手の離職やDXの遅れ、技術継承といった課題解決をサポートいたします。
Construction Boardingの特徴
- 建設業に特化した実践的な講座内容
- 1つの動画が3分前後と短く、隙間時間を活用可能
- スマホ・タブレット・PCでいつでもどこでも学習可能
- 理解度テストで知識の定着を確認
- 現場のリアルな映像やイラストを活用したわかりやすい解説
OJTだけでは伝えきれない基礎知識の習得や、多能工育成の一環としても活用できます。
2週間の無料トライアルがあるため、講座の内容や使用感などを確認してみてください。
建設業の研修についてよくある質問
最後に、建設業の研修についてよくある質問にお答えします。
建設業の研修は何日がいい?
研修期間に決まった正解はなく、目的や内容によって異なります。
新入社員研修の場合は、ビジネスマナーや基礎知識を学ぶために数週間~1ヶ月程度かけるケースが一般的です。
一方、特定のスキルを学ぶ専門研修の場合は2〜3日で集中的に行うこともあります。
ポイント
重要なのは日数ではなく、研修のゴールを達成するために必要な時間を確保することです。
まずは研修の目的を明確にした上で、必要な期間を考えましょう。
研修内容はどう決めるの?
研修内容は、現場の課題や従業員のニーズを基に決めるのが基本です。
経営層や現場の意見も取り入れながら、会社全体で納得のいく内容を決めましょう。
「効果を最大化する建設業の研修設計5ステップ」で紹介した研修設計のステップを参考に、自社の状況に合う内容をご検討ください。
オンライン研修でも効果は出る?
オンライン研修でも高い効果が期待できます。
オンラインは時間や場所の制約が少なく、反復して学習できる点がメリットです。
基礎知識の習得や安全教育などに向いています。
ポイント
ただし、実技の習得には限界があるため、現場でのOJTと組み合わせることが重要です。
オンラインとOJTを組み合わせ、研修の効果を高めていきましょう。
新入社員と中堅社員を同時に研修できる?
以下のケースでは合同研修も効果的です。
合同研修のテーマ例
- 全社共通のコンプライアンス研修
- 企業の理念浸透を目的とした研修
- ハラスメント防止研修
合同研修を実施する場合は、グループワークでレベルに応じた議論ができるように配慮しましょう。
なお、全社共通のテーマ以外は、新入社員と中堅社員の研修内容は分けて設計します。
社員の知識やスキルに合わせて研修内容を考えることが大切です。
研修効果をどう測定する?
研修効果は以下の指標を組み合わせて測定します。
研修効果の測定方法
- 研修直後の理解度テストやアンケート
- 現場での行動変化(チェックリストなどで評価)
- 資格取得者数やヒヤリハット発生件数の増減
- 研修3ヶ月後の定着率や満足度調査
研修前に設定したゴールがどの程度達成できたかを、これらの指標で定期的に確認します。
測定結果を分析し、研修内容を改善していきましょう。
まとめ
最後にもう一度、研修設計のステップをまとめておきます。
効果を最大化する建設業の研修設計5ステップ
- 現場の課題を洗い出してゴール設定する
- カリキュラムを設計する
- 教材を選定する
- 定期的にフィードバックする
- フィードバックを基に研修を改善する
この記事の内容を参考に、課題解決につながる研修を設計してみてください。
研修制度の整備にはConstruction Boardingのようなeラーニングツールが効果的です。
ポイント
忙しい現場でも隙間時間に学べる短時間設計で、スマートフォンやPCから気軽にアクセスできます。
また、実際の現場映像やわかりやすいイラストで施工管理の基礎から実践までを効率的に学習できるため、若手の早期戦力化と定着率向上に役立ちます。
無料で2週間のトライアルができ、人材開発支援助成金の対象となる場合があるため、低コストで質の高い研修を実施できます。
まずは無料トライアルで、実際の使い勝手を確かめてみてください。