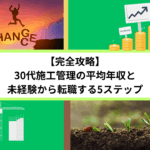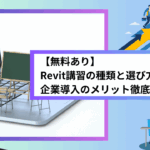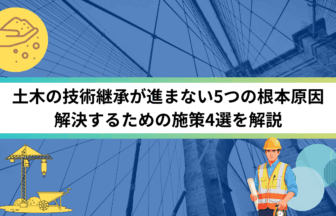「施工管理DXって何?」
「うちの会社は何から始めればいいの?」
こういった疑問がある建設会社の管理職や、経営者の方に応える記事です。
この記事でわかること
- そもそも「施工管理DX」とは
- 施工管理DXを導入する5つのメリット
- 施工管理DXを導入する5ステップ
- 施工管理や建設DXの成功事例
働き方改革の推進や、施工管理の人材不足に対応するためにもDX化が有効です。
工数や残業時間を削減できて、コストカットにも繋がります。
IT化に興味を持つ若手人材も採用しやすくなるでしょう。
この記事では、施工管理DXに興味を持つ方に向けて、基本から具体的な導入ステップまで網羅的に解説します。
DX化を進めることで経営改善していきたい方は、最後まで読んでみてください。
この記事の監修者
施工管理の技術者派遣と施工管理向けの研修を行う会社です。
- 労働者派遣事業許可番号 派13-304593
- 有料職業紹介事業許可番号 13- ユ-304267
- 特定建設業 東京都知事許可 (特-1) 第150734号
目次
施工管理DXとは?
「施工管理DX」とは、建設業界が紙資料や手書きの指示など従来のアナログ手段から、デジタル技術を取り入れて業務全体を変革する概念のことです。
DXとは
「デジタルトランスフォーメーション」のことで、デジタル技術を活用してビジネスや社会の仕組みを変革し、効率的・革新的な形にするという意味です。
施工管理におけるDXは、現場の進捗や安全管理をリアルタイムで共有し、効率と品質を同時に高める点が特徴です。例えば図面や指示書をクラウドで共有すると、ミスや確認作業が減り、工程の遅延リスクが低減します。
以下は施工管理のアナログ作業と、デジタル化の違いをまとめた表です。
| 従来のやり方(紙ベース) | デジタル技術を活用した場合 |
|---|---|
| 手書きによる図面修正や日報作成 | タブレットで図面更新や写真添付が可能 |
| 書類や台帳を事務所に保管 | クラウド上でプロジェクト管理 |
| 朝礼や打ち合わせで紙資料を配布 | オンライン会議やアプリで資料共有 |
| 現場巡回中に撮影した写真を後日整理 | その場で撮影し、即座に共有や振り分け |
従来よりも業務効率化できるため、施工管理DXが注目されています。
建設業界が抱える課題と施工管理DXの需要

建設業界が抱える課題と、それに伴う施工管理DXの需要について解説していきます。国も建設業界のDX化を推進しているため、時代の流れに乗っていきましょう。
建設業界が直面する主な課題
建設分野には、人材の確保から生産性の向上まで多岐にわたる課題があります。現場の負担を軽減しないと、工期の遅延や品質の維持が難しくなるかもしれません。
特に課題となっているのは以下の要素です。
建設業界では2025年に47〜93万人の人材不足が発生すると試算されており、DX化による業務効率化が急務です。
施工管理DXは、これらの課題を解決する手段として注目を集めています。
国や行政の後押しする施工管理DX
建設業を取り巻く課題に対して、国や行政は施策を打ち出しています。特に国土交通省の「i-Construction」は、BIM/CIMやICT機器の導入を後押ししている点が特徴です。
出典:国土交通省|i-Construction推進コンソーシアム 3次元データ流通・利活用WG報告会
例えばBIMを用いた三次元モデルで計画を進めれば、設計段階から衝突箇所を検知し、施工ミスを防ぎやすくなります。
ポイント
デジタル庁によるアナログ規制撤廃も重要です。行政手続きのオンライン化が進行し、対面や紙中心の手続きを減らそうとする動きが加速しています。
特に公共工事では、受発注や申請手続きをシステム化する必要性があるでしょう。国も建設業や施工管理のDX化を推進しているため、この波に乗ってDX化を検討してみてください。
施工管理DXのメリット5選

施工管理DXを導入すると、建設業界で生じがちな負担を減らし、生産性や安全性を高められます。ここからは、施工管理DXで特に注目度が高い5つのメリットを紹介します。
施工管理DXのメリット
- 生産性の向上とコスト削減
- 人材不足の問題を解決できる
- 施工管理の採用を強化できる
- 安全管理・品質管理を強化できる
- ベテラン施工管理のスキルを継承できる
事例を交えながら具体的に見ていきましょう。
生産性の向上とコスト削減
施工管理DXでは、リアルタイム共有や自動化により業務が効率化し、全体の生産性が高まります。具体的には以下のような取り組みがあります。
施工管理DXによる生産性向上の例
- 工程管理や写真整理を自動化して、時間短縮・ミス削減
- ICT建機やドローンなどで現場作業を効率化
- タブレットでの記録・報告により紙資料を削減
- オンライン打ち合わせや電子黒板で移動時間を最小化
上記のような施策を進めると、残業が減少して人件費を抑えやすくなります。さらに、必要な書類をクラウド上に集約するため、スペースや印刷費も圧縮できるでしょう。
結果として、限られたリソースを有効活用しながら、利益率を高める可能性があります。
人材不足の問題を解決できる
施工管理DXを導入してクラウドベースの運用を取り入れると、少人数でも複数の現場をチェックできます。現場を遠隔から確認できるため、担当者が一ヶ所に滞在しながら複数の現場管理が可能です。
さらに
タブレットやセンサーを使った進捗管理や写真撮影も自動化できるため、一人が抱える業務量が減るでしょう。
施工管理DXは、従来よりも少ない人数で同じ工数をまかなえます。
施工管理の採用を強化できる
施工管理人材を募集している企業がDX化を進めると、IT化や業務効率の高さをアピールできて、採用面で有利になることがあります。
例
クラウドで書類作業を減らし、長時間労働を回避しやすい環境を作ると、候補者は「働きやすい」「先進的な会社」という印象を持つでしょう。
他社と比べて魅力的な労働環境を用意できて、優秀な人材を採用できる可能性が高まります。特にITリテラシーが高い若手は、デジタル技術が整備された職場を好む傾向があります。施工管理の採用を強化するうえでも、DX化を進めていきましょう。
安全管理・品質管理を強化できる
建設現場では、事故防止と品質の確保が優先事項です。施工管理DXによって、危険を早期に見つけたり、設計精度を高めたりしやすくなります。
DX化により、以下のような対策が可能です。
DX化による安全管理・品質管理の強化
- AIやセンサーによるリスク検知や不具合の早期発見
- BIM/CIMによる干渉チェックで施工ミスを低減
- ドローンや遠隔カメラによる定期巡回で異常箇所を素早く認識
結果として事故のリスクが減り、品質面のトラブル発生率も下がります。
ベテラン施工管理のスキルを継承できる
ベテランの施工管理者は、計画立案やトラブル対応で培ったノウハウを多く持っています。しかし、口頭だけでは若手の施工管理者にノウハウを伝えきれないでしょう。
施工管理DXの導入でベテランの技術をデジタル化し、組織全体で共有すると、人材育成に役立ちます。
具体的には、以下のような対策が可能です。
こうした仕組みを整備すれば、世代交代を進めながら、チーム全体のスキルレベルを底上げできます。施工管理DXは、人的資源を次に引き継ぐツールとしても有効です。
施工管理DXを導入するときの課題
施工管理DXを導入する場合、以下のような課題があるでしょう。
施工管理DXを導入するときの課題
- 導入コストとランニングコストがかかる
- 施工管理者のフォローアップ体制が必要
- 部分的な導入だけでは効果が限定的
課題に対する対処法も記事の中で解説しますが、まずはどんな課題があるのか把握した上で、DX導入を検討してみてください。
導入コストとランニングコストがかかる
新しいDXツールを導入するときは、初期投資だけでなく維持費も必要です。ソフトウェアやクラウドサービスの月額費用に加え、ハードウェアのアップデートや操作研修の費用が発生することもあります。
以下の表は代表的な施工管理DXツールの費用相場です。
上記のように幅広い選択肢がありますが、安価に導入できるツールも存在します。予算に合わせて無理のない製品やサービスを検討すれば、費用対効果を高められます。
施工管理DXに関する補助金を活用する
DXツールの導入コストの負担が大きい場合は、補助金を活用しましょう。以下の表は、施工管理DXの導入に活用しやすい国の補助金の例です。条件や金額は年度ごとに変更される場合があるので、申請前に最新の公募要領を確認してください。
施工管理者のフォローアップ体制が必要
デジタルツールに馴染みがないベテラン社員は、新しいシステムを使う際に抵抗感を持つかもしれません。若手との習熟度の差が拡大すると、現場で情報共有が進まず混乱を招く懸念があります。
ポイント
教育体制を整えたうえで、導入直後は厚めにサポートするとスムーズです。例えば、クラウド上で図面を更新するとき、初日はサポート担当者が横について操作を一緒に確認すると理解が深まりやすいです。
また、操作マニュアルを動画や図解入りで作成すると、研修後の復習や後から参加したスタッフへの説明が楽になります。現場全体がDXを受け入れるためには、フォローアップの仕組みが欠かせません。
部分的な導入だけでは効果が限定的
一部の現場のみがデジタル化しても、全体の業務効率や生産性はあまり変わらない場合があります。資料作成や工程管理は社内で連携する範囲が広いため、一部で新システムを導入しても、前後のやりとりで従来の紙や口頭に頼る流れが残りがちです。
ポイント
根本的な業務改革を目指すなら、経営層のコミットが必要です。各部署を横断する形でプロジェクトチームを立ち上げ、IT担当者や現場リーダー、管理部門などと方針を共有すると一体感が高まります。
全社的に取り組めばデジタル化のメリットを隅々まで行き渡らせやすく、属人的な業務や二重入力を減らせる可能性が高まります。
施工管理DXに使われる主な技術・ツール

続いて、施工管理DXでよく使われる技術やツールを紹介していきます。
施工管理DXに使われる主な技術・ツール
- AI
- IoT
- クラウド
- VR/AR
- ドローン
- BIM/CIM
複数の技術・ツールを組み合わせて導入すると、効果が高まります。施工管理DXに使われる技術やツールが、どのように役立つか解説していきます。
AI
人工知能(AI)は、大量のデータを解析してパターンや法則を見つけ出し、リスクや作業効率などを見通せます。施工管理の場面では、画像認識による検査作業の省力化や、センサーから集まる膨大な数値をもとに、設備トラブルを予測する技術開発が進んでいます。
出典:国土交通省|AIを活用した建設生産システム の高度化に関する研究
AIが提供できる機能とメリットは以下のとおりです。
AIをうまく活用すると、作業や検査が単純化され、従来は人が長時間かけて対応していた処理を短縮できます。DXの推進に向けて、AI技術は今後も急速に進化し、建設業界の働き方を変えていくでしょう。
IoT
IoT(モノのインターネット)は、センサーや機器をネットワークに接続し、稼働状況や環境データを収集・共有する技術です。建設現場では、重機や作業員の装着センサーから得る情報を活用し、リアルタイムで工程を監視する事例が増えています。
以下はIoTで実現できることとメリットです。
IoTを導入すれば、従来は経験や感覚で行っていた現場管理を、数値ベースで実施できます。遠隔地でもリアルタイムに状況を把握しやすいため、管理者の移動コストを抑えられるでしょう。
クラウド
クラウドは、インターネット上のサーバーやストレージを利用して、データやアプリケーションを管理する仕組みです。建設業界では、図面や写真、書類などをクラウドに集約して、オフィスや現場、協力会社などが同時に情報を閲覧できます。
施工管理アプリを提供する企業が増えており、導入しやすくなっています。具体的な活用事例は以下のとおりです。
現場の離れたスタッフ同士が円滑に連携するための土台として、クラウドツールは欠かせません。
VR/AR
VR(仮想現実)は3D空間を再現したバーチャル空間での視覚体験、AR(拡張現実)は実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術のことです。
例
施工計画でVRを利用すれば、完成イメージの建物内部を歩き回るように確認でき、平面図ではわかりづらい高さや奥行きを立体的に把握できます。また、ARゴーグルを装着すれば、現場にデジタル図面を合成表示し、配管や配線の位置をその場で確認できます。
VR/ARの主要な活用例とメリットを見てみましょう。
VR/ARを活用すると、紙ベースでは把握しにくい空間情報を体感的に理解できます。図面のミスを前もって見つけられるため、生産性の向上を実現できるでしょう。
ドローン
ドローンは遠隔操作で空撮や測量、点検が可能です。障害物が多い場所や高所、広大な敷地の工事でも、短時間で詳細な情報を取得できます。
特に地形測量では、人手では数日かかる作業を数時間で終えられることがあり、工期短縮と労力削減に直結します。
ドローン導入による活用例とメリットは以下のとおりです。
ドローンを使えば、手作業に比べて作業員の負担を減らしつつ安全性を高められます。さらに、撮影したデータをクラウドやAIと組み合わせると、現場の変化を定量的に追える点もメリットです。
BIM/CIM
BIMとCIMは建物や土木構造物を3Dモデル化して、設計・施工・維持管理の情報を一元管理する技術です。
BIMとCIMの主な違い
- BIM(Building Information Modeling):建築向け
- CIM(Construction Information Modeling):土木向け
紙図面だと把握しにくい衝突や仕様の食い違いを事前に発見できるため、手戻りを減らし、品質向上や工期短縮に繋がります。
BIM/CIMでできることとメリットは以下のとおりです。
BIM/CIMを導入すると、設計者・施工者・発注者・維持管理者が同じモデルを見ながら意見を出し合えるため、コミュニケーションロスを減らせます。公共工事でも導入が進み、今後ますます建設業界の標準ツールになり得る技術でしょう。
施工管理DXを導入する5ステップ

それでは、実際に施工管理DXを導入する手順を解説していきます。
施工管理DXを導入する5ステップ
- 現場の課題をヒアリング
- 導入コストとROIを計算する
- 施工管理者のニーズが高い部分から導入する
- 施工管理者のサポート体制を作る
- PDCAサイクルを回す
施工管理DXを円滑に進めるには、企業全体で合意形成を図りながら少しずつ段階を踏むのがおすすめです。1ステップずつ解説するので、導入の参考にしてみてください。
①現場の課題をヒアリング
まずは施工管理者に現場の具体的な課題を聞き取り、アナログ作業が多い工程やコスト負担が大きいポイントを洗い出しましょう。
例
紙の日報や重複入力に時間を取られているなら、その部分にツールを導入すると改善につながる可能性があります。
作業者や施工管理者にインタビューしたり、稼働時間の記録を細かく集めたりするのがおすすめです。全員が抱えている悩みを整理すると、優先度の高い問題が自然に浮かび上がります。
まずは「どこに手を付ければよいか」を明らかにし、DX導入の方向性を具体的に固めましょう。
②導入コストとROIを計算する
必要な投資を回収できるかを考えるために、DXツールの導入コストとROI(Return on Investment)を計算してください。
ROIとは
「投資収益率」のことで、投資した資金に対してどれだけの利益を得られたかを示す指標です。
ソフトウェアのライセンス費やハードウェア費用に加え、メンテナンス費や研修費なども見積もると失敗が減ります。ROIの計算式は以下のとおりです。
ROIの計算式
ROI(%)=(利益ー投資額)÷投資額×100
例えば、ツールの導入に100万円かかり、年間で150万円のコスト削減が見込める場合、ROIは以下のように計算します。
ROIの計算式
(利益150万円ー投資額100万円)÷投資額100万円×100=ROI:50%
つまり、投資額に対して年間で50%の利益が出る計算です。最初に投資を回収できる目安を設定すれば、周りの承認も得やすいでしょう。
③施工管理者のニーズが高い部分から導入する
最初からフルパッケージでDXを導入するよりも、現場の施工管理者が強く求めている領域で小さく始めるのが効果的です。現場に抵抗感を与えずにメリットを体感してもらいやすく、次の施策にも興味を示してくれるでしょう。
ポイント
途中で不具合が見つかったらすぐに修正し、現場の反応を確認しながら徐々に範囲を拡大していくのがおすすめです。
段階的に成功体験を重ねることで、他の現場からも「導入してみたい」という声が出始め、最終的には社内のDX化が円滑に進みやすいです。
④施工管理者のサポート体制を作る
ITに苦手意識を持つベテラン社員がいたり、新システムが急に増えたりすると混乱が起きる恐れがあります。そのため、以下のようにサポート体制を作っていきましょう。
サポート体制を整えると、導入直後の疑問や操作ミスを解決できます。研修やマニュアルが充実していれば、個々の習熟度の差が埋まり、現場全体で新システムを活用しやすくなります。
⑤PDCAサイクルを回す
ツールなど導入した後も継続的に改善するため、PDCAサイクルを回していきましょう。
まずはDX化の成果を測るKPI(指標)を決め、定期的に振り返るようにしてください。KPI設定例は以下のとおりです。
KPIの設定例
- 月間残業時間の削減率
- 現場写真の提出遅れ件数
- 工期短縮率
- ミスやクレームの発生数
以下はDX化のPDCAサイクルの具体例です。
PDCAサイクルを途切れさせずに回し続ければ、施工管理DXの効果が可視化され、社内のモチベーションも上がります。改善を重ねることで、DXの恩恵を最大化していきましょう。
施工管理や建設DXの成功事例
施工管理DXの成功事例も紹介していきます。実際に効果が出ているため、貴社でもDX化を検討してみてください。
BIM/CIMの導入事例
渋谷駅西口付近で進められている国道246号の地下歩道整備事業における事例です。狭い施工空間でのパーシャルプレキャスト(PPCa)ボックスカルバート工法を採用し、BIM/CIMとVR、4Dシミュレーションを組み合わせています。
具体的な対策
既設構造物や地下仮設物を3Dモデル化し、工程ごとの時間軸を可視化することで、部材の据付手順や安全対策を精密に検討しました。
AR技術で現場や関係者へ完成イメージを伝え、360°カメラで定点観測した写真を共有するなど、円滑な工事調整にもつなげています。結果として、施工リスクの事前検出や工期短縮に貢献し、新工法によるプレキャスト部材の据付日数が40%削減されています。
参考:国土交通省関東地方整備局|BIM/CIM活用工事としての取り組み(国道246号 渋谷駅周辺整備事業)
ドローンの活用事例
水管理・国土保全局では、ドローンの空撮を活用して周囲の三次元点群データを取得し、河川やインフラの巡視・点検を効率化しています。
具体的な内容
VTOL(垂直離着陸)機を用いて25kmの管理区間を約25分で巡視し、従来の4時間から大幅な時間短縮を達成しました。既設の通信網(K-PASS)を使い、安定した遠隔制御や映像伝送ができるのも特長です。
さらに、着陸後2時間で3次元モデルを出力可能で、災害発生時の迅速な被害把握に役立てています。砂防施設の点検など山間部の危険箇所調査にもUAVを導入して安全性を高める取り組みを拡大中です。
ドローン撮影画像とVR技術を組み合わせ、河川水位予測を三次元で表示する研究開発も進行しており、災害時の情報共有と防災対策が期待されています。
参考:国土交通省 水管理・国土保全局DX|現場で活用・実証されているDX事例について紹介します
マシンガイダンス適用による業務効率化
沖縄県の極東建設株式会社は、水中バックホウにマシンガイダンス技術を導入し、透視度が低い環境でも安全かつ高精度の施工を実現しました。
具体的な内容
音響プロファイルソナーを用いて海底状況を約1分で3D表示し、従来5時間かかった情報更新を大幅に短縮しています。
さらに、磁歪式ストロークセンサでバケット姿勢を即時把握し、マウンド形状を立体的に確認することで、潜水士の目視に依存しない作業を可能にしました。河川やダムなどさまざまな水域でも施工できるため、全国的な展開が期待されています。
施工管理DXでよくある質問
最後に、施工管理DXについてよくある質問に答えていきます。
大企業と中小企業で導入に差はある?
大企業は資金や専任チームを確保しやすく、最新のBIMソフトや多数のドローン導入など大規模なDX施策を進めやすいかもしれません。一方、中小企業は限られた予算と人員で、導入範囲を見極めつつ段階的に進めるケースがあります。
例
まずは施工管理アプリや写真整理ツールだけを導入し、効果を実感してから他の分野にもDXを拡張するなど、段階的に進めていくのも良いでしょう。
高額なハードウェア導入が難しい場合は、業務委託やレンタルも検討してみてください。さらに、補助金を利用できないか調べてみるのもおすすめです。
DXの導入目的を明確にすれば、中小企業でも十分に成果を出せます。状況に合わせたツールを検討してみてください。
既存のソフトと連携できる?
すでに施工に関連するソフトを使っている場合、新ツールと連携すると過去のデータを無駄にせずに済みます。例えば、API(アプリケーション同士のデータ連携手段)やCSV形式のデータ取り込みを活用し、重複入力を避ける方法があります。
ポイント
やり方がわからない場合は、外部のITコンサルやシステムベンダー、あるいは社内に詳しい担当者がいないか確認してみてください。専門家に相談すれば、ソフト同士の仕様を確認できるでしょう。
社内稟議を通すコツは?
施工管理DXの導入は設備投資や研修費など、まとまった予算を要するケースが多いです。社内稟議を通すには、投資額に見合う効果やリスク回避の根拠を示す必要があるでしょう。
稟議を通すためのステップは以下のとおりです。
現場と経営層が同じ目標に向かうために、必要な資料やシミュレーションを入念に準備しましょう。
情報のセキュリティ面は大丈夫?
堅牢なクラウドサービスでは、データ暗号化や多要素認証が整っており、自社サーバーよりセキュリティ水準が高い場合もあります。
例
施工写真や図面を暗号化して送受信する仕組みがあれば、外部からの不正アクセスリスクを抑えられます。
導入時にサービス提供企業のセキュリティ対策をよく確認し、アクセス権限の管理や情報取り扱いルールを社内で徹底しましょう。定期的にパスワードを変更し、職員の教育を行えば、情報保護と利便性を両立できます。
まとめ|施工管理者向けにDXを導入していきましょう
施工管理DXには以下のようなメリットがあります。
施工管理DXのメリット
- 生産性の向上とコスト削減
- 人材不足の問題を解決できる
- 施工管理の採用を強化できる
- 安全管理・品質管理を強化できる
- ベテラン施工管理のスキルを継承できる
実際に導入を進める際は、以下のステップで進めていきましょう。
施工管理DXを導入する5ステップ
- 現場の課題をヒアリング
- 導入コストとROIを計算する
- 施工管理者のニーズが高い部分から導入する
- 施工管理者のサポート体制を作る
- PDCAサイクルを回す
貴社の業務効率化やコストカット、さらには人材獲得の参考になれば幸いです。