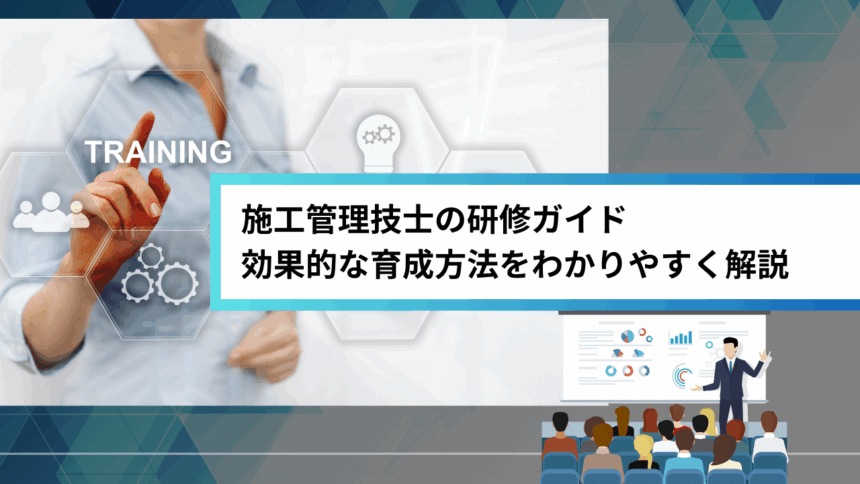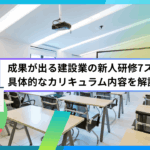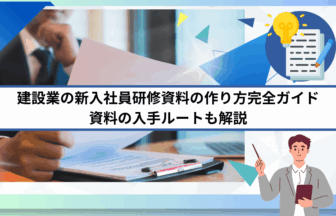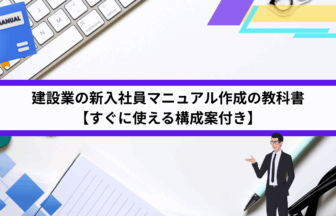「施工管理技士の研修をどうやって進めよう…」
「社内研修を始めたいけど、何から手をつければいいかわからない…」
「若手の資格取得率を上げて、会社の技術力を底上げしたい」
このような悩みを抱える建設会社の経営者様や研修担当者様に役立つ記事です。
この記事でわかること
- 施工管理技士研修を内製化すべき4つの理由
- 【一次・二次検定対策】合格に導く社内研修プログラム
- 効果的な社内研修を設計するための5つのステップ
施工管理技士の研修は内製化することで、コストを抑えつつ企業の技術力を効果的に高められます。
OJTと連動させた実践的な教育が可能になり、資格取得率の向上にもつながります。
「でも、研修制度を一から作るのは大変そうだし、時間もコストもかかる…」と思いますよね?
この記事を読めば、施工管理技士の研修を内製化するための具体的なステップがわかり、効果的な育成プランを設計できるようになります。
記事の内容を参考にして、貴社に最適な研修制度を構築していきましょう。
研修の内製化とeラーニングの併用がおすすめ
研修の内製化と合わせてeラーニングを活用すると学習効率が高まり、合格しやすくなります。
私たちワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」は、いつでもどこでも学べるeラーニングです。
現場が忙しくても、スマートフォン1つで基礎知識の習得や資格試験対策を進められます。

2週間の無料トライアルもあるので、試しながら検討してみてください。
目次
施工管理技士研修を内製化した方が良い4つの理由
外部研修の活用も効果的な手段ですが、施工管理技士の研修を内製化すると多くのメリットがあります。
施工管理技士研修を内製化した方が良い4つの理由
- 全社の技術力・知識レベルを標準化できるから
- 資格取得率の向上が企業の経営事項審査評点につながるため
- OJTと連動させた自社流の実践的な教育が可能になるから
- 外部研修のコストを削減し計画的な人材投資ができるため
自社の状況に合わせて研修を最適化できるため、組織全体の成長につながりやすいです。
それぞれの理由を1つずつ解説します。
全社の技術力・知識レベルを標準化できるから
現場や担当者ごとに業務の進め方が異なると、施工品質にばらつきが生じる原因になります。
社内で統一した基準を設けることで、どの現場でも一定の品質を保ちやすくなります。
研修で標準化できる項目の例
- 安全管理のチェック基準
- 顧客への定期報告の形式
- 使用する施工管理アプリの操作方法
- 各工程で作成する書類のフォーマット
こうした基準を明確にする研修を設けることで、会社全体の技術力を底上げできます。
結果として、顧客からの信頼性向上にもつながります。
資格取得率の向上が企業の経営事項審査評点につながるため
資格取得率が向上すると、企業の技術力を示す経営事項審査の評点向上に直結します。
評点が高まると受注できる工事の規模や種類が広がり、企業の成長につながります。
企業の成長と受注機会の拡大を目指すうえで、資格取得を支援する内製化研修は有効な投資です。
OJTと連動させた自社流の実践的な教育が可能になるから
内製化研修では、日常業務であるOJTと連携させた自社ならではの教育プログラムを組めます。
例えば、OJTと研修を以下のように連動させられます。
| 研修内容 | OJTでの実践 |
|---|---|
| 鉄筋の配筋検査に関する講義 | 研修翌日に現場で先輩技術者と一緒に配筋検査を実施する |
| 新しい測量機器の操作研修 | 研修で学んだ機器を用いて実際の測量業務を担当する |
机上での学びをすぐに現場で実践するサイクルを作ることで、知識の定着が早まります。
結果として、即戦力となる人材を育成しやすくなります。
参考記事:建設業OJTを始める前にやるべき準備と8つのテクニックを完全解説
外部研修のコストを削減し計画的な人材投資ができるため
外部研修は1人あたりの受講料が高額になりがちですが、社内研修は一度プログラムを構築すると、費用を抑えつつ多くの社員を教育できる点がメリットです。
ポイント
例えば、毎年10人の新入社員を外部研修へ派遣すると、多額の費用がかかります。
一方の社内研修は初年度に教材開発費がかかりますが、次年度以降は講師役社員の人件費のみで済む場合があります。
研修コストを抑えるためにも、施工管理技士の研修は内製化を検討してみてください。
【一次検定対策】知識を定着させる社内研修プログラム
施工管理技士の一次検定は出題範囲が広く、効率的に学習できるかが合格を左右します。
ここでは、受講者の知識を確実に定着させるための社内研修プログラムについて解説します。
一次検定対策の社内研修プログラム
- 過去10年の出題傾向を分析し頻出分野に絞った講義を行う
- 自社の施工写真や図面を使い専門用語を具体的に解説する
- 単元ごとの理解度を確認するオンライン小テストを実施する
- 受講者同士で教え合うグループ学習の時間を取り入れる
プログラムをうまく組み合わせると受講者の学習意欲が高まり、合格率の向上につながります。
それぞれの社内研修プログラムの内容を見ていきましょう。
過去10年の出題傾向を分析し頻出分野に絞った講義を行う
試験範囲は膨大ですが、毎年くりかえし出題される分野や法改正に関連する項目には一定の傾向があります。
そのため、過去10年の出題傾向を分析し頻出分野に絞った講義を行うことで、効率よく合格率を高めることが可能です。
こうした得点源となる分野に学習時間を集中させ、効率的に合格者を増やしていきましょう。
自社の施工写真や図面を使い専門用語を具体的に解説する
テキストだけの学習ではイメージしにくい内容も、見慣れた現場の写真と結びつけることで記憶に定着しやすくなります。
以下のように、専門用語と現場の写真をセットで解説すると効果的です。
| 専門用語 | 解説に使う自社資料の例 |
|---|---|
| 型枠支保工(かたわくしほうこう) | 自社が施工したビルのコンクリート打設前の現場写真 |
| 配筋(はいきん) | 基礎工事で撮影した鉄筋が組まれている状態の図面と写真 |
受講者は日々の業務と学習内容を関連づけられるため、学習効果が高まります。
単元ごとの理解度を確認するオンライン小テストを実施する
講義を聞くだけの受け身の学習では「わかったつもり」になってしまう場合があります。
テスト形式でアウトプットの機会を設けることで、理解が不十分な点を早期に発見できます。
オンライン小テストの利点
- 隙間時間を活用してテストを受験できる
- 自動採点機能で即座に結果がわかる
- 間違えた問題の解説をすぐに確認できる
- 管理者が個人の学習進捗を把握しやすい
受講者は自分の苦手分野を客観的に把握し、効率的な復習に役立てられます。
また、管理者側は全体の進捗をデータで管理しやすくなる点がメリットです。
受講者同士で教え合うグループ学習の時間を取り入れる
受講者同士が互いに教え合うグループ学習は、知識の理解を深めるうえで効果的な方法です。
ポイント
他人にわかりやすく説明するには、内容を正しく理解している必要があります。
人に教えるという行為を通じて、知識がより強固に記憶されます。
例えば、単元ごとに得意な受講者が講師役となり、ほかのメンバーに解説する時間を設けましょう。
また、難易度の高い問題についてグループで討議し、解答を導き出す演習もおすすめです。
【二次検定対策】実践力を養う社内研修プログラム
ここでは、二次検定突破を目指すための社内研修プログラムについて解説します。
二次検定対策の社内研修プログラム
- 「経験記述」の作成ワークショップを開催する
- 過去の優良工事事例を基にしたケーススタディを行う
- 先輩技術者が講師となりマンツーマンで記述内容を添削する
- 完成した記述文の模擬発表会とフィードバックを実施する
二次検定は筆記試験の知識だけでなく、現場での応用力が問われます。
特に、自身の工事経験を記述する「経験記述」は合否を左右する重要な項目です。
1つずつ見ていきましょう。
「経験記述」の作成ワークショップを開催する
多くの受講者が「何を書けばいいのかわからない」「文章の構成が難しい」といった悩みを抱えています。
そのため、ワークショップ形式で記述の基本構成や評価されるポイントを体系的に学ぶ機会を設けましょう。
ワークショップで学ぶ内容例
- 経験記述で問われるテーマの解説(品質管理、安全管理など)
- 評価されやすい文章の構成方法
- 自身の担当工事経験の棚卸しと整理
- 避けるべきNG表現や記述内容の共有
担当した工事経験を整理し、記述の骨子を作成する良い機会となります。
このステップを踏むことで、その後の具体的な記述作成がスムーズに進むでしょう。
過去の優良工事事例を基にしたケーススタディを行う
自身の経験だけでは記述内容に限界がある場合でも、他者の成功事例から学ぶことで記述に幅や深みが出ます。
例えば「工期短縮を実現した品質管理の工夫」や「無事故を達成した安全管理の取り組み」など、具体的なテーマで表彰された工事の記録を読み解きます。
そのうえで担当者がどのような課題に対し、どう対策したのかをグループで討議すると良いでしょう。
優れた事例に触れることで、自身の経験をより客観的かつ具体的に記述するためのヒントを得られます。
先輩技術者が講師となりマンツーマンで記述内容を添削する
受講者ごとに担当した工事内容や立場が異なるため、画一的な指導では限界があります。
個別の状況に合わせた具体的なアドバイスが、内容の質を大きく向上させます。
| 添削の観点 | 具体的なアドバイス例 |
|---|---|
| 具体性 | 「コストを削減した」→「〇〇の導入で資材費を5%削減した」 |
| 技術的根拠 | なぜその対策が有効だったのか、技術的な裏付けは明確か |
| 独創性 | ほかの工事でも応用できるような独自の工夫点が示されているか |
受講者それぞれの経験に寄り添った指導を行うことで、より説得力のある経験記述が完成します。
また、先輩から後輩への技術継承においても有益な時間となるでしょう。
完成した記述文の模擬発表会とフィードバックを実施する
研修の総仕上げとして、完成した経験記述の模擬発表会とフィードバックの場を設けましょう。
記述内容を第三者に口頭で説明することで、論理的な矛盾やわかりにくい点に気づきやすくなるからです。
ポイント
また、ほかの受講者の発表を聞くことで、新たな視点や表現方法を学べます。
発表会は持ち時間5分程度で経験記述の要点を発表するようにしましょう。
その後、講師やほかの受講者から質疑応答の時間を取り、多角的なフィードバックを行います。
本番の試験を想定した環境で発表を経験することで自信が深まり、記述を磨き上げる良い機会となります。
効果的な社内研修を設計するための5つのステップ
施工管理技士の資格取得という明確なゴールに向けて、着実に成果を出すためのプロセスは5つのステップに分けられます。
ここでは、効果的な社内研修を設計するための具体的な手順を解説します。
効果的な社内研修を設計するための5つのステップ
- 目標の合格人数を決める
- 受講対象者を選定し学習スケジュールを策定する
- 社内のエース級技術者を講師として任命・育成する
- 業務時間内に研修時間を確保し学習に集中できる環境を作る
- 資格取得者への報奨金などモチベーション維持の仕組みを導入する
こうしたステップを順番に実行することで、参加者のモチベーションを高めながらプログラムを運営できます。
社内研修を内製化したい方は、参考にしてみてください。
参考記事:【離職率の改善】建設業の研修内容の設計手順をわかりやすく解説
STEP1|目標の合格人数を決める
目標を数値化することで、研修の規模や必要な予算、期間などを具体的に計画しやすくなります。
例えば「今年度は1級建築施工管理技士の合格者を5名輩出する」といった明確な目標を立てましょう。
最初に設定した目標が研修全体の方向性を決め、後工程である効果測定を行う際に重要な基準となります。
STEP2|受講対象者を選定し学習スケジュールを策定する
目標人数を決めたあとは受講対象者を選定し、具体的な学習スケジュールを策定します。
対象者の現在のスキルレベルや経験年数を考慮して選ぶと、研修効果が高まります。
スケジュールは、試験日から逆算して長期的な視点で計画を立てることが望ましいです。
| 時期 | 研修内容 | 到達目標 |
|---|---|---|
| 4月~6月 | 基礎知識の講義(週1回) | 各科目の基本的な概念を理解する |
| 7月~8月 | 過去問題の演習(週2回) | 苦手分野を克服し、解答スピードを上げる |
| 9月 | 模擬試験と直前対策 | 試験形式に慣れ、本番での得点力を最大化する |
長期的な視点で余裕のある計画を立てることで、受講者は業務とのバランスを取りながら学習を進められます。
STEP3|社内のエース級技術者を講師として任命・育成する
経験豊富な技術者は、自社の実情に即した具体的な事例を交えて指導できます。
例えば、過去に自社で手掛けた工事の図面を教材にしたり自身の合格体験談を共有したりすることで、受講者の理解を深められます。
講師役の技術者には、事前に指導方法に関する簡単な研修を受けてもらうと良いでしょう。
こうした取り組みは質の高い研修の実現だけでなく、社内の技術継承を促進する効果も期待できます。
STEP4|業務時間内に研修時間を確保し学習に集中できる環境を作る
社員の自己啓発だけに頼らず、会社として業務時間内に研修時間を確保しましょう。
業務後に学習時間を設けるだけでは日々の疲れから集中力が続かず、学習効率が低下しがちです。
会社が積極的に学習環境を整える姿勢を示すと、受講者の意欲も高まります。
学習に集中できる環境づくりの例
- 毎週水曜日の午後を研修時間として設定
- 研修期間中は対象者の定常業務の一部を免除
- 静かな会議室を研修専用の自習室として開放
- 研修用のオンラインツールや参考書籍を会社負担で購入
支援体制を整えることで、受講者は安心して学習に専念できます。
STEP5|資格取得者への報奨金などモチベーション維持の仕組みを導入する
資格試験の学習は長期にわたるため、モチベーションを維持する仕組み作りが重要です。
例えば、合格者に対して報奨金や資格手当といったインセンティブを用意することで、学習意欲の向上を図れます。
| 制度の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 報奨金 | 合格時に10万円を支給する |
| 資格手当 | 毎月の給与に1万円を上乗せする |
| 人事評価への反映 | 昇進や昇格の評価項目に加える |
明確な報酬制度は、受講者にとって学習を続けるうえで魅力的な目標となります。
努力が正当に評価される仕組みを整えることで、最後までやり抜く力を引き出しやすくなります。
施工管理技士の社内研修でよくある質問
最後に、施工管理技士の社内研修でよくある質問にお答えします。
社内に適切な講師が見当たらない場合はどうすれば良いですか?
社内に適切な講師が見当たらない場合は、外部リソースの活用と社内でのサポート体制を組み合わせるのが効果的な解決策です。
無理に1人の講師に任せるのではなく、柔軟な方法を検討しましょう。
講師が見当たらない場合の対策例
- 外部から専門講師を招いてスポットで講義を依頼する
- 複数の若手・中堅社員が科目ごとに分担して講師役を務める
- 経験豊富なOB技術者に講師を依頼し、技術伝承の機会とする
- 資格予備校などが提供するオンライン講座を法人契約で活用する
こうした方法を組み合わせることで、特定の社員に負荷が集中するのを防ぎつつ、質の高い研修を実現できます。
また、eラーニングをうまく活用すると外部から講師を招く必要がなくなるため、大幅にコストを抑えることも可能です。
社内に教えられる人材がいない場合は、eラーニングの活用を検討してみてください。
業務と学習を両立させるための工夫はありますか?
個人の努力だけに任せるのではなく、以下のように組織的な工夫を取り入れましょう。
| 工夫の種類 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 時間の有効活用 | スマートフォンで学べるeラーニングを導入して移動時間や休憩時間を活用する |
| 業務量の調整 | 研修期間中は上司が業務量を調整して定時で退社しやすいように配慮する |
| 周囲の協力体制 | 研修の目的をチーム全体で共有して参加者の不在時に業務をフォローする体制を作る |
研修参加者が学習に集中できるよう部署全体で協力する雰囲気を作ることが、両立を成功させるうえで大切です。
研修の効果はどのように測定すれば良いですか?
研修の効果は最終的な資格試験の合格率だけでなく、多角的な指標で測定することが望ましいです。
研修効果の測定指標の例
- 資格試験の合格率
- 研修の満足度や理解度(アンケートで調査する)
- 模擬試験の点数の推移
- 受講者からの研修内容に関する改善提案
- 研修で学んだ知識の実務での実践報告
合格率のような定量的なデータとアンケートのような定性的な意見を組み合わせることで、研修プログラムの成果を正しく評価できます。
eラーニングなどの外部サービスと組み合わせるべきですか?
社内研修とeラーニングなどの外部サービスを組み合わせる「ブレンディッドラーニング」は、効果的な手法です。
それぞれの利点を生かすことで、研修の質と効率を同時に高められます。
例えば、基礎知識の習得や試験範囲の網羅はeラーニングに任せ、社内研修では自社の事例を用いたケーススタディや質疑応答に時間を集中させるといった使い分けが可能です。
外部サービスもうまく取り入れ、社内講師の負担を軽減しつつより充実した学習機会を提供しましょう。
参考記事:【必見】建設業がeラーニングを導入すべき3つの理由と具体的メリット
まとめ
今回は、施工管理技士の研修の内製化や効果的な育成方法などを解説しました。
最後にもう一度、効果的な社内研修を設計するためのステップをまとめておきます。
効果的な社内研修を設計するための5つのステップ
- 目標の合格人数を決める
- 受講対象者を選定し学習スケジュールを策定する
- 社内のエース級技術者を講師として任命・育成する
- 業務時間内に研修時間を確保し学習に集中できる環境を作る
- 資格取得者への報奨金などモチベーション維持の仕組みを導入する
社内研修の仕組みを整えることで、企業の技術力は着実に向上していきます。
「研修を整備したいけど、時間もコストもかけられない…」という場合は、eラーニングConstruction Boardingがおすすめです。
ポイント
スマートフォンやPCからいつでもどこでも学習できるため、現場が忙しい企業様の悩みを解決するのに役立ちます。
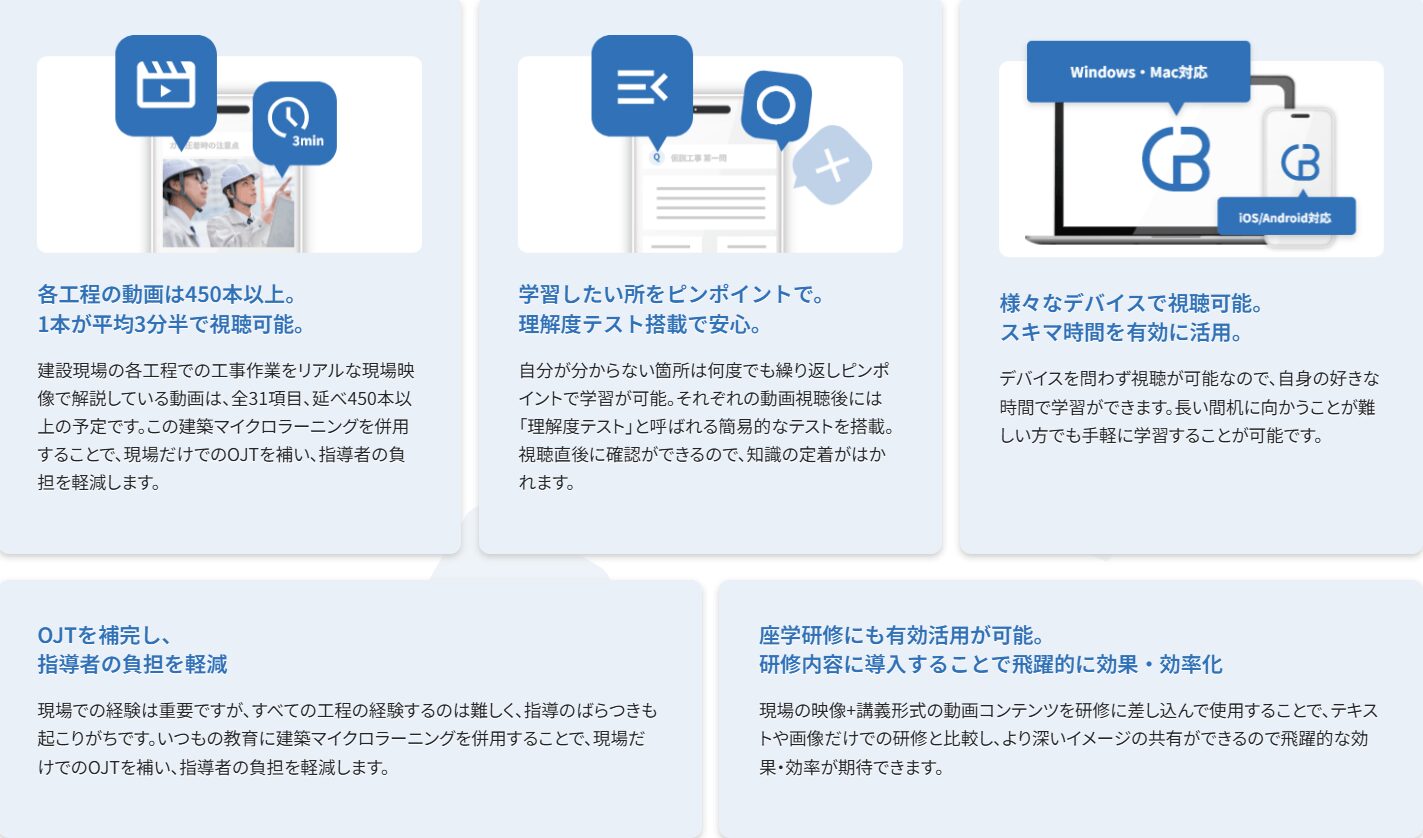
無料で2週間のトライアルができ、さらに人材開発支援助成金の対象となるため、低コストで質の高い研修を実施できます。
「まずはお試しで始めたい」「低コストで研修を整えたい」という方は、お気軽に資料請求してみてください。
貴社の施工管理研修の参考になれば幸いです。