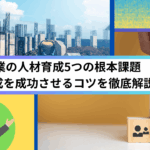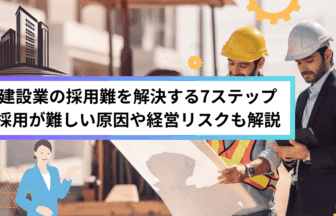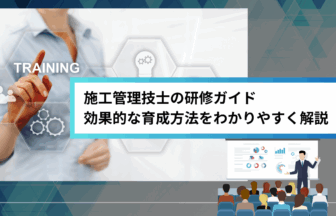「建設業で社員に資格を取得させたいけど、使える助成金はないかな?」
「助成金の申請手順が複雑でよくわからない…」
このような悩みを抱える建設会社の方に役立つ記事です。
この記事でわかること
- 建設業の資格取得で使える「人材開発支援助成金」について
- 資格取得以外で使える建設業の助成金
- 建設業の助成金を申請する5つの手順
建設人材の資格取得には「人材開発支援助成金」を活用可能です。
助成金を活用すると社員のスキルアップにかかる費用を軽減しながら、計画的に人材育成を進められます。
「でも、助成金の申請手順がわかりにくい…」と思いますよね?
この記事では、助成金の具体的な申請手順や、失敗しないための注意点などを詳しく解説します。
建設人材の資格取得におすすめのeラーニング
建設人材の資格取得には、ワット・コンサルティングのeラーニング「Construction Boarding」がおすすめです。
人材開発支援助成金の対象となります。
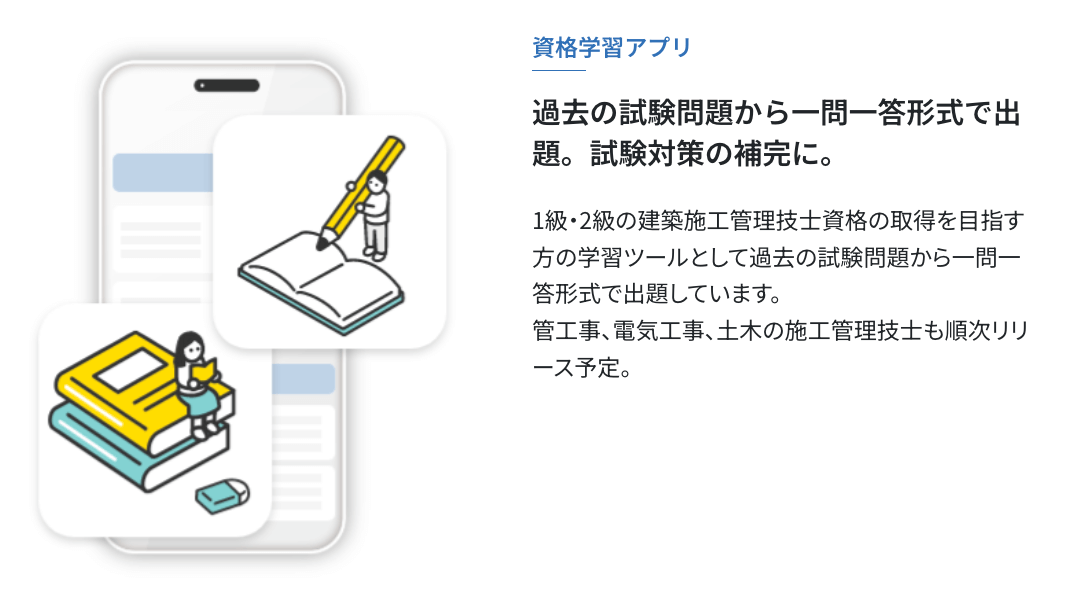
eラーニングなので、忙しい人材でも隙間時間で学習を進められます。
資格取得の研修がない企業にもおすすめです。
無料で2週間のトライアルもできるので、試しながら検討してみてください。
目次
建設業の資格取得で使える「人材開発支援助成金」
企業の技術力向上や人材育成を支援するために、国は「人材開発支援助成金」を設けています。
ここでは、建設業の資格取得で使える「建設労働者技能実習コース」「人材育成支援コース」について詳しく解説します。
建設労働者技能実習コース
建設労働者技能実習コースは、若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を目的とした制度です。
キャリアに応じた技能実習を実施した場合、助成金が支給されます。
中小建設事業主が制度を利用する場合の助成額は、以下のとおりです。
| 助成の種類 | 助成内容 |
|---|---|
| 経費助成 | ・雇用保険被保険者数が20人以下の場合は支給対象費用の3/4 ・雇用保険被保険者数21人以上の場合、35歳未満は支給対象費用の7/10、35歳以上は9/20 ・女性建設労働者に技能実習を行う場合は支給対象費用に対する所定の割合を助成 |
| 賃金助成 | ・雇用保険被保険者数20人以下の場合は1日あたり8,550円 ・雇用保険被保険者数21人以上の場合は1日あた7,600円 ※建設キャリアアップシステム技能者情報登録者は増額 |
現場で必要な資格を取得させる際に、費用の負担を軽減できる制度です。
参考:厚生労働省|建設事業主等に対する助成金 パンフレット
人材育成支援コース
人材育成支援コースは、従業員の職務に関連した知識やスキルを習得させるための訓練を実施した場合、賃金の一部が助成される制度です。
建設業に特化した制度ではありませんが、幅広い訓練に利用できます。
ポイント
例えば「10時間以上のOFF-JT」「新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練」などが対象です。
中小企業が正規雇用労働者に対して利用する場合の経費助成率は45%、訓練中の賃金として1人1時間あたり800円が助成されます。
OFF-JTだけでなく、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練にも活用できる点が特徴です。
人材開発支援助成金が対象のeラーニング「Construction Boarding」

人材開発支援助成金を活用して資格取得の試験対策を行うなら、Construction Boardingがおすすめです。
施工管理技士などの資格取得サポートに活用でき、人材開発支援助成金でコストを抑えながら研修を実施します。
Construction Boardingの特徴
- 1級・2級の施工管理技士試験対策に対応
- 過去問を分析した一問一答形式で効率的に学習可能
- 1つの動画が3分前後と短く、隙間時間を活用可能
- スマホ・タブレット・PCでいつでもどこでも学習
- 理解度テストで知識の定着を確認
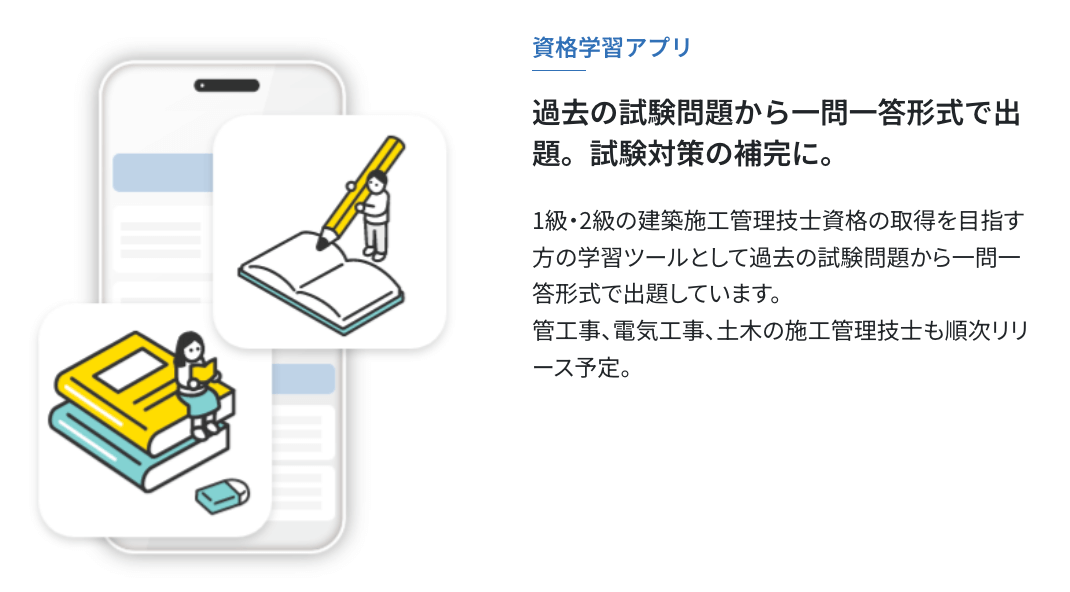
資格学習アプリは過去の試験問題を分析しており、効率的に試験対策ができます。
資格取得以外で使える建設業の助成金
資格取得の支援だけでなく、人材の確保や定着、労働環境の改善などを目的とした助成金もあります。
資格取得以外で使える主な助成金
- 人材確保等支援助成金
- キャリアアップ助成金
- トライアル雇用助成金
- 働き方改革推進支援助成金
採用活動や従業員の待遇改善にかかる費用を抑えたい方は、参考にしてみてください。
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、従業員の人材確保に取り組む事業主を支援する制度です。
建設分野では、若年者や女性が働きやすい魅力的な職場づくりを支援する「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース」などが設けられています。
このコースの対象経費は以下のとおりです。
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースの対象経費の例
- 講師謝金
- コンサルティング料
- 賃金
- 教材費
- 受講参加料など
支給される助成金の上限は200万円です。
若年者や女性が働きやすい環境を整備し、人材の定着を図る際に活用できます。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員化や処遇改善の取組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
主なコースは、有期契約労働者を正社員に転換した場合に助成が受けられる「正社員化コース」で、中小企業の場合は1人あたり以下の金額が支給されます。
中小企業で1人あたりに支給される額
- 「重点支援対象者」の場合:80万円(40万円×2期)
- それ以外の有期雇用労働者:40万円(40万円×1期)
「重点支援対象者」の定義は以下のとおりです。
重点支援対象者の定義
- 雇い入れから3年以上の有期雇用労働者
- 雇い入れから3年未満で、過去5年間の正規雇用期間が合計1年以下かつ過去1年間正規雇用されていない者
- 派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定訓練修了者
人手不足が続く建設業において、非正規雇用の従業員の意欲向上と定着を促す上で効果的な制度です。
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、職業経験や技能の不足などから就職が困難な求職者を「お試し」で雇用する事業主に対して助成する制度を指します。
建設業向けの制度は「若年・女性建設労働者トライアルコース」です。
ポイント
このコースは、35歳未満の若年者や女性を建設技能労働者として試行雇用した場合「最大4万円/月 × 3ヶ月(最大)」が支給されます。
お試しで若手人材を雇用できるため、採用のリスクを軽減できる点が魅力的な制度です。
参考:厚生労働省|トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金は、生産性を向上させながら、労働時間の削減や年次有給休暇などの推進に取り組む中小企業を支援する制度です。
例えば、勤怠管理システムを導入して業務効率化を図り、時間外労働時間を短縮する成果目標を達成した場合、設備導入費用の一部が助成されます。
ポイント
成果目標は3つあり、成果目標1を達成すると最大150万円が支給されます。
労働環境を改善しつつ、法令を遵守しながら生産性を維持・向上させたい企業におすすめの制度です。
参考:厚生労働省|働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
建設業の助成金を申請する5つの手順
ここでは、建設業の助成金を申請する手順を解説します。
助成金申請の基本的な5ステップ
- 管轄の労働局で相談する
- 訓練計画書を作成する
- 労働局へ必要書類を提出して認定を受ける
- 計画に基づき資格取得(訓練)を実施する
- 支給申請書と必要書類を提出する
助成金の申請を検討中の方は、参考にしてみてください。
①管轄の労働局で相談する
まずは、会社の所在地を管轄する労働局の助成金窓口への事前相談です。
例えば、利用したい助成金が自社の計画(資格取得など)に合致しているか、受給要件を満たしているかなどを専門家に相談します。
ここで計画の概要を伝え、申請できるかを確認しましょう。
②訓練計画書を作成する
窓口相談のあとは、助成金の申請に必要な「訓練計画書」を作成します。
助成金は国が定めた計画に基づいて実施された訓練に対して支給されるため、詳細な計画書の作成が必須です。
ポイント
訓練計画書を提出することで「どのような訓練を、いつ、誰に実施するか」を明確に示します。
書類は厚生労働省の様式に従って正確に作成しましょう。
③労働局へ必要書類を提出して認定を受ける
次に、労働局へ必要書類を提出してください。
提出期限は以下のとおりです。
| 助成金の種類 | 提出期限 |
|---|---|
| 人材開発支援助成金(人材育成支援コース等) | 訓練開始日から起算して6ヶ月前から1ヶ月前までの間 |
| 建設労働者技能実習コース | 技能実習開始日の3ヶ月前から1週間前まで |
必要書類は以下のとおりです。
必要書類
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号)
- 事前確認書(様式第11号)など
認定を受けずに訓練を開始した場合、助成金は支給されません。
必ず訓練前に必要書類をご提出ください。
④計画に基づき資格取得(訓練)を実施する
計画書に記載したとおりに資格取得の訓練(技能講習など)を実施します。
計画と異なる訓練を実施したり受講者が変わったりすると、支給対象外となる可能性があるため注意が必要です。
訓練実施中は、以下の点を正確に管理・記録しましょう。
| 管理・記録が必要な項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 出欠管理 | 訓練実施日ごとの受講者の出欠状況(タイムカードや出勤簿) |
| 費用管理 | 訓練機関に支払った受講料や教材費の領収書 |
| 訓練内容 | 計画どおりに実施されたことを示す訓練日報 |
こうした記録は支給申請時に提出を求められるため、管理と記録が必要です。
⑤支給申請書と必要書類を提出する
訓練終了日の翌日から2ヶ月以内に労働局へ「支給申請書」と必要書類を提出します。
支給申請時に必要な書類の例
- 支給申請書(様式第4-1号)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 経費助成の内訳(様式第6-1号)
- 対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写しなど
計画通りに訓練を実施し、要件を満たしていることを証明する最終手続きです。
支給審査を通過すると、登録した振込先に助成金が振り込まれます。
建設業の助成金申請で失敗しないための注意点
ここでは、助成金を申請する際の注意点を解説します。
助成金申請で失敗しないための注意点
- 訓練実施前に計画届を提出する
- 助成金の対象となる経費の範囲を確認する
- 労働保険料の滞納がない状態にしておく
それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。
訓練実施前に計画届を提出する
多くの助成金は、労働局が事前に計画を認定することが支給の前提条件になっています。
例えば、4月1日から始まる講習の計画届を4月1日以降に提出しても受理されません。
ポイント
すでに始まってしまった訓練は助成金の対象外となるため、注意が必要です。
資格取得のスケジュールを決めたあとは、定められた期限までに計画届をご提出ください。
助成金の対象となる経費の範囲を確認する
申請した経費はすべて認められるわけではありません。
資格取得(訓練)の場合、一般的に対象となる経費とならない経費は以下になります。
| 区分 | 経費の例 |
|---|---|
| 対象となる経費 | 受講料や教科書代 |
| 対象とならない経費 | 交通費や宿泊費、PC等の機材購入費 |
あくまで一例のため、参考程度にお考えください。
利用する助成金制度によって対象となる経費は異なります。
対象外の費用を申請しても助成されないため、事前に確認した上で申請しましょう。
労働保険料の滞納がない状態にしておく
納付義務を果たしていない事業主は支給対象から除外されます。
申請書類の提出時に、労働保険料の納付状況を示す書類(納付書や領収書)の提出を求められるのが一般的です。
申請手続きを始める前に自社の納付状況を必ず確認し、未納があれば速やかに納付を済ませましょう。
建設業の助成金についてよくある質問
最後に、建設業の助成金についてよくある質問にお答えします。
玉掛けやクレーンなどの技能講習も対象になる?
利用する助成金制度によっては対象となる可能性があります。
例えば、人材開発支援助成金の「建設労働者技能実習コース」は対象となります。
建設労働者技能実習コースの対象例
- 玉掛け技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- フォークリフト運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
こうした講習は、建設現場の安全と技術力向上に直結する訓練です。
助成金を積極的に活用することで、費用を抑えつつ社員の教育を進められます。
助成金はいつ振り込まれる?
助成金は原則として後払いです。
先に訓練を実施し、事業主が訓練機関への支払いをすべて完了させたあとで、労働局へ支給申請を行います。
ポイント
支給申請書と必要書類(領収書や出勤簿など)を提出し、労働局での審査を経て助成金の支給が決まる流れです。
審査には一定の期間を要するため、申請書の提出から実際の振込みまでは数か月程度を見込んでおきましょう。
複数の助成金を同時に利用することは可能?
対象となる従業員や助成金の利用目的などが分かれている場合は、複数の助成金を同時に利用できる可能性があります。
例えば、Aさんの資格取得には「人材開発支援助成金」で、Bさんの正社員転換には「キャリアアップ助成金」を利用する、といった使い分けが考えられます。
計画段階で管轄の労働局に相談し、併用できるかを確認してみてください。
まとめ
最後にもう一度、助成金の申請手順をまとめておきます。
建設業の助成金を申請する5つの手順
- 管轄の労働局で相談する
- 訓練計画書や支給要件を作成する
- 労働局へ必要書類計画書を提出して認定を受ける
- 計画に基づき資格取得(訓練)を実施する
- 支給申請書と必要書類を提出する
この記事で紹介した手順や注意点を参考に、助成金を活用して人材の資格取得を進めましょう。
ちなみに、建設人材の資格取得にはConstruction Boardingのようなeラーニングツールが効果的です。
忙しい現場でも隙間時間に学べる短時間設計で、スマホやPCから気軽にアクセスできます。
施工管理技士の試験対策コンテンツが充実しているため、資格取得と若手の早期戦力化の両立に役立ちます。
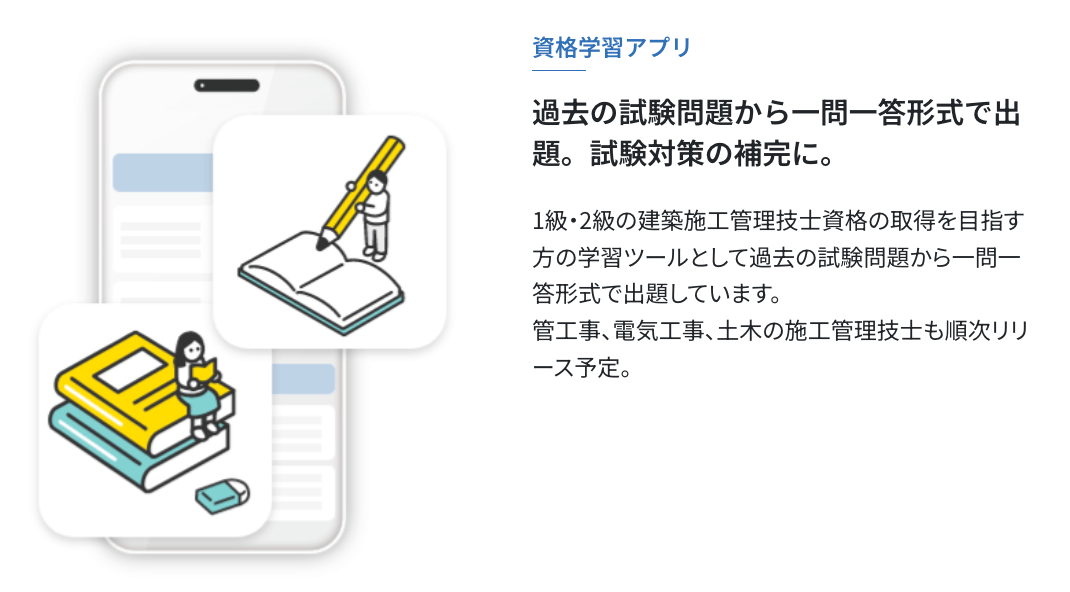
人材開発支援助成金の対象となるため、低コストで質の高い研修を実施可能です。
今すぐ資料請求して、自社の人材育成に役立ててください。
貴社の人材育成の参考になれば幸いです。