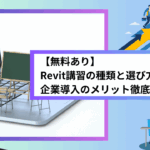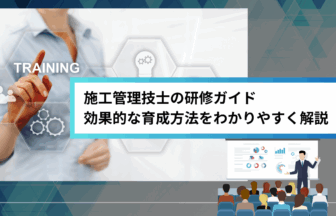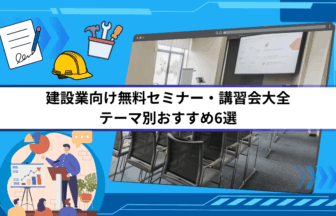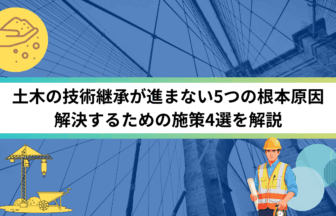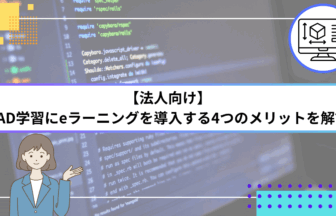「BIMの講習を社内に導入したい」
「BIM講習の選び方を知りたい」
こういった経営者・研修担当者様向けの記事です。
この記事でわかること
- BIM講習を導入するメリット
- 講習スタイルごとのメリットとデメリット
- 職種別のBIM講習の選び方
社内の人材のBIMスキルを効率的にアップさせたい場合は、BIM講習を導入しましょう。
体系的に学んだり、わからないことをすぐ解決できたりする講習だと、知識の習得が早いです。
ポイント
業務効率化したり、コストカットしたりできる点で、社内のBIMスキル向上は効果的です。
他社と差別化できる可能性もあるため、積極的にBIM講習を実施しましょう。
この記事では、BIM講習のメリット・デメリットや、講習の選び方を徹底解説しています。
貴社に合う講習を選んで、社内のBIMスキルを高めたい場合は、最後まで読んでみてください。
BIM講習は、株式会社ワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」がおすすめです。
いつでもどこでも学べるeラーニングなので、BIMを使いたい人材が忙しい場合でも導入しやすいです。
Construction Boardingが合う企業様の特徴
- BIMの人材育成に割く資金が足りない
- 残業を減らしながら人材育成する時間を捻出できない
- 社内でBIM講習制度を作るノウハウがない
無料で2週間のトライアルができて、さらに助成金の対象となるeラーニングです。
「まずはお試しで始めたい」「低コストでBIM講習を実施したい」という場合は、お気軽に資料請求してみてください。
※前置きはいいから、早く「BIM講習の選び方を教えて!」という方は、BIM講習の種類と特徴|メリットとデメリットも解説にジャンプしてみてください。
この記事の監修者
施工管理の技術者派遣と研修を行う会社です。
- 労働者派遣事業許可番号 派13-304593
- 有料職業紹介事業許可番号 13- ユ-304267
- 特定建設業 東京都知事許可 (特-1) 第150734号
目次
BIM講習が求められる背景
建設業界では、国土交通省が進めるi-ConstructionやBIM/CIMの推進を背景に、デジタル技術を活用して生産性を高めるDX化が急速に求められています。
BIM(Building Information Modeling)は、建物を3次元モデルで可視化し、設計から施工、維持管理までの情報を一元的に共有できる技術です。これにより、図面の不整合や手戻りの削減、施工計画の最適化など、業務効率化とコスト削減が期待できます。
一方、建設業界は人材不足が問題になっています。当然ながら、BIMの技術者も不足している状態です。BIM講習を通じて業務を効率化し、少人数でもプロジェクトを進めていく仕組み作りが急務となっています。
BIM講習を実施して、DX化や人材不足に対応していきましょう。
※前置きはいいから、早く「BIM講習の選び方を教えて!」という方は、BIM講習の種類と特徴|メリットとデメリットも解説にジャンプしてみてください。
BIM講習を導入する4つのメリット
BIM講習を社内に導入すると、以下のメリットがあります。
BIM講習を導入するメリット
- 業務効率が向上する
- コストカットできる
- 営業活動しやすくなる
- 人材を採用しやすくなる
プロジェクトの生産性が高まり、人材採用でも優位に立ちやすくなるでしょう。メリットを1つずつ解説していきます。
業務効率が向上する
BIMを身につけた人材が増えると、設計や施工にまつわる手戻りが減り、全体の作業がはかどります。図面の変更が発生した場合でもデータの連動によって修正をまとめやすく、複数部門で共有しやすい点が強みです。
例えば、以下のような業務で効率化が進むでしょう。
こうしたフローを浸透させれば、従来はアナログだった工程もスムーズに連携できるようになります。BIMツールを効果的に使う社員が増えるほど、無駄なやり取りや入力ミスを最小限に抑えられます。
BIMベースの作業手順を習慣づけると、部門をまたぐ情報共有が円滑になるでしょう。
コストカットできる
BIMを使いこなした社員がいると、建設プロセス全体の無駄が見えやすくなります。作業手順を一元管理しやすいぶん、材料の発注や工期の見直しなどでコストを抑えられるケースが増えるでしょう。
例えば、以下のような面で費用負担の低減が望めます。
BIM活用でコストカットできる例
- 二重発注や材料ロスの軽減
- 事前のシミュレーションで工程の手戻りを低減
- 打ち合わせ時間や現場移動コストを削減
- 紙や図面の出力費を最小限に抑える
BIM運用を定着させれば、大掛かりな設計変更が起きてもスムーズに再計算ができます。アナログ作業に頼っていた頃と比べ、必要経費を早期に把握しやすい点も特徴です。
将来的には運営コスト全般を見直すきっかけになる可能性があります。
営業活動しやすくなる
BIMを習得した担当者がプレゼンテーションする場面では、三次元モデルを見せながら提案を進められます。紙の図面だけでは理解しにくかった部分も、完成イメージを視覚化すれば発注側の納得を得やすいです。
例
大規模なリノベーション案件なら、客先が具体的な空間レイアウトをイメージしやすく、成約率アップにつながる可能性があります。
出典:国土交通省|官庁営繕事業の設計業務における BIM 活用の目安に
また、新規顧客を獲得するときには「BIM活用による精度の高い見積もり」がセールスポイントです。可視化されたモデルを提示しつつ、工程やコスト面を明確に示せるため、競合よりも説得力のある営業を進められます。
プロジェクトの初期段階で信頼を得やすくなり、大きな案件を受注するチャンスが広がるでしょう。
人材を採用しやすくなる
社内でBIMの研修を設けておくと「この企業に転職すればBIMを学べる」と候補者に認識されて、人材を採用しやすくなる可能性もあるでしょう。BIMスキルを身につけたい人材は多く、採用面で他社と差別化しやすくなります。
さらに
社内でBIMスキルが根付くと教育担当が育ち、新人が迷わずに実務を覚えられます。
BIM講習を取り入れて社内で教え合う文化を外部にアピールすると、優秀な人材を採用できるかもしれません。
BIM講習の種類と特徴|メリットとデメリットも解説
BIMを導入する際、講習のスタイルによって学習効率やコストが違います。企業によって最適な研修が違うため、自社に合った講習を導入しましょう。
以下の表は、代表的な4種類のBIM講習を比較したものです。
それぞれの詳細をチェックしながら、自社に合うスタイルを探してみてください。
集合研修
集合研修は、対面で講師と意見を交わしたいときに役立ちます。演習形式で実践しながら学ぶと、トラブル時の対処法をリアルタイムに吸収しやすいです。全員が同じ空間でワークを進めれば、研修後の情報共有もスムーズになります。
会場費や移動費はかさみがちですが、熱量の高い学習環境を整えたい企業に向いているでしょう。
eラーニング
eラーニングは場所を選ばず学べるため、全員を同じ時間・同じ場所に集めるのが難しい場合や、出張コストを抑えたい場合に役立ちます。テキストや動画を繰り返し閲覧できるので、苦手箇所を念入りに学ぶのにも向いています。
モチベーションの持続を図るために、進捗を管理する体制やシステムがあると良いでしょう。
【無料から試せる】BIMでおすすめのeラーニング
冒頭でもお伝えしましたが、BIM講習は「Construction Boarding」がおすすめです。
Construction BoardingはBIMを学べるeラーニングなので、担当者が自分のペースで学べます。
社内の技術者を集めて集合研修する必要がないため、まとまった時間を確保する必要がありません。
進捗管理機能もあるため、メンバーのモチベーション維持もしやすいです。
ポイント
さらに「Construction Boarding」は、低コストでBIM講習を導入できます。
無料で2週間のトライアルもあるため、お気軽に資料請求してみてください。
オンライン講習
オンライン講習は双方向でやりとりできるものの、全員が離れた場所にいる前提です。リアルタイム性があるため、その場で質問できますが、集合研修ほどの一体感は生まれにくいかもしれません。
支店が遠方に点在している企業や、移動コストを抑えたいときに適しています。講師の画面を見ながら操作手順を覚える場面では、チャット機能などで随時質問すると理解度が高まりやすいです。
メーカー公認の講習
メーカー公認講習は、ソフトウェアの標準操作やアップデート内容を正確に覚える場面で役立ちます。公認の修了証を受け取れるケースが多く、外部への実績アピールもしやすいです。
公式の基本知識を押さえつつ、現場の実務と結びついたノウハウを学べる研修もセットで用意すると良いでしょう。
職種別|BIM講習の選び方

BIMを導入する際は、職種ごとに注目する機能が異なります。設計者、施工管理者、設備担当者がほしい機能や学びたい内容を整理しないと、研修の成果が薄れる恐れがあるでしょう。
以下では、それぞれの職種に合ったBIM講習の選び方を解説します。
設計者向けBIM講習の選び方
設計者が扱う範囲は空間レイアウトや建築意匠が挙げられます。BIMを使って形状や寸法を俯瞰しながらプランを検討すると、修正作業の回数が減りやすいです。
例
レンダリング機能やモデリング演習を含む講習を選べば、発注者に見せるプレゼン資料の完成度が高まります。
また、図面と連動させて変更箇所を自動反映できるカリキュラムを選べば、細部の管理を効率化しつつ全体像を把握できるでしょう。最終的にデザイン面で魅力的な建築モデルを提案できるため、クライアントの満足度が向上します。
設計者向けのBIM講習を選ぶ際は、以下に注目してみてください。
設計者向けBIM講習を選ぶ際のチェックポイント
- 意匠デザインを三次元で検討できるカリキュラムがあるか
- 図面修正時にモデルへ瞬時に反映させる仕組みを学べるか
- レンダリングやCG出力に対応した実践演習があるか
- 色や素材設定まで細かく扱う可視化の手順がわかるか
空間表現を重視する設計者がBIMを使いこなすと、顧客への提案がわかりやすくなるでしょう。
施工管理向けBIM講習の選び方
BIMを施工管理者が使いこなすと、工程や資材の管理を効率化できます。図面を紙で頻繁に出力しなくても、変更内容を三次元モデル上で共有できれば、工期短縮やトラブルを防止しやすくなります。
例
干渉チェック機能や工程シミュレーションを学べる講習を選ぶと、現場での段取りや発注管理を一元化しやすいでしょう。
修正点が増えても、モデル上で再検討して必要部材を明確にすれば、コスト面でも無駄を減らせます。さらに、品質と安全に配慮しながら進捗を管理しやすくなるのも利点です。
施工管理向けのBIM講習を検討する際に、チェックしておきたい点は以下のとおりです。
施工管理向けBIM講習を選ぶ際のチェックポイント
- 工程表とモデルを連動させて進捗管理する方法を学べるか
- 干渉検討機能を使って施工不良を抑制する手順がわかるか
- 積算システムと結びつけて重複発注を防ぐ仕組みがわかるか
- 品質管理や安全管理に役立つ計測・記録の使い方を学べるか
BIMに精通する施工管理者が増えれば、現場の統率力が上がり、納期も守りやすくなります。
設備担当向けBIM講習の選び方
設備担当者がBIMを導入すると、空調や配管などのレイアウトを三次元で把握しやすくなります。換気ダクトや電気系統を立体的に検証しながら検討すれば、干渉リスクを事前に見つけられるでしょう。
例
空調負荷のシミュレーションや機器同士の連携手順を学べる研修であれば、保守やメンテナンスの段取りにも役立ちます。
各設備のパラメータを細かく設定し、運用データと結合する流れも学べれば、将来的な改修時にもスムーズに反映しやすいです。設備担当者向けのBIM講習では、メンテナンス性と拡張性に重きを置いたカリキュラムが有効でしょう。
設備担当者向けBIM講習では以下をチェックすると安心です。
設備担当者向けBIM講習を選ぶ際のチェックポイント
- 空調や配管など設備別のモデリングの手順を学べるか
- メンテナンスを視野に入れたデータ管理の仕方がわかるか
- シミュレーション機能で負荷や熱源を計算する方法を学べるか
- 改修や増設時に備えるための情報記録や引き継ぎを学べるか
設備担当者がBIMを使いこなせると、建物全体の運用コストが抑えられ、長期的な保守計画にも役立ちます。
BIM講習を通じた学習ロードマップ

BIM講習を通じて、社員のスキルアップをはかりましょう。基礎から段階的に学ぶと、実務へ落とし込みやすいです。
以下は大まかな学習ロードマップです。
BIM講習を通じた学習ロードマップ
- BIM基礎知識の習得
- BIMの基本操作の習得
- 社内テンプレートの作成
- プロジェクトを通じた実践
- BIMの応用スキルの習得
1つずつ解説するので、スキル定着を目指してみてください。
ステップ1:BIM基礎知識の習得
BIMの役割と活用イメージを理解すると、後の操作や応用を把握しやすくなります。データベースとして部材情報を管理する考え方や、2D設計との違いを把握すると、プロジェクト全体を見通せるでしょう。
以下は主に押さえておきたいBIMの基礎知識です。
| 学ぶ項目 | 内容の例 |
|---|---|
| BIMとは何か | 2Dと3Dの相違点や、要素同士を関連づける仕組みを理解する |
| 業界の動向 | 国内外のBIM化の現況と主要ソフトウェアの普及状況を把握する |
| データベース思考 | 属性情報を一元管理し、モデルと連動させる基本的な考え方を学ぶ |
| 連携メリット | 意匠・構造・設備が同じモデルを参照できるため、誤差や重複作業を減らしやすい |
社内での利用目的をはっきりさせ、業務フローのなかでBIMがどう活用されるかを意識して学ぶと良いでしょう。
ステップ2:BIMの基本操作の習得
次に、実際にソフトウェアを操作しながら機能を習得していきます。コマンドや画面構成は異なることも多いため、メインで使うソフトの操作に集中すると良いでしょう。
基本操作で学ぶ例は以下のとおりです。
| 学ぶ項目 | 内容の例 |
|---|---|
| インターフェースの把握 | ツールバーやパネル位置、ショートカット設定などを把握して画面を見やすくする |
| 基本モデリング操作 | 壁や床、窓などを配置・編集し、寸法や属性を設定する一連の流れを習慣化する |
| 図面やビューの設定 | 3Dビューの切り替えや断面図・立面図の作成方法など、表示形式を柔軟に調整する |
| 外部連携の下準備 | 他形式へのエクスポートや、他ソフトとの互換性の確認手順を身につける |
基本機能を一通り扱えるようになるまで、公式のチュートリアル動画や事例集を参考にすると効率が上がります。最初から機能を深追いしすぎず、必要最低限の操作を確実にこなしながら慣れていくと、後で応用しやすいです。
ステップ3:社内テンプレートの作成
基本操作を覚えたら、自社のプロジェクトに合うテンプレートを整えると、作業効率が向上しやすいです。
例
部材属性の標準設定や、図面のレイアウト、注釈の設定などをテンプレートにまとめておけば、複数の社員が同じ基準で作業を進められます。
テンプレートの具体例は以下のとおりです。
| テンプレートの種類 | 具体例 |
|---|---|
| 設計テンプレート | 壁厚や標準の階高をあらかじめ設定し、よく使うファミリやパーツを組み込んでおく |
| 施工管理テンプレート | 進捗管理や検査用のビューをあらかじめ用意し、躯体表記などをわかりやすく調整しておく |
| 設備テンプレート | ダクトや配管の呼び径や材質をデフォルトで登録し、標準ルールに沿ったレイアウトを設定しておく |
社員全員が同じ初期設定を使えば、個人差によるデータのばらつきを減らせます。テンプレートは、導入後に運用を通じて改善を重ねると精度が上がり、次のプロジェクトで再利用しやすくなるでしょう。
ステップ4:プロジェクトを通じた実践
ある程度操作に慣れた段階で、実際のプロジェクトを題材にBIMを操作すると、スキルが身につきます。
例
新築の小規模オフィス棟や、既存のビル改修案件をBIMで進めるといったケースもあるでしょう。
意匠・構造・設備が絡む案件であれば、連携のシミュレーションとしても役立ちます。工期やコストの制約があるなかでモデルを活用し、設計変更や干渉チェックを行う場面は理解を深める良い機会です。
納期や予算を意識しながら操作する習慣が身につくと、プロジェクトの完成度が上がります。
ステップ5:BIMの応用スキルの習得
基本操作とプロジェクト実践を重ねたあとは、応用スキルを学んでいきましょう。例えば、4Dや5Dと呼ばれる工程・原価管理への連動、VRやARを組み合わせたプレゼンテーションなどがあります。
以下の表に応用スキルの具体例をまとめました。
| 応用スキル | 内容の例 |
|---|---|
| 4D/5Dシミュレーション | 時系列で工程を可視化し、費用計算も同時に連動。工期短縮や予算管理の精度を高めやすい。 |
| AR/VR連携 | 立体モデルをリアルタイムでチェック。施主へのわかりやすいプレゼンや遠隔立会いに活用可能。 |
| スクリプトの活用 | API連携やスクリプトを使った自動化。大量修正やパラメトリックデザインの実現に応用しやすい。 |
| クラウド環境との統合 | 遠隔地のチームとモデルを同時編集。社内外とのコラボレーションを加速しやすい。 |
ここまで習熟すると、大規模案件や複数部署が絡むプロジェクトでもBIMをフル活用しやすくなります。自動化や連携機能を使いこなせる人材が増えるほど、組織全体の生産性と競争力が上がるでしょう。
ちなみに、上記のような応用スキルの学習法は、次から解説していきます。
BIMと連動した周辺ツールの学習法
応用編として、BIMと連動した周辺ツールも学習しておくと、業務効率が上がります。
BIMと連動した周辺ツール
- ドローン
- VR/ARツール
- 4D/5Dシミュレーションツール
これらも習得しておくと、他社との差別化もはかりやすいです。学習方法も1つずつ解説していきます。
ドローン
BIMとドローンを組み合わせると、現地の地形情報や建物外観を短時間で取得し、三次元モデル化しやすくなります。従来は人が立ち入りにくい高所や狭い場所の点検に時間がかかりましたが、ドローンなら空撮映像を用いて素早く状況を把握できます。
地形データをBIMに取り込むと、測量精度を高めながら工程も短縮しやすいでしょう。以下はドローンの学習手順の一例です。
敷地形状や既存構造物を正確に把握しながら、設計段階の検討をスムーズに進めやすくなります。遠隔地での調査も含め、リスクや手間を減らしながら作業の効率向上に役立つ方法です。
VR/ARツール
VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を使うと、BIMモデルを実寸大に近い形で表示して、建物内部や設備の配置を立体的に検証しやすくなります。施主や関係者に対して空間イメージを視覚的に伝えられるため、プレゼンや設計変更の打合せが円滑に進むでしょう。
以下にVRやARツールの学習手順をまとめました。
試作段階での検証を繰り返して、完成度を高められる点もメリットです。リアルなスケール感を共有できるため、関係者との意思疎通が取りやすく、施工前の段階で潜在的な問題に気づきやすいでしょう。
4D/5Dシミュレーションツール
BIMモデルに時間軸(4D)やコスト軸(5D)を追加すると、工程や予算を同時に可視化できる利点があります。施工順序や工期をグラフ化しながらモデルと連動させれば、変更やリスクを早期に洗い出しやすいです。
以下は4D/5Dシミュレーションツールの学習手順の一例です。
時間軸と費用を同時にチェックできるため、工程遅延や予算オーバーのリスクに早めに気づけます。計画精度を上げたい現場ほど、この方法を導入するとコスト削減や納期遵守につながります。
BIM講習を導入する際に利用できる助成金・補助金
BIM講習では助成金や補助金を活用できる可能性があります。以下はBIM研修に関連する助成金や補助金制度です。自社で活用できそうかチェックしてみてください。
| 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 社員に職務関連の研修を実施する企業に対して、研修費や研修期間中の賃金を助成する制度。デジタル技術を扱う研修(BIMを含む)が対象になりやすい。 |
| 対象となる企業 | 雇用保険適用事業所なら利用可能中小・大企業とも申請可。社員が雇用保険に加入していることが前提。 |
| 助成・補助される金額 | 中小企業で・研修経費:最大75%助成・研修中の賃金:1時間あたり960円上限(上限時間あり)大企業は助成率・金額ともに低め |
ポイント
私たちが提供する「Construction Boarding」も、人材開発支援助成金の対象です。
コストカットしながらBIM講習を導入したい場合は、お気軽に資料請求してみてください。
| 建築GX・DX推進事業(国土交通省) | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 建築プロジェクトでBIMを導入・活用するために必要な費用を補助。ソフトや機材の導入、BIM講習の実施費用などプロジェクト単位で支援を受けられる。 |
| 対象となる企業 | 建築物の設計・施工を担当する企業が代表となり、協力事業者と連携して申請。建設・設計・設備など業種は問わず。 |
| 助成・補助される金額 | 補助率1/2が基本で、プロジェクト規模に応じて数百万〜数千万円単位の補助も可能。大規模案件では最大数千万円の補助が受けられる |
| IT導入補助金(中小企業デジタル化支援策) | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 中小企業がITツールやソフトを導入して業務効率化や生産性向上を目指す際の費用を補助。BIMソフトも対象ITツールに含まれれば活用しやすい。 |
| 対象となる企業 | 建設業を含む中小企業・小規模事業者。資本金や従業員数の要件を満たす必要がある。事前にIT導入支援事業者と連携して申請。 |
| 助成・補助される金額 | 通常枠は補助率1/2上限450万円など枠によって異なる。複数業務プロセスの導入枠なら上限が引き上げられるケースあり。 |
| ものづくり補助金(中小企業生産性革新支援事業) | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 中小企業が生産プロセス改善やDX化を進める設備投資の費用を国が補助。BIMシステム導入や関連機器の導入も計画内容により対象となる。 |
| 対象となる企業 | 建設業を含む中小企業。建設業の場合は資本金3億円以下または従業員300人以下。革新的取組を審査で評価し、採択方式で決定。 |
| 助成・補助される金額 | 補助率1/2(小規模事業者は2/3)上限額は通常枠で2,500万円さらにデジタル化やグローバル展開枠など事業内容によって上限が上がる場合あり。 |
上記の制度を活用することで、BIM研修費だけでなくソフト導入費やハード購入費、研修中の賃金負担などをカバーできる可能性があります。申請方法や公募期限は毎年見直されるため、最新の申請要領を確認してください。
BIM講習についてよくある質問
最後に、BIM講習についてよくある質問に答えていきます。
独学でBIMを習得できる?
独学でBIMを習得できる可能性はありますが、操作ミスや理解の偏りに気づきにくいデメリットがあります。講習なら疑問点を解消しやすかったり、学習スピードが早かったりします。
また、講習はプロジェクトで必要になるテンプレートやソフト連携のノウハウもまとめて学べるので、実務に直結させやすいでしょう。
初心者でもBIM講習についていける?
BIMには専門用語や操作手順が多く、初心者が不安を感じやすいです。初心者向けのコースがある講習なら、基礎から学べるカリキュラムを組んでいる場合が多いでしょう。
ポイント
導入期の社員が多い会社は、初心者向けの講習を選ぶのがおすすめです。専門用語が少なめだったり、専門用語の詳しい解説がある講習だと、初心者でも知識が定着しやすいです。
ちなみに、私たちが提供する「Construction Boarding」は、BIM初心者にも対応している講習です。
BIM初心者にスキルを身につけてほしい場合は、お気軽に資料請求してみてください。
仕事と並行してBIM講習で学べる?
BIMを学習したいと思っても、現場が忙しくまとまった研修時間を確保しにくい企業もあるでしょう。
ポイント
eラーニング形式であれば録画動画やオンデマンド講座を活用できるため、空き時間を使って学びやすいです。
長時間の集合研修に比べ、業務と並行しながら細切れの時間で学習を進められます。社内で進捗を共有したり、フォローアップ機能がある講習を受けたりすれば、モチベーションを維持しながらスキルを身につけられるでしょう。
BIM講習ではどの程度のPC環境が必要?
BIMソフトを扱う環境では、ある程度のCPUやグラフィックの性能が必要です。大規模なモデルを表示する場合はメモリ不足が作業効率に影響するため、スペックに余裕があるパソコンが望ましいでしょう。
以下は参考となるPC環境の目安です。
| 項目 | スペックの目安 |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7以上、または同等クラス |
| メモリ | 16GB以上 |
| グラフィック | NVIDIA GeForce・Quadroなどの専用GPU |
| ストレージ | SSD 512GB以上 |
| ディスプレイ | フルHD(1920×1080)以上の解像度 |
メモリが少ないと、重いファイルを扱う際に動作が遅れる懸念があります。グラフィック能力も重要なので、余裕を持ったハード構成を選べば快適にBIMの学習を進められるでしょう。
BIM講習の費用はどれくらいかかる?
講習の費用は内容によって差があり、なかには1日数万円〜十数万円が必要な講習もあります。
ポイント
一方、eラーニングは安価で、月額数千円から提供している講習も存在します。
複数名がまとめて受講する際は割引する事業者もあるため、コストと得られる効果を比較しながら選ぶと良いでしょう。
まとめ
さっそくBIM講習を導入していきましょう。貴社に合う講習スタイルを検討するところから始めてみてください。
くりかえしですが、BIM講習は「Construction Boarding」がおすすめです。
Construction BoardingはBIMを学べるeラーニングなので、担当者が忙しくても隙間時間で学習できます。
ポイント
「Construction Boarding」は、低コストでBIM講習を導入できます。
無料で2週間のトライアルもあるため、お気軽に資料請求してみてください。
貴社のBIM講習の参考になれば幸いです。