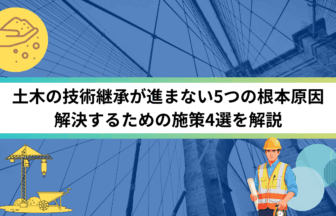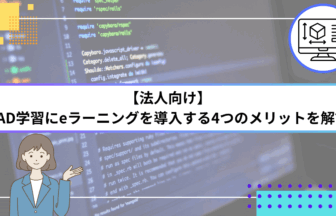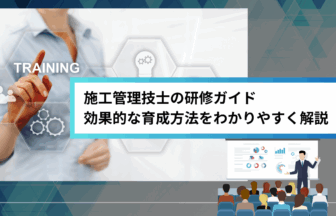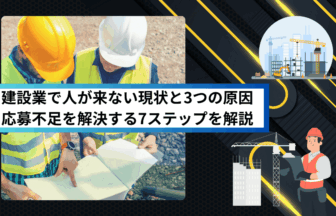「若手の建設人材を採用できない…」
「若手の人材が辞めていってしまう…」
こういった悩みに答える記事です。
この記事でわかること
- 建設業の若者離れが当たり前と言われる7つの理由
- 建設業の若手を採用したり若者離れを防いだりする8つの対策
- 若手に建設業の魅力を伝えて応募を増やす方法
建設業界では若年層の減少とベテラン技術者の高齢化が進み、人材確保と育成が大きな課題となっています。
しかし、適切な対策を講じることで、若手の確保から定着までを実現できる可能性が高まります。
この記事を読むことで、若手人材が集まり、長く活躍する職場づくりのヒントが得られるでしょう。
人材を確保して現状を打破したい建設会社の方は、最後まで読んでみてください。
建設業におすすめの人材育成ツール
建設業の若手の人材育成を効率的に進めるなら、ワット・コンサルティングの「Construction Boarding」がおすすめです。
いつでもどこでも学べるeラーニングで、忙しい建設現場でも若手の人材育成が可能です。
以下に該当する企業におすすめの研修ツールです。
Construction Boardingが合う企業の特徴
- 人材育成に割く資金が足りない
- 残業を減らしながら人材育成する時間を捻出できない
- 若手の育成がうまくいかず定着率が低い
無料で2週間のトライアルができて、さらに助成金の対象となるeラーニングです。
「まずはお試しで始めたい」「低コストで研修を整えたい」という場合は、お気軽に資料請求してみてください。
「早く若手人材を採用する方法を教えて!」という場合は、建設業の若手を採用したり若者離れを防いだりする8つの対策へジャンプしてみてください。
目次
建設業界の現状と若手人材の就業状況
建設業界では若年層の減少と、ベテラン技術者の高齢化が進んでいます。国土交通省の資料によると、建設業に従事する60歳以上の割合は25.7%(77.6万人)であるのに対し、29歳以下はわずか11.7%(35.3万人)にとどまっています。
このような年齢構成のアンバランスにより、2025年以降にはベテラン技術者の大量退職が予想され、技術継承が難しくなる可能性があります。人材不足は工期の遅延や品質低下につながるため、各企業は早急な対策が必要です。
建設需要の高まりと2024年問題
インフラ整備や災害復興事業の増加に伴い、建設業界の仕事量は増えています。
一方で2024年には働き方改革が本格的に施行され、時間外労働の上限規制や有給休暇の取得義務化が始まりました。
人材が不足している企業では、工期を守るために長時間労働に頼らざるを得ない状況が生じがちです。この結果、従業員の疲労蓄積による離職や新たな採用の難しさといった悪循環に陥ります。
現場管理や安全対策にも人手が必要なため、過密スケジュールから脱却できない現場もあるでしょう。
若者は本当にいない?データから見る実態
建設業界における若手人材の早期離職も大きな問題です。厚生労働省の調査では、建設業で働き始めた若手の28.6%が3年以内に離職しています。
出典:厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(平成 31 年3月卒業者)を公表します
前述のとおり29歳以下の就業者がすでに11.7%しかいない状況で、さらに早期離職が続けば、将来の担い手不足は一層深刻化します。
離職理由としては、作業がきつかったり、休みが取りづらい環境などがあります。安全で働きやすい環境が整っていなければ、新卒者や未経験者が定着することは困難です。
若手人材を確保・定着させるためには、計画的な育成システムと職場環境の改善が不可欠です。
建設業の若者離れが当たり前と言われる7つの理由
建設業界では高齢化や人材不足が深刻な問題となっています。若者が建設業界に入職しない背景には、様々な要因があります。ここでは、若者が建設業を敬遠する主な理由を7つ紹介します。
建設業の若者離れが当たり前と言われる理由
- 根強い3Kのイメージがあるから
- 労働条件の厳しさがあるから
- 雇用が不安定な印象があるから
- 建設業界の人間関係に不安があるから
- 会社が考える離職理由と若手の考えがズレているから
- 考え方が古い印象があるから
- 仕事のプレッシャーが大きい印象があるから
1つずつ見ていきましょう。
根強い3Kのイメージがあるから
建設業界には「きつい・汚い・危険」という3Kのイメージが根強く残っています。若年層はこれらのネガティブなイメージから、自分の将来を建設業で描きにくいと感じています。
3K
- きつい
- 汚い
- 危険
近年、国土交通省は新3K「給与・休暇・希望」を推進し、建設業のポジティブな側面をアピールしています。
新3K
- 給与
- 休暇
- 希望
しかし、こうした取り組みにもかかわらず、若年層の間では従来の3Kイメージが依然として強く残っています。
労働条件の厳しさがあるから
建設業界の労働条件は他産業と比較して厳しい面があります。厚生労働省の調査によると、建設業の年間出勤日数は全産業平均より12日多く、年間実労働時間も約90時間長くなっています。
また、多くの現場では4週6休(月に6日の休み)が一般的であり、これは他業種の週休2日と比べると少ないです。
このような労働環境では、若者にとって魅力的な就職先とは映りにくいでしょう。
また、夏の猛暑や冬の厳寒といった厳しい気象条件下での作業も多く、これらの要因が若者の応募を妨げたり、早期離職につながったりしています。
雇用が不安定な印象があるから
建設業界、特に職人の世界では日当制を採用している事業所が多く、天候不良で作業ができない日は収入が得られないケースがあります。これは月給制が主流の他業界と比較して、収入の安定性に欠ける印象を与えています。
また、プロジェクトごとに勤務地が変わることも多く、生活の安定性を求める若者にとっては不安要素となるでしょう。将来設計や家族計画を考える若年層には、こうした不安定さがリスクとして映るため、他業種を選択する傾向があります。
建設業界の人間関係に不安があるから
建設業界には「見て覚える」文化や厳しい指導方法が残っている職場も少なくありません。体系的な教育制度よりも、先輩の背中を見て学ぶスタイルが主流の現場では、若手が技術を習得しにくいと感じることがあります。
ポイント
また、現場ごとに強い上下関係があり、失敗に対する許容度が低い環境では、若手が心理的に負担を感じて早期離職につながるケースもあります。
同じメンバーで長期間のプロジェクトを進めることが多いため、人間関係に問題が生じた場合の逃げ場がないと感じる若者もいるでしょう。
会社が考える離職理由と若手の考えがズレているから
企業側と若手の間には、離職理由に関する認識のギャップがあります。以下の表は、企業と若者の主な認識の違いの一例です。
| 企業が想定する離職要因 | 若者が実際に敬遠する要因 |
|---|---|
| 肉体的な負担が大きい | 指導体制の不十分さ |
| 給与水準の低さ | 雇用形態の不安定さ |
| 若者の根性不足 | 遠方現場の多さ |
| 忍耐力の欠如 | 休日確保の難しさ |
例えば、企業側は給与水準の改善に注力する一方、若者は「十分な休暇」「明確なキャリアパス」「働きやすい環境」を求めています。このような認識のズレが解消されなければ、若手の定着率向上は難しいでしょう。
考え方が古い印象があるから
建設業界では、IT化やデジタル化の動きが他業界に比べて遅れていると言われています。紙ベースの図面管理やFAXでの連絡など、アナログな業務プロセスが残っている現場もあり、デジタルネイティブ世代の若者にとっては違和感を覚える環境です。
ポイント
柔軟な働き方やリモートワークなど、新しい労働スタイルへの対応も遅れがちな印象もあります。
時代の変化に合わせた環境を求める若者からは敬遠される要因となっています。
仕事のプレッシャーが大きい印象があるから
建設業は高額な工事費用と厳格な納期が求められる仕事です。一度施工した構造物は簡単に修正できないため、ミスが許されない緊張感の高い環境となっています。
ポイント
若手にとっては、この「失敗が許されない」というプレッシャーが大きな心理的負担となります。小さな現場でも、施工不良はクレームや追加コスト、工程の再調整が必要になるため、責任の重さを感じる若者は少なくありません。
こうした心理的負担を軽減する環境づくりや段階的な責任の付与が、若い人材を呼び込むために必要です。
建設業の若手を採用したり若者離れを防いだりする8つの対策

建設業界で若い人材を確保し、長く活躍してもらうためには、様々な面での対策が必要です。ここでは、若者離れを防ぐための8つの対策を紹介します。
対策
- 若手の育成方法を見直す
- 労働に見合った給与を設定する
- 労働環境の改善と働き方改革を進める
- DXによる業務効率化
- キャリアパスの明確化
- 若手人材のサポート体制を強化する
- 多様な人材を採用する
- 派遣人材も活用する
1つずつ詳しく見ていきましょう。
若手の育成方法を見直す
若手の効果的な育成には、OJT(現場研修)とOff-JT(座学研修)を組み合わせた計画的なアプローチが役立ちます。平日は現場で実務を学び、週末に基礎講座を設けるなど、理論と実践を組み合わせた研修が効果的です。
メリット
研修体制の整備を人材募集時に提示すると、若手の不安が小さくなり、応募数の増加が見込まれます。
実務と座学が連携した育成方針を明示すると、入社後の成長を具体的に思い描く新人が増える可能性があるでしょう。
ベテラン職人が作業手順を実演しながら質問を受け付ける時間を設けることで、若手は理解を深めやすくなります。また、マニュアルを整備して振り返りができる環境を用意することも有効です。
他にも、若手を育てる具体的な施策には以下のような選択肢があります。
若手を育てるための具体的な施策
- 研修カリキュラムを段階的に設定する
- 毎週1回の振り返りミーティングでOJTの進捗を可視化
- 外部講習やセミナーを実施する
- 社員が好きなときに学べるeラーニングを導入する
自社に合いそうな方法を検討してみてください。
現場が忙しい場合はe-ラーニングで育成がおすすめ
研修制度をアピールして人材を採用したい企業や、現場が忙しくOff-JT研修の時間を確保できない企業には、eラーニングの導入が効果的です。
ワット・コンサルティングの「Construction Boarding」は、建設業界専用に開発されたeラーニングシステムで、いつでもどこでも学習できる環境を提供します。
Construction Boardingの特徴
- スマートフォンやタブレットで隙間時間に学習可能
- 1コンテンツ5分程度のマイクロラーニング形式で集中力維持
- CAD操作やBIM/CIMなど専門コンテンツが充実
- 学習進捗状況をリアルタイムで管理できる機能搭載
特に建設現場では、時間外労働の制限や繁忙期に研修時間を確保するのが難しい状況があります。
Construction Boardingなら、現場の休憩時間や移動時間を活用して効率的な人材育成が可能です。
無料トライアルもあるので、まずは資料請求してみてください。
労働に見合った給与を設定する
適切な待遇は若手のモチベーション向上と人材確保に貢献します。経験や資格に応じた給与体系を設けることで、若手が将来のキャリアをイメージしやすくなります。
社内評価制度を透明化し、成果に応じた昇給が実感できる仕組みを整えることが効果的です。また、経費や売上の見える化により、賃金アップの基盤を作ることも役立ちます。
経営状況から即座に給与アップが難しい場合は、以下のような金銭面以外の待遇改善も効果的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格取得支援 | 受験料や講習費用の会社負担、勉強時間の確保 |
| 福利厚生の充実 | 社宅制度、食事補助、健康診断の充実 |
| 報奨金制度 | 業績や改善提案に応じた一時金の支給 |
| 休暇制度の拡充 | 有給休暇の取得推進、リフレッシュ休暇の導入 |
| 作業環境の改善 | 最新工具の導入、快適な現場環境の整備 |
これらの施策は直接的な給与アップよりも導入しやすく、若手社員の満足度向上にも寄与します。「将来的な給与アップを目指している」という会社の姿勢を示し、具体的な改善計画を共有することで、若手社員の理解と協力を得られることもあります。
労働環境の改善と働き方改革を進める
週休2日制や残業削減など、働き方改革の推進は若年層の応募・定着に良い影響があります。
| 項目 | 内容・導入例 |
|---|---|
| 週休2日制 | 4週6休から週休2日へ移行 |
| 残業削減 | 定時退社日を設定し、上長が率先して実践 |
| 年間休日の確保 | 年間カレンダーを公開し、連休を定期的に設定 |
例えば、週に1回でも定時退社日を設けることで、プライベートの時間を確保したい若手にとって働きやすい環境となります。休日が増えても納期を守れる体制を整えることで「休める職場」としての評価も高まるでしょう。
働き方改革を無理なく導入するためには、段階的なアプローチが効果的です。
働き方改革の導入ステップ例
- 現状分析:労働時間や休日取得状況の把握
- 目標設定:数値目標の設定(例:残業月20時間以内)
- 短期対策:すぐに実施できる取り組みの開始
- 中長期計画:段階的な改善計画の策定
- 効果測定:定期的な振り返りと改善
具体的な導入例としては以下のようなものがあります。
| 第1段階(3ヶ月目標) | ・ノー残業デーの設定 ・業務の棚卸しと効率化検討 ・勤怠管理システムの導入 |
| 第2段階(6ヶ月目標) | ・4週7〜8休の実施 ・会議時間の短縮(1時間→30分) ・書類作成の効率化(テンプレート活用) |
| 第3段階(1年目標) | ・週休2日制の本格導入 ・変形労働時間制の検討 ・年間休日カレンダーの策定と公開 |
ちなみに、建設業界の働き方改革については、2024年問題!建設業界で働き方改革が無理といわれる7つの理由にまとめています。
DXによる業務効率化
ICT施工やBIM/CIM、ドローンなどの最新技術を導入することで、業務効率化と安全性向上の両立が可能です。
| 技術 | 内容・特徴 |
|---|---|
| ICT施工 | GPSやセンサーで重機を制御し、作業の正確性を向上 |
| BIM/CIM | 3Dモデルで設計から施工管理まで一元化 |
| ドローン | 上空からの撮影で測量や点検作業を効率化 |
紙ベースの業務をデジタル化し、クラウドサービスやモバイル端末を活用することで、作業の負担軽減が図れます。デジタル化により労働時間の短縮とミスの削減が期待できるため、若手にとっても働きやすい環境となるでしょう。
DXツールの導入には費用がかかりますが、限られた予算でも効果的に始める方法があります。
コストを抑えたDX導入例
- 無料のプロジェクト管理ツールで工程管理
- スマートフォンアプリを活用した簡易測量や写真記録
- 低コストのクラウドストレージでの図面共有
- 月額制のサブスクリプションサービスの活用
- 低コストのeラーニングで研修開始
また、新しい技術導入の際は、現場の混乱を防ぐため、事前研修やサポート体制の整備が必要です。DXの導入方法については、施工管理DXで人材不足を解消!建設業の成功事例と導入5ステップに詳しくまとめています。
BIM/CIM研修はワット・コンサルティングがおすすめ
BIM/CIM技術は建設業界の生産性向上に欠かせない技術ですが、導入には専門的な知識と技術が必要です。
ワット・コンサルティングの「Construction Boarding」では、BIM/CIMに関する充実した研修コンテンツを提供しています。
Construction BoardingのBIM/CIM学習コンテンツ
- 3Dモデルによる図面の理解と活用方法
- BIM/CIMの基礎から応用までの段階的学習
- 実務に即した実践的な操作演習
- 最新のソフトウェアに対応した講座内容
Construction Boardingは、建設エンジニアのためにカスタマイズされた学習システムで、Z世代の若手技術者も取り組みやすいデザインになっています。
全11種類、ほぼ450点に及ぶ建設業界専用のマイクロラーニングコンテンツが用意されており、効率的にBIM/CIMスキルを習得できます。
助成金の対象となるeラーニングでもあるため、コスト面での負担も軽減できます。
無料トライアルがあるため、資料請求して検討してみてください。
キャリアパスの明確化
明確なキャリアパスを提示することで、若手社員は将来像を描きやすくなり、長期的な視点で働くモチベーションが高まります。キャリアパスの具体例は以下のとおりです。
こうした成長イメージを具体化すると、社員の定着率向上につながります。明確な目標設定とともに、スキルアップや資格取得のための支援制度を設けることで、若手が長期的に働きやすい環境が整います。
若手人材のサポート体制を強化する
新入社員が安心して働けるよう、質問しやすい環境と悩みを受け止める制度も重要です。効果的なサポート体制としては以下のような取り組みがあります。
例
- メンター制度:先輩社員が個別にフォロー
- 質問チャットの導入:気軽に質問できる
- メンタルサポート窓口:定期的なカウンセリングの機会
特に建設現場では体力的・精神的な負担が大きいため、充実したサポート体制が離職防止とモチベーション向上に役立ちます。
多様な人材を採用する
女性や外国人技能実習生など、多様な人材を積極的に採用することで、活気ある職場環境が実現します。
ポイント
女性が働きやすいよう休憩室や更衣室を整備したり、外国人技能実習生向けに多言語マニュアルを用意したりするなど、それぞれの特性に合わせた環境整備が重要です。
工業高校や専門学校との連携を強化し、インターンシップや現場見学会を実施することで、早い段階から建設業の魅力を若い世代に伝えられます。
多様な人材の採用・定着を進めるには、以下のような具体的な取り組みが有効です。
| 取り組み | 具体的な内容 |
|---|---|
| 女性の採用・定着に向けた取り組み | ・トイレ、更衣室、休憩室の整備 ・軽量工具や補助機器の導入 ・産休、育休制度の充実と復帰支援プログラム ・時短勤務やフレックスタイム制度の導入 ・女性技術者、管理者のロールモデル紹介 |
| 若年層向けの取り組み | ・工業高校、専門学校への出前授業 ・インターンシップの積極的な受け入れ ・現場見学会、体験会の定期開催 ・SNSを活用した情報発信 ・若手社員による採用説明会の実施 |
| 外国人材の活用 | ・多言語マニュアル、案内の整備 ・日本語学習支援 ・生活面のサポート(住居、銀行口座開設など) ・文化理解研修(日本人社員向け) ・コミュニケーションツールの活用(翻訳アプリなど) |
| シニア層の活用 | ・定年後の再雇用制度の充実 ・経験を活かした技術指導者としての役割付与 ・体力面に配慮した作業環境の整備 ・短時間勤務など柔軟な働き方の提供 |
こうした取り組みを通じて多様な人材が活躍できる環境を整えることで、人材確保と職場の活性化につながります。
派遣人材も活用する
繁忙期や急な欠員に対応するため、派遣スタッフの活用も有効な選択肢です。専門スキルを持つ派遣社員を適材適所で配置することで、正社員の負担軽減が図れます。
ポイント
契約期間が明確なため、人件費の柔軟な管理も可能です。若手正社員の負担を軽減することで、精神的な余裕が生まれ、労働環境の改善につながります。
多角的な人材活用を検討し、若手が働きやすい環境づくりを進めることが、定着率向上と生産性アップの鍵となります。
若手に建設業の魅力を伝えて応募を増やす方法

建設業の魅力を若年層に効果的に伝えるには、積極的な情報発信が欠かせません。ここでは、若手に建設業の魅力を伝える3つの方法を紹介します。
若手に建設業の魅力を伝える方法
- 自社サイトでの発信
- SNSやYouTubeを始める
- 求人票の書き方を工夫する
1つずつ詳しく見ていきましょう。
自社サイトでの発信
ホームページは企業の姿を総合的に示せる媒体です。採用情報だけでなく、現場の雰囲気や社員の活躍を見せることで、若手に具体的なイメージを持ってもらえます。
自社サイトに掲載すると効果的な項目
- 施工事例や完成写真
- 現場スタッフや社員の声
- キャリアの流れや教育制度
- 1日のスケジュールや年間行事
- 福利厚生や休暇制度の紹介
会社の実績を写真や動画で紹介すると、完成した建物やプロジェクトの価値が伝わります。新人社員のインタビューを掲載すれば、未経験から成長するイメージが具体的になるでしょう。
ポイント
定期的に更新し、ブログ形式で工事の進捗や研修の様子を公開すれば、閲覧者に新鮮な情報を提供できます。
検索エンジンから自社サイトを訪れた人が、会社の特色を理解して前向きな気持ちになる情報構成を心がけましょう。
SNSやYouTubeを始める
X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどのSNSを活用すると、デジタルネイティブ世代に情報が届きやすくなります。各プラットフォームの特性を活かした発信が効果的です。
現場のリアルな空気や作業風景を短い動画で発信すると、肉体労働だけが強調されがちなイメージを変えるきっかけになります。Xで定期的に工事の進展を報告し、Instagramで完成後の写真を共有すると、内容が重複せず多角的に伝わるでしょう。
YouTubeではベテランと新人の対談動画を公開し、新人の視点や学ぶ姿勢を映し出すと親近感が増します。投稿を行う際は、プライバシー保護や安全管理にも注意しながら、会社の魅力を継続的に発信することが大切です。
SNS運用のポイント
- 若手社員に運用を任せて新鮮な視点を取り入れる
- 定期的な投稿スケジュールを設定する(週1〜2回程度)
- コメントには必ず返信し、コミュニケーションを大切にする
求人票の書き方を工夫する
募集段階で伝える情報の質を高めると、若手の応募意欲を引き出しやすくなります。仕事内容や勤務条件が曖昧だと、早い段階で候補から外される可能性があります。
| 項目 | 書き方の例・ポイント |
|---|---|
| 仕事内容 | 道路舗装や公共施設の耐震工事など、担当現場の規模と具体的な作業内容を明示。社員インタビューから「完成後に達成感を得られる」など実感を伝える。 |
| 勤務地 | ◯◯市内の現場をメインに担当。遠方の出張は月1回程度で短期間、グループ制で移動。転勤は原則なしで生活リズムを保ちやすい。 |
| 休日・休暇 | 週休二日制で年間休日120日。現場ごとに交代制を導入し、祝日は休みやすい仕組み。 |
| 昇給・評価 | 施工管理技士の資格取得で昇給3万円、現場リーダー就任時に手当を加算。評価シートの公開で公正な査定を実施。 |
| 教育制度 | 先輩社員とマンツーマンのOJTに加え、外部セミナーも会社負担で受講。資格勉強の時間を確保するための業務調整あり。 |
| 社内の雰囲気 | 平均年齢34歳で活気がある。定期的な懇親会や社内イベントを企画し、オープンに意見交換できる場を設けている。 |
具体的な例文としては以下のように書くと、読み手に魅力が伝わりやすくなります。
求人票の例文
職種名:土木施工管理スタッフ(未経験歓迎)
仕事内容:道路や公共施設の補修工事を中心に携わります。最初の1年間は先輩社員のサポートにつき、作業の段取りや図面の見方を学ぶ時間を確保します。工事の進捗をチームで共有しながら安全管理を行い、完成後は地元の方々に感謝される場面もあります。
勤務地:◯◯市内がメインで、現場によっては月1回程度の出張があります。遠方現場には相乗りで移動し、宿泊の際は会社が手配。転勤は原則なしです。
勤務時間:8時~17時(休憩60分)、週休二日制(年間休日120日)現場によっては残業ありですが、定時退社日を週1回設けてメリハリを付けています。
給与:月給20万円〜30万円スタート(経験・資格を考慮)施工管理技士取得後は月給にプラス3万円を支給。リーダー手当や報奨金も用意しています。
昇給・賞与:年2回査定を行い、成果に応じて昇給。会社の業績により年2回の賞与を支給。評価シートを開示して透明性を重視しています。
教育制度:OJTでは先輩社員が1対1で指導し、座学研修も外部セミナーを活用。資格取得支援が整備され、受験料や講習費は会社負担としています。
福利厚生・社内イベント:社会保険完備、通勤手当(上限2万円)社員旅行は国内外を交互に開催。夏のバーベキュー大会などで他現場のメンバーとも交流します。
このように、「何をやるのか」「どれだけ成長できるか」「条件面での安心感はあるか」を言葉と数値で示すと「ここなら働きたい」と思いやすくなります。
建設業の若手採用でよくある質問
最後に、建設業の若手採用についてよくある質問に答えていきます。
若手の採用や育成に使える助成金は?
企業の負担を抑えながら新人を育てたい場合、助成金を活用すると良いでしょう。公的機関の支援を受けられるため、研修費や給与負担が軽減されます。
具体的な助成金は以下のとおりです。
出典:厚生労働省|建設業 時間外労働の上限規制わかりやすい解説
いずれも事前申請が必要で、手続きの期限や要件が細かく定められています。公式サイトの情報をよく確認して計画的に活用しましょう。
助成金を効果的に導入できれば、負担を抑えつつ教育水準を上げる道が開けます。
建設業に未来はない?
建設業界は変化に合わせて体制を整えれば、若手が活躍できる領域が広がる可能性があります。
公共インフラや民間開発の需要は一定水準を保ち、社会の基盤を支える仕事が尽きる見通しは低いです。災害復旧や老朽化した橋梁の補修など、維持管理の場面でも建設会社の役割が大きいでしょう。
ポイント
さらに、ICT施工やドローン点検、BIM/CIMを導入する企業が増えており、最新技術を駆使した新しい働き方が出現しています。
2024年問題として労働時間の上限規制が強化される動きもありますが、それを機に働き方改革を進める企業が出てくる傾向です。古いイメージを変えようとする機運も高まっているため、これからの建設業界を担う世代にとっては、挑戦できる領域がまだ多く残っています。
まとめ|建設業界の若手の人手不足が当たり前の状況に対応していこう
建設業界が直面している若手人材の確保・定着問題は、一朝一夕に解決できる課題ではありません。
しかし、この記事で紹介した対策を段階的に取り入れることで、状況を改善できる可能性があります。
建設業界の若手人材確保・定着のための8つの対策
- 若手の育成方法を見直す
- 労働に見合った給与を設定する
- 労働環境の改善と働き方改革を進める
- DXによる業務効率化
- キャリアパスの明確化
- 若手人材のサポート体制を強化する
- 多様な人材を採用する
- 派遣人材も活用する
まずは自社の課題を正確に把握し、取り組みやすい対策から実施していきましょう。
OJTとOff-JTを組み合わせた育成方法の見直しや、eラーニングの導入は比較的取り組みやすいです。
建設業におすすめの人材育成ツール
建設業の人材育成を効率的に進めるなら、ワット・コンサルティングの「Construction Boarding」がおすすめです。
いつでもどこでも学べるeラーニングで、忙しい建設現場でも人材育成が可能です。
以下に該当する企業におすすめの研修ツールです。
Construction Boardingが合う企業の特徴
- 人材育成に割く時間が確保できない
- 若手の定着率を高めたい
- 技術継承を効率的に進めたい
無料で2週間のトライアルができて、さらに助成金の対象となるeラーニングです。
「まずはお試しで始めたい」「効率的に若手を育成したい」という場合は、お気軽に資料請求してみてください。
貴社の人材確保と育成の参考になれば幸いです。