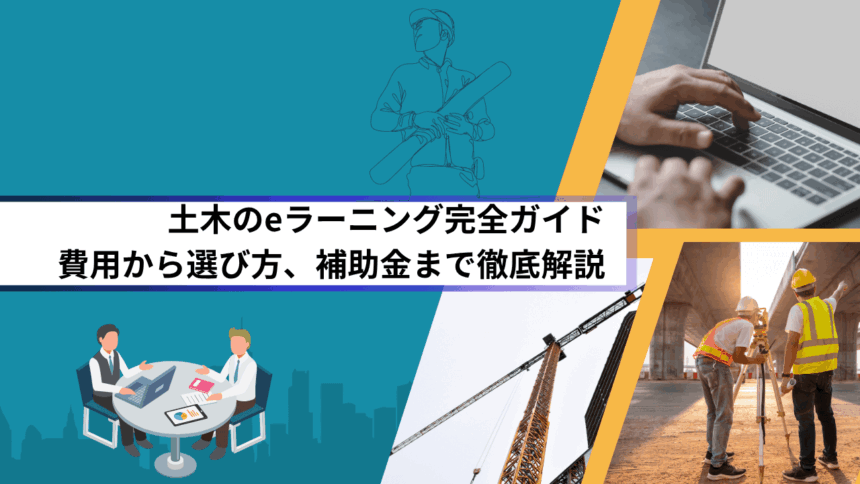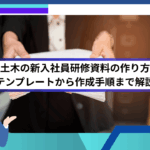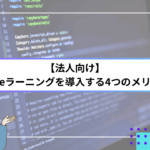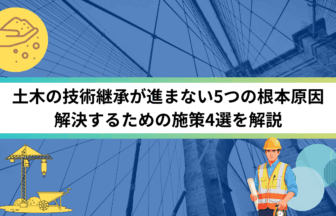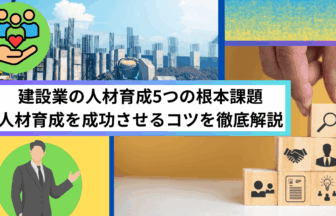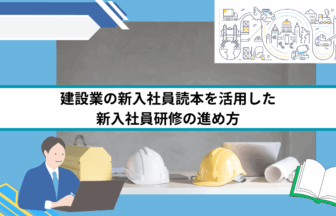「自社に合う土木のeラーニングがどれかわからない…」
「eラーニングを導入したいけど、費用や効果が気になって踏み出せない…」
「若手や技術者の育成を効率化したい…」
このような悩みを抱える、土木業界の経営者様や研修担当者様に向けた記事です。
この記事でわかること
- 土木業界でeラーニングが求められる理由
- 土木でeラーニングを導入する5つのメリット
- 土木のeラーニングサービスを選定するポイント
土木業界が抱える技術者不足や働き方改革といった課題を解決するために、eラーニングの導入は効果的です。
熟練技術者のノウハウを体系化し、時間や場所を選ばずに学習できる環境は、技術承継を促進し、若手のスキルアップと定着に貢献します。
「でも、数あるサービスの中から自社に最適なeラーニングを選ぶのは難しい…」と思いますよね?
この記事を読むことで、土木業界に特化したeラーニングの選び方や費用相場、活用できる補助金などの導入に必要な知識がすべてわかります。
貴社に最適なeラーニングを見つけ、効果的な人材育成を実現するためにも最後まで読んでみてください。
建設業におすすめのeラーニング
私たちワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」は、建設業に特化したeラーニングサービスです。
1本3分程度の短時間動画で、土木・施工管理の基礎から実践的なスキルまで、スマートフォンやPCでいつでもどこでも学習できます。
2週間の無料トライアルもございますので、まずはお気軽にお試しください。
目次
土木業界でeラーニングが求められる理由
土木業界は深刻な技術者不足や働き方改革への対応などで、多くの課題に直面しています。
これらの課題を乗り越え持続的に発展していくための有効な解決策として、eラーニングへの期待が高まっています。
eラーニングが求められる理由
- 技術者不足とCPD義務化の波
- 移動ゼロ学習とeラーニング
- BIM・ICT人材をeラーニングで育成する
eラーニングが求められる理由を、1つずつ解説します。
参考記事:【必見】建設業がeラーニングを導入すべき3つの理由と具体的メリット
技術者不足とCPD(継続的専門能力開発)義務化の波
技術者の高齢化と若手不足という課題の解決策として、eラーニングが注目されています。
国土交通省のデータによると、55歳以上の建設業就業者が約36%を占める一方、29歳以下は約12%です。
出典:国土交通省|建設業における人材確保に向けた取り組みについて
深刻な若手人材の不足により、建設業にとって技術承継が大きな課題です。
こうした状況下で、公共工事の入札で評価されるCPD(継続的専門能力開発)単位の取得は、企業の競争力を維持するために欠かせません。
| 課題 | 現状 | eラーニングによる解決策 |
|---|---|---|
| 技術者不足 | 55歳以上が約36%、29歳以下が約12%という高齢化構造 | 熟練技術者のノウハウを映像教材化し、若手へ効率的に技術を伝承する |
| CPD義務化 | 公共工事の総合評価落札方式でCPD単位が加点対象 | 現場業務の合間にスマートフォンなどで学習し、効率よく単位を取得できる |
eラーニングを活用すると多忙な業務の中でも計画的に知識を習得し、CPD対応と技術承継を両立できます。
参考記事:施工管理(現場監督)は人手不足が当たり前の3つの理由|働きやすい会社の見つけ方
移動ゼロ学習とeラーニング
現場が各地に点在する土木業界において、移動時間ゼロで学べるeラーニングは働き方改革を力強く後押しします。
集合研修の場合、研修場所への移動に多くの時間とコストがかかっていました。
特に、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制により、移動時間の削減と業務の効率化は企業にとって重要な経営課題です。
移動ゼロ学習のメリット
- コストを削減できる
- 残業を抑制できる
- 学習や別の業務に時間を使える
例えば、これまで研修のために半日を移動に使っていた従業員は、eラーニングの導入により移動する必要がなくなります。
移動時間がなくなることで学習に使える時間を増やせるのは、eラーニングの魅力です。
参考:厚生労働省|建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制
BIM/ICT人材をeラーニングで育成する
国土交通省が推進する「i-Construction」の中核をなすBIM/CIMの習得に、eラーニングは適しています。
これらの新技術は専門性が高く、社内に十分な指導者がいないケースも少なくありません。特定のソフトウェア操作などを伴うため、一度きりの研修よりも自分のペースで繰り返し学べる環境が効果的です。
eラーニングは、以下のようなBIM/ICTスキルの習得と相性が良いです。
BIM/ICTスキル
- 3Dモデリングソフトの基本操作
- ドローン測量で取得した点群データの処理
- ICT建機の操作シミュレーション
動画教材を活用することで、複雑なソフトウェアの操作手順を視覚的に理解しやすくなります。
eラーニングを通じてデジタルスキルの底上げを図ることは、企業の生産性向上と競争力強化につながります。
参考記事:施工管理DXで人材不足を解消!建設業の成功事例と導入5ステップ
土木でeラーニングを導入する5つのメリット
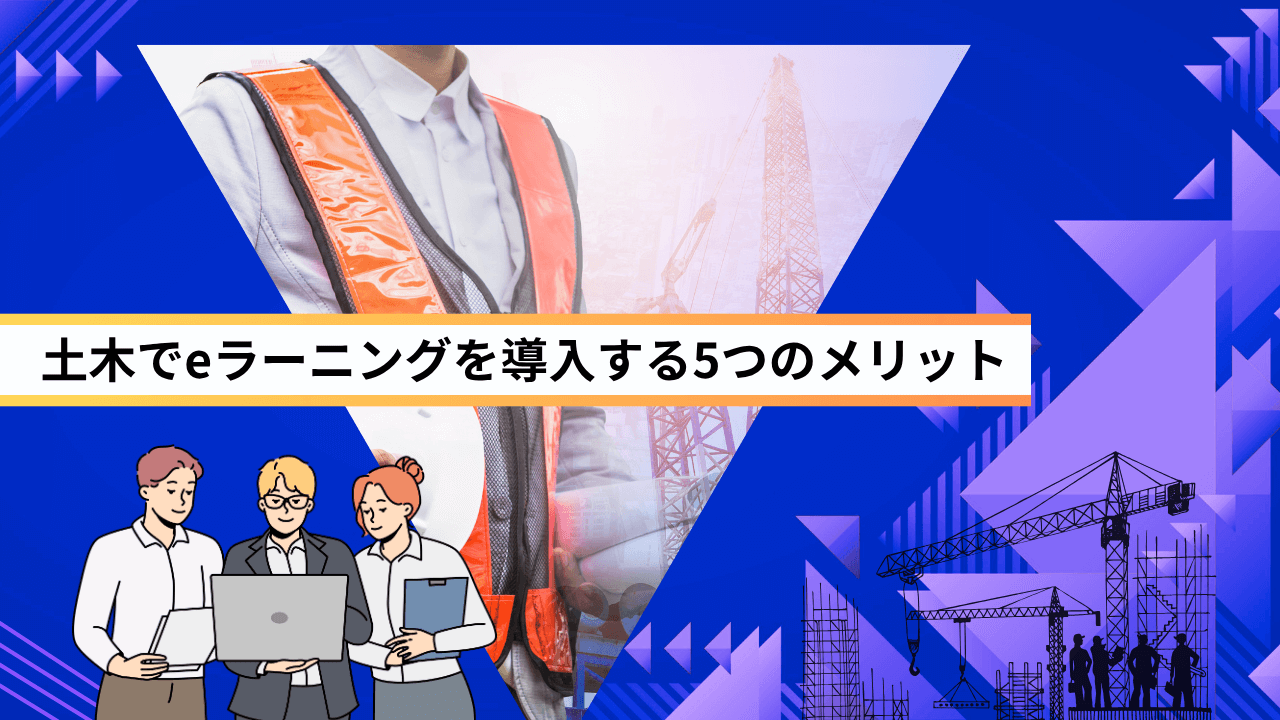
土木業界でeラーニングを導入すると、以下のように多くのメリットがあります。
eラーニングを導入するメリット
- eラーニングで反復学習定着
- CPD単位を効率取得
- 若手定着と採用ブランディング
- 学習データの可視化と評価
- 助成金活用でコスト低減
それぞれのメリットを1つずつ解説します。
eラーニングで反復学習定着
eラーニングは反復学習に適しており、知識の定着を促進します。
一度学んだ内容を記憶に定着させるには、繰り返し学習することが効果的です。
eラーニングはスマートフォンやPCがあれば時間や場所を選ばないため、従業員は自分のペースで何度も学習できます。
反復学習のメリット
- 苦手な分野を集中して学習できる
- 自分の理解度に合わせて復習できる
- 通勤中などの隙間時間を活用できる
業務でわからなかった点を休憩中に動画で再確認したり、資格試験の重要項目を何度も解き直したりできます。
eラーニングは学んだ知識を「知っている」から「できる」に変える手助けをします。
CPD単位を効率取得
eラーニングを活用すると、CPD(継続的専門能力開発)単位を効率よく取得できます。CPD単位は、公共工事の総合評価落札方式で企業の技術力を示す指標として評価されます。
ポイント
多忙な技術者が学習時間を確保して集合研修に参加することは大変ですが、eラーニングは現場業務の合間や移動時間を活用して学習を進められるため効率的です。
CPD認定を受けた講座も多く提供されており、企業の競争力維持と技術者のスキルアップを両立させる有効な手段です。
充実した教育体制は、若手社員の定着率向上と企業の魅力につながります。
若手定着と採用ブランディング
国土交通省の調査では、建設業における新卒入職者の3年目までの離職率は大卒者で約30%、高卒者で約40~50%です。
グラフを見てもわかるように、製造職よりも離職率が高い傾向にあります。
若手社員が成長を実感できる環境を整えることは、人材確保の観点から重要です。
eラーニングの導入は「人材育成に投資する企業」という前向きな姿勢の証明になります。
採用におけるアピールポイント
- 計画的にスキルアップできる
- 資格取得の支援体制が整っている
- 最新技術を学べる環境がある
採用面接や会社説明会でeラーニングの活用事例を紹介することは、他社との差別化になります。
教育制度の充実は若手が魅力を感じる条件です。
参考記事:「建設業の若者離れは当たり前?」若手採用を成功させる8つの対策
学習データの可視化と評価
eラーニングは従業員の学習状況をデータで可視化し、客観的な評価を可能にします。
従来のOJTは指導者の経験や感覚に頼ることが多く、個々のスキルを正確に把握するのは困難でした。
一方、eラーニングの学習管理システムを活用すると、データに基づいた人材育成が可能です。
可視化できる学習データ
- 講座ごとの学習進捗率
- 確認テストの点数や正誤履歴
- 総学習時間やログイン頻度
これらのデータを分析することで、個々の従業員がどの分野を苦手としているかを特定し、的確にフォローできます。
また、スキルマップの作成や適材適所の人員配置にもデータを活用可能です。
助成金活用でコスト低減
eラーニングの導入は国の補助金を活用できるため、コストを抑えられます。
特に、厚生労働省が管轄する「人材開発支援助成金」は、建設業の人材育成を支援する制度として広く知られています。
ポイント
人材開発支援助成金の「建設労働者技能実習コース」を活用すると、eラーニングの導入・運用コストの負担を軽減可能です。
申請には一定の要件がありますが、補助金を活用できると費用対効果の高い人材投資を実現できます。
導入を検討する際は、eラーニング提供事業者が補助金申請のサポートをしているか確認しましょう。
参考記事:【必見】建設業がeラーニングを導入すべき3つの理由と具体的メリット
Construction Boardingでも助成金の利用が可能
私たちワット・コンサルティングが提供するeラーニング「Construction Boarding」も、人材開発支援助成金の対象です。
コストを抑えながら質の高い研修制度を構築したい企業様はぜひ一度ご相談ください。
土木のeラーニングサービスを選定するポイント

eラーニングサービスを選ぶ際は、いくつかのポイントがあります。
自社の育成目的や予算に合ったサービスを選ぶために、以下の点を比較検討しましょう。
eラーニングサービスを選定するポイント
- 講座ラインナップとCPD認定
- 進捗管理・確認テスト機能
- モバイル・多言語対応
- カスタマイズと自社教材連携
- 料金体系とユーザー拡張性
選定ポイントを1つずつ解説します。
講座ラインナップとCPD認定
自社の育成目標に合う講座が揃っているかを確認します。
土木業界では職種や階層によって必要な知識やスキルが異なるため、講座の網羅性は重要な選定ポイントです。
特に、公共工事の入札で評価されるCPD認定講座の有無は、企業の競争力に影響します。
講座ラインナップの確認項目
- 職種別講座(施工管理・測量など)
- 階層別研修(新人、若手、管理職など)
- 専門分野の講座(BIM/CIM、i-Constructionなど)
- CPD認定講座の数と種類
自社の事業内容や人材育成計画と照らし合わせ、必要な講座が過不足なく提供されているサービスを選びましょう。
進捗管理・確認テスト機能
学習効果を高めるには、進捗管理と確認テストの機能が重要です。
管理者が従業員の学習状況を把握できないと、適切な指導やフォローはできません。
また、知識の定着度を測るために講座内容に応じた確認テスト機能も必要です。
確認すべき管理機能
- 受講者ごとの学習進捗の可視化
- テスト結果の自動採点とデータ集計
- 学習が遅れている従業員への通知機能
これらの機能が充実しているサービスを選ぶことで、eラーニングの「受けっぱなし」を防ぎ、計画的に人材育成を進められます。
モバイル・多言語対応
現場間の移動や休憩などの隙間時間を活用するためにも、スマートフォンやタブレットなどに対応しているか確認しましょう。
また、近年は外国人材の採用も増えているため、多言語対応も重要な選定ポイントです。
モバイル・多言語対応の確認点
- 各デバイスに最適化された表示か
- 専用アプリが提供されているか
- オフラインでも学習できる機能の有無
- 対応言語の種類(英語・ベトナム語など)
従業員の多様な働き方や背景に対応できる、利便性の高いサービスを選びましょう。
カスタマイズと自社教材連携
自社独自のルールやノウハウを教えたい場合、システムのカスタマイズ性や自社教材との連携機能があると便利です。
自社で作成した動画や資料を教材として登録できると、より実践的な研修ができます。
カスタマイズ・連携機能の例
- 自社マニュアル(PDF、動画)のアップロード
- 複数の講座を組み合わせたオリジナル研修コースの作成
- 自社に合わせた独自の確認テストやアンケートの作成
将来的に研修内容を変更・追加することも見越して、柔軟に運用できるサービスがおすすめです。
料金体系とユーザー拡張性
料金体系が自社の事業規模や利用計画に合うかを確認します。
料金プランはサービスによって様々ですが、月額固定費や利用ID数に応じた従量課金制が一般的です。
また、初期費用の有無や最低利用ID数も事前に確認しておきましょう。
料金体系の確認項目
- 初期費用と月額費用
- IDあたりの料金単価
- オプション機能の追加料金
- 最低契約期間や利用人数
将来の事業拡大で利用者が増える可能性を考え、ID追加のしやすさやカスタマイズの自由度なども見ておくと安心です。
無料トライアルを実施しているサービスもあるため、試しに利用して内容を確認するのもおすすめです。
「Construction Boarding」で2週間の無料トライアルが可能
ワット・コンサルティングが提供するConstruction Boardingでは、2週間の無料トライアルをご用意しています。
実際の教材や管理画面の使い勝手を、ぜひこの機会にお確かめください。
土木のeラーニング導入費用と補助金活用術
ここでは、eラーニング導入費用とコスト削減に役立つ補助金活用術を解説します。
導入費用と補助金活用術
- 導入費用の相場と回収計算
- 補助金・助成金とCPD費用補助
- 隠れコストとROI改善
- CB料金モデルと事例
1つずつ見ていきましょう。
導入費用の相場と回収計算
eラーニングの費用は、主に初期費用と月額費用で構成されます。
料金体系はサービスにより異なりますが、例えばクラウド型の場合は初期費用が〜10万円、月額費用はID数に応じた数万円からが一般的です。
導入効果を測るには、投資額に対して「どれだけコストを削減できたか」「利益はいくら増えたか」で計算します。
投資回収シミュレーションの要素
- 投資額:初期費用・月額費用・運用担当者の人件費など
- 削減コスト:集合研修の会場費・交通費・宿泊費など
- 利益向上:生産性の向上・事故防止による損失回避など
事前にシミュレーションすることで費用対効果を予測でき、導入の意思決定がしやすくなります。
投資回収の計算式は、以下のとおりです。
投資回収の計算式
回収年数 = 導入コスト ÷ (年間削減コスト + 年間増加期待利益)
例えば、導入コストが300万円、年間のコスト削減が100万円、利益の増加が200万円見込める場合、1年で投資を回収できる計算です。
補助金・助成金とCPD費用補助
eラーニングで利用できる代表的な補助金・助成金制度は、以下のとおりです。
活用できる補助金・助成金
- 人材開発支援助成金
- IT導入補助金
- 自治体の独自制度
申請には要件があるため、社会保険労務士などの専門家やeラーニング提供事業者に相談してみてください。
隠れコストとROI改善
eラーニングの費用対効果(ROI)を高めるには、見えにくい「隠れコスト」に注意が必要です。
例えば、自社教材を作成するための時間や人件費、システムを運用管理する担当者の工数がコストとして発生します。
ポイント
ROI(投資した費用に対してどれだけ利益を上げられたかを示す指標)を改善するには、これらのコストを事前に把握しておくことが重要です。
eラーニングの導入を成功させるためにも、隠れコストに注意しましょう。
Construction Boardingの料金モデルと事例
eラーニングの料金モデルは様々ですが、ここではConstruction BoardingのCB料金モデルを紹介します。
Construction Boardingは利用人数に応じて料金が変わるID課金制を採用しており、少人数からでも始めやすい点が特徴です。
ID課金制の料金モデルの特徴
- 利用人数に応じた柔軟なプラン
- 少人数からでもスタートしやすい
- 事業規模の拡大に合わせてIDを追加可能
1IDでのご契約は、個人事業主様・従業員数が140名以下の企業様・主たる事業が建設業以外の企業様が対象です。
Construction Boardingは2週間の無料トライアルがあるため、試しに利用して講義の内容や使用感を確認してみてください。
土木のeラーニング「Construction Boarding」の強み
土木業界向けのeラーニングなら、私たちワット・コンサルティングが提供するConstruction Boardingがおすすめです。
建設業界に特化した人材サービスのノウハウを凝縮し、現場の実態に即した教育を実現します。
Construction Boardingの特徴
- 土木・建設業に特化: 現場で即使える実践的な講座が豊富
- マイクロラーニング: 1本3分前後で、隙間時間に効率よく学習可能
- マルチデバイス対応: スマホやPCでいつでもどこでも学べる
- わかりやすい教材: 現場のリアルな映像やイラストで初心者も安心
- 学習管理機能: 理解度テストや進捗管理で知識の定着をサポート
- 助成金活用: 人材開発支援助成金の対象になる場合がある
OJTだけでは伝えきれない基礎知識の習得から、BIM/CIMなどの専門スキルまで幅広くカバー。
若手技術者の早期戦力化と定着率向上を力強くサポートします。
2週間の無料トライアルで、その効果を実感してみてください。
まとめ
本記事では、土木業界におけるeラーニングの重要性から導入のメリット、サービスの選び方や費用までを解説しました。
最後に、eラーニング導入を成功させるためのポイントを振り返りましょう。
土木のeラーニング導入成功のポイント
- 目的の明確化: 自社の課題に合う講座を選ぶ
- 機能の比較検討: 学習効果を高める機能を確認する
- 費用の検討: 料金体系を比較し、補助金を活用してコストを抑える
- 無料トライアルの活用: 使用感を確認してから本格導入を決定する
これらのポイントを踏まえて自社に最適なeラーニングを選び、計画的な人材育成を進めましょう。
ちなみに、土木・建設業界に特化したeラーニングならConstruction Boardingがおすすめです。
1本3分程度の動画で学べるため、多忙な現場でも隙間時間を活用して効率的に学習を進められます。
実際の現場映像やイラストを用いたわかりやすい教材で、若手の早期戦力化と定着率向上に貢献します。
人材開発支援助成金の対象となるため、コストを抑えて質の高い研修を実現可能です。
2週間の無料トライアルをご用意しておりますので、まずはお気軽に資料請求してその効果を体験してみてください。
貴社の人材育成の参考になれば幸いです。