
僕は受験できるのかな?
あと、試験はどれくらい難しいんだろう?
合格しやすい勉強方法も知りたいな。
二級建築士の受験も考えてるけど、木造建築士とどう違うの?
こういった疑問に答える記事です。
本記事でわかることは下記のとおり。
- 木造建築士の受験資格がわかる
- 木造建築士試験の難易度がわかる
- 合格しやすい勉強方法がわかる
- 二級建築士との違いがわかる
木造建築士の受験資格を紹介する記事です。
また、試験の難易度や、合格しやすい勉強方法も解説します。
正直、二級建築士も検討してる人が多いと思うので、違いも解説しますね。
あなたの資格取得の参考にどうぞ。
目次
木造建築士の受験資格【学校を卒業するのが最短】

結論、建築系の学校を卒業するのが最短コースです。
学歴も資格もないと、設計事務所などで7年以上の実務経験が必要。
しかも、設計事務所などは建築系の学校を出てない人をあまり採用しないので、学校を卒業するのが良いですね。
木造建築士試験の合格率や過去問からみる難易度

木造建築士の難易度を下記の視点でまとめました。
- 合格率
- 過去問
- 合格基準
受験の参考にどうぞ。
木造建築士の合格率からみる難易度
過去5年の木造建築士の合格率は、おおよそ下記のとおりです。
- 学科:55%前後
- 製図:60%前後
- 総合:35%前後
10人中3人は合格できるので、割と難易度は低めです。
ちなみに、二級建築士の合格率は約25%なので、二級建築士の方が難関だとわかります。
結論、木造建築士の合格率からみる難易度は低めです。
木造建築士の過去問(出題範囲)からみる難易度
結論、学科も製図もきちんと勉強すれば解ける問題です。
極端なひっかけ問題もないので、きちんと勉強すれば大丈夫。
学科試験の出題範囲は、下記のとおりです。
- 建築計画:設計に関わる問題
- 建築法規:建築基準法に関する問題
- 建築構造:木造建築の構造に関する問題
- 建築施工:工事方法に関する問題
製図試験の過去問は毎年同じで、製図を行います。
製図は、設計条件がありかなり実戦的な内容です。
具体的な過去問は、公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページに掲載されてます。
合格基準からみる難易度
木造建築士の学科試験の合格基準は、100点満点中60点以上です。
4割は間違えていいので、合格基準からみる難易度は低め。
製図試験の採点は4段階評価で行われます。
最高ランクのみ合格なので、製図試験の合格基準からみる難易度は少し高めです。
木造建築士の勉強方法【学校で対策してくれる】

木造建築士の勉強方法ですが、建築系の学校で試験対策をしてくれることがほとんど。
なので、学校の授業でしっかり勉強しましょう。
学校だと製図試験対策もしっかりしてるので、合格しやすいです。
木造建築士は独学でも合格できるのか【製図が難関】
結論、独学でも合格は可能です。
ただし、正確にいうと下記のイメージ。
- 学科:独学でも可能
- 製図:講座とかを受けた方がいいかも
製図は添削してもらわないと伸びないので、講座を受けるのがおすすめ。
SAREXなんかがおすすめです。
木造建築士の独学におすすめの参考書【講座と併用がいいかも】
おすすめの参考書は、木造建築士資格研修テキストです。
正直、受験者数が少ないので参考書は少なめ。
不安な人は講座を受講しましょう。
木造建築士と二級建築士の資格の違い【正直、二級建築士がおすすめ】

木造建築士を検討するときは、二級建築士も気になるもの。
結論、取得するなら二級建築士がおすすめです。
理由は、二級建築士の方ができる範囲が広いから。
木造建築士と二級建築士の業務範囲の違いは、下記のとおりです。
| 資格 | 業務範囲 |
| 木造建築士 | 木造で延べ床面積300㎡以下高さ13m以下軒高9m以下
2階建てまでの設計が可能 |
| 二級建築士 | 木造と木造以外で延べ床面積300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下、3階以上木造の一般建築物で延べ床面積1000㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下、3階以上木造の一般建築物で延べ床面積1000㎡以上、高さ13m以下、軒高9m以下、1階建て |
簡単にいうと、二級建築士があれば木造建築士の業務も可能です。
二級建築士を受験する人は、二級建築士の難易度!合格率や受験資格から分析してみたが参考になるかと。
試験の難易度や受験資格を解説してます。
まとめ【木造建築士の受験資格は、学校を卒業すると早い】
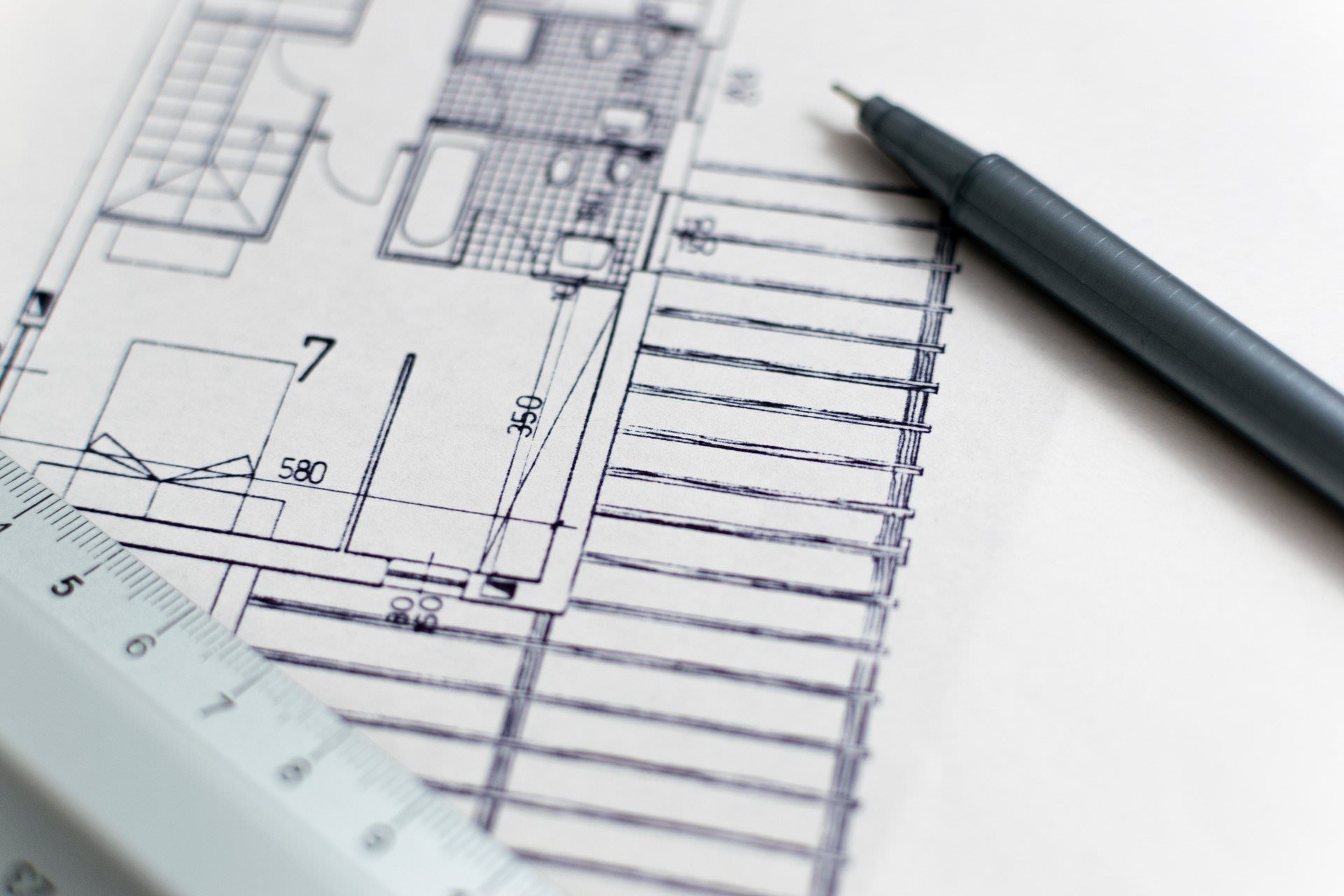
この記事をまとめます。
- 木造建築士の受験資格は、建築系の学校を卒業すると最短
- 合格率は30%台なので難易度は高くない【二級建築士の方が難しい】
- 合格基準は学科60%以上合格、製図は最高ランクで合格
- 建築系の学校で試験対策もやってくれるので、きちんと勉強すれば大丈夫
- 独学の参考書は少ないので、不安なら講座を受ける
- 正直、二級建築士を取得した方がいい【木造建築士も兼ねられるから】
木造建築士の受験を検討しているあなたの、参考になればうれしいです。
ちなみに、建築士の最高峰である一級建築士については、一級建築士試験の合格率や受験資格からみる難易度にまとめたのでどうぞ。
あなたの試験合格を祈っています!


















