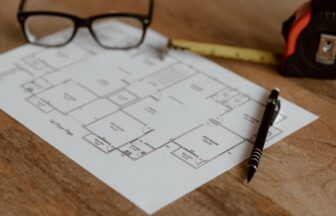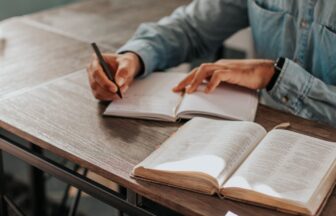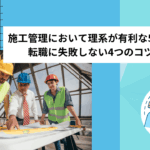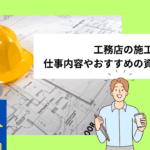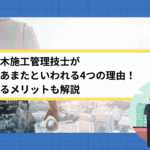一級建築士の合格率や受験資格、大学、試験内容などからみる難易度を紹介します。
一級建築士は建設業界の資格の中で最難関資格といっていいでしょう。
設計職の中でも花形の資格で、二級建築士や木造建築士に比べると可能な業務範囲が一気に広がります。
建設業界で働くうえで取得したい資格ですよね。
この記事では下記などを解説します。
- 一級建築士の合格率からみる試験の難易度
- 受験資格からみる難易度
- 試験内容からみる難易度
- 出身大学からみる難易度
- 偏差値からみる難易度
- 一級建築士の勉強時間や勉強方法
- 一級建築士と二級建築士の違い
- 他の資格との難易度比較
- 一級建築士を取得するメリット
あなたの一級建築士合格の参考になればうれしいです。
それではさっそく見ていきましょう!
目次
- 1 一級建築士試験の合格率からみる試験の難易度【学科・製図・合計で紹介】
- 2 一級建築士の受験資格からみる難易度は高い
- 3 一級建築士の過去問など試験内容からみる難易度【試験時間も紹介】
- 4 一級建築士の出身大学からみる難易度
- 5 一級建築士の偏差値からみる難易度ランキング【頭の良さはどれくらい必要?】
- 6 一級建築士の難易度は昔より上がった【試験範囲が広がっている】
- 7 一級建築士試験に合格するための勉強方法や勉強時間の目安
- 8 一級建築士と二級建築士の違い
- 9 一級建築士と他の資格の難易度比較
- 10 一級建築士を取得するメリット5選【なぜ人気なのか】
- 11 まとめ【一級建築士になるにはあきらめずに勉強するのが重要。難しいけど頑張ろう】
一級建築士試験の合格率からみる試験の難易度【学科・製図・合計で紹介】

一級建築士の合格率からみる試験の難易度をご紹介します。
一級建築士試験は学科と製図に分かれています。
学科試験を合格した人のみ製図試験を受験できます。
過去5年(平成29年〜令和3年)の学科・製図・合計の平均合格率は下記のとおりです。
- 学科:19%
- 製図:36.9%
- 合計:11.1%
結論、10人に1人くらいしか合格できない難関試験です。
一級建築士の学科試験の合格基準点【足切りの点数アリ】
一級建築士の学科試験の合格点は毎年変動します。
125点満点中、何点以上正答かで合否が決まります。
- 学科Ⅰ(計画):約11点以上/20点満点
- 学科Ⅱ(環境・設備):約11点以上/20点満点
- 学科Ⅲ(法規):約16点以上/30点満点
- 学科Ⅳ(構造):約16点以上/30点満点
- 学科Ⅴ(施工):約13点以上/25点満点
過去5年の学科試験の合格基準点は、125点満点中90点前後です。
正答率でいうと約72%くらい必要です。
一級建築士と二級建築士・木造建築士の合格率の違い【やはり一級は難易度高い】
過去5年(平成29年〜令和3年)の一級建築士・二級建築士・木造建築士の平均合格率を見てみましょう。
| 学科 | 製図 | 合計 | |
| 一級建築士 | 19% | 36.9% | 11.1% |
| 二級建築士 | 39.9% | 51.2% | 24.4% |
| 木造建築士 | 52.9% | 68% | 36% |
一級建築士の合格率の低さがわかりますね。
ちなみに、二級建築士と木造建築士については、下記の記事にまとめてます。
一級建築士の製図試験の合格率や難易度
くりかえしですが、一級建築士の学科と製図の平均合格率(過去5年)は下記のとおり。
- 学科:19%
- 製図:36.9%
「製図は合格率が高い」「製図はカンタン?」と見えるかもしれませんが、これには理由があります。
学科の合格率が低く、製図の合格率が高い理由は下記のとおり。
- 学科は合格目的ではなく記念受験の人もいるから
- 製図の問題は試験の3ヶ月前に公表されるから
- 製図試験は学科試験の3ヶ月後なので、製図試験の勉強に集中できるから
- 学科試験に合格すると2回免除があり、製図試験の勉強に集中できるから
- 学科に合格した人だけ製図を受験できるから(学科に合格してるので基礎ができてる人が多い)
なので、製図試験の合格率が高くなる傾向です。
ただし、決して「製図試験はカンタン」という意味ではありません。
後述しますが、製図は独学が難しいので、スクールに通うなどして対策した方がいいでしょう。
一級建築士の合格まで何年もかかる人が多い【何回目で合格できる?】
一級建築士試験は難易度が高いので、1回目で合格できる人は少ないです。
試験が年1回しかないこともあり、平均的には合格まで3〜5年かかる人が多いです。
もちろん、中には10年以上かかって合格する人もいますよ。
一級建築士の一発ストレート合格率はかなり低い
結論、ストレートの合格率は7%くらい。
建築系の学校を卒業して、1回で合格できる人は一握りです。
長期戦になるので、着実に合格に向けて歩んでいきましょう。
学科試験に合格すれば、翌年と翌々年は学科試験が免除されます。
今後の一級建築士の合格率は上がる?下がる?
もちろん未来を予測できるわけではないので確かなことはいえませんが、おそらく合格率は上がると思われます。
なぜなら、一級建築士が不足しているから。
建設業界の就労者は年々減少傾向にあり、高齢化も進んでいるためさらに人材が不足する可能性があります。
国土交通省の「建設産業の現状と課題」によると、建設業界の約3割は55歳以上で、29歳以下は約1割しかいません。
2025年には47万人~93万人の建設技能労働者が不足すると試算しています。
一級建築士にも同じことがいえます。
一級建築士の約65%は50歳以上です。
ベテランの建築士が引退してしまうと、国内の建築士の数は一気に不足してしまいます。
30代以下の一級建築士は10%台しかいません。
建築士の高齢化が進み、将来的に建築士が大幅に不足することが予測できます。
一級建築士試験の受験者数はここ10年で約40%減っており、建築士の高齢化・建築士不足になっています。
また、一級建築士の求人は多く出ています。
明らかに一級建築士が足りないのです。
もしかすると今後は試験の合格率を上げて、一級建築士を増やす方向になる時代がくるかもしれませんね。
※未来を読むことはできないため、保証はできませんが。
一級建築士の受験資格からみる難易度は高い

一級建築士は誰でも受験できるわけではないので、受験資格からみる難易度は高いといえるでしょう。
受験資格は下記のとおり。
| 受験資格 | 免許登録に必要な実務経験年数 |
| 建築系の大卒 | 2年以上 |
| 建築系の短大卒(3年制) | 3年以上 |
| 建築系の短大卒(2年制)、高専卒 | 4年以上 |
| 二級建築士 | 4年以上 |
| 建築設備士 | 4年以上 |
| 国土交通大臣が認めた人(外国大学の卒業者など) | 所定の年数 |
もっとも多いのは、建築系の学校を卒業した人です。
ちなみに、二級建築士と建築設備士については下記の記事のまとめてます。
改正建築士法で一級建築士は実務経験なしで受験できるようになった
ちなみに、前述のとおり一級建築士が不足している問題を解決するために、平成30年12月8日の参議院本会議で建築士法が一部改正され、実務経験がなくても建築士試験を受験できることになりました。
一級建築士の新受験資格を紹介します。
| 改正前の受験資格 | 改正後の受験資格 |
| 大学で指定科目を卒業して実務経験が2年以上 | 大学で指定科目を卒業年に受験できる。合格後、実務経験を2年以上積めば免許登録。 |
| 3年制短大で指定科目を卒業して実務経験が3年以上 | 短大で指定科目を卒業年に受験できる。合格後、実務経験を3年以上積めば免許登録。 |
| 2年制短大か高専で指定科目を卒業して実務経験が4年以上 | 短大か高専を指定科目を卒業年に受験できる。合格後、実務経験を4年以上積めば免許登録。 |
| 二級建築士として実務経験が4年以上 | すぐに受験可能。合格後、実務経験を4年以上積めば免許登録。 |
大学卒業後に一級建築士を取得するパターンは4つです。
- 大学卒業⇒試験合格⇒実務経験2年⇒免許登録
- 大学卒業⇒実務経験2年⇒試験合格⇒免許登録
- 大学卒業⇒実務経験1年⇒試験合格⇒実務経験1年⇒免許登録
- 大学卒業⇒大学院に在学中に試験合格⇒実務経験2年⇒免許登録
③のパターンからわかるとおり、受験前に実務経験がある人は、その実務経験も免許登録に必要な実務経験年数に含むことができます。
また、④のパターンのように大学院在学中に試験に合格することもできます。
一級建築士の受験資格改正については、改正建築士法の建築士試験の新受験資格!実務経験なしで受験できる?を参考にどうぞ。
一級建築士の過去問など試験内容からみる難易度【試験時間も紹介】
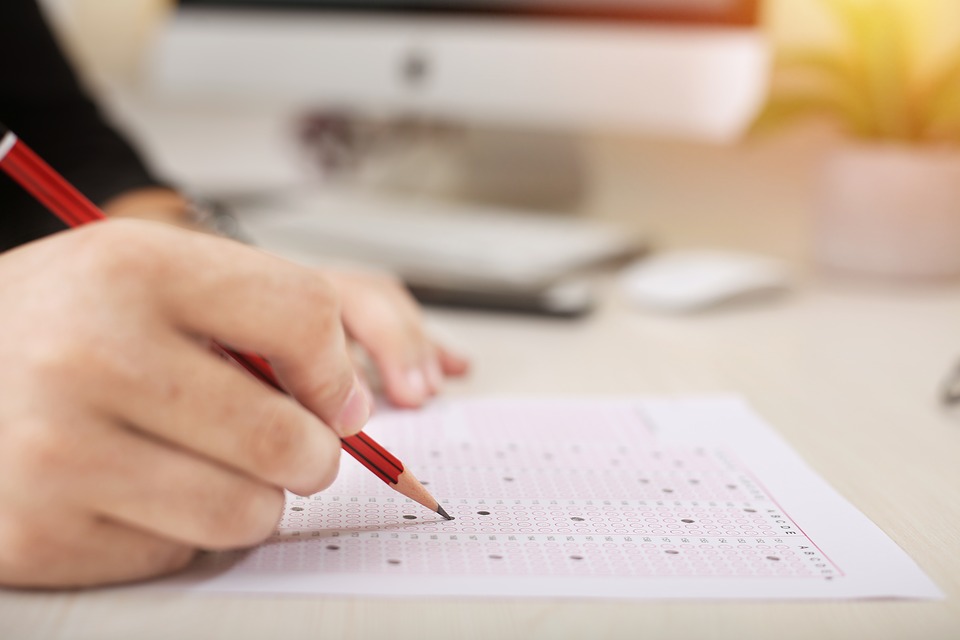
一級建築士の過去問など試験内容を見ていきましょう。
学科試験と製図試験の内容をそれぞれ解説します。
※試験時間も紹介しますね。
学科の試験内容
学科は四肢択一式のマークシート試験です。
試験範囲・出題数・試験時間は下記のとおり。
| 試験範囲 | 出題数 | 試験時間 |
| 学科Ⅰ(計画) | 20問 | 学科Ⅱと併せて2時間 |
| 学科Ⅱ(環境・設備) | 20問 | 学科Ⅰと併せて2時間 |
| 学科Ⅲ(法規) | 30問 | 1時間45分 |
| 学科Ⅳ(構造) | 30問 | 学科Ⅴと併せて2時間45分 |
| 学科Ⅴ(施工) | 25問 | 学科Ⅳと併せて2時間45分 |
学科試験の問題は下記のとおりです。
| 学科Ⅰ(計画) |
暗記系の問題が多い |
| 学科Ⅱ(環境・設備) |
計算問題あり |
| 学科Ⅲ(法規) | 建築基準法、建築士法、高齢者円滑法、耐震改修法、都市計画法、消防法、建築物省エネ法、建設リサイクル法など法令集を試験会場にもちこめる(どこに何が書いてあるか把握しておく) |
| 学科Ⅳ(構造) |
改修・耐震診断、非構造部材の耐震性なども出題される |
| 学科Ⅴ(施工) | 施工計画・現場管理、地業、建築工事、改修工事、契約など |
学科試験は4択で「最も不適当なものはどれか」という問いが多いです。
明らかに違うものを消去法で削っていきましょう。
例えば、下記のような問題が出題されます。
- 伝統的な木造建築の屋根の記述で不適当なものを4つから選ぶ
- 給水設備の記述で不適当なものを4つから選ぶ
- 建築基準法の記述で不適当なものを4つから選ぶ
- 土質や地盤の記述で不適当なものを4つから選ぶ
以前は過去問をくりかえし勉強すれば合格できましたが、近年は過去問だけでは合格できません。
過去問中心の勉強方法だと基礎的なことや理論を理解できないことが多く、基礎的な理論がわからないと解けない問題に対応できません。
近年は過去問の使いまわしではなく新しい問題が増えています。
過去問集だけでなく、テキスト・参考書を勉強するのもお忘れなく。
※もちろん、過去問をおろそかにしていいという意味ではありませんが。
過去問は過去5年分、できれば過去7年分をくりかえし解きましょう。
また、法規は法令集を試験会場にもちこめますが、しっかり勉強してください。
特に「法令集のどこに何が書いてあるか」を把握してないと、調べるのに時間がかかりすぎます。
製図試験の試験内容
製図試験は、1課題の設計を行います。
設計条件などが決められており、実際に図面に手書きで製図します。
※試験時間は6時間30分。
製図では、下記のポイントを見られます。
- 空間構成
- 建築計画
- 構造計画
- 設備計画
そして、製図した内容は下記の4ランクで採点されます。
- ランクⅠ:知識及び技能を有するもの
- ランクⅡ:知識及び技能が不足しているもの
- ランクⅢ:知識及び技能が著しく不足しているもの
- ランクⅣ:設計条件および要求図書に対する重大な不適合に該当するもの
ランクⅠに該当すると合格です。
製図試験は、学科試験の前日に公表されます。
公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページに過去3年分の製図試験の過去問が掲載されているので、イメージをつかむためにも見てみてください。
【ちなみに】一級建築士の試験のスケジュール
試験のおおまかなスケジュールは下記のとおりです。
- 4月ころ:願書申込(受験料17000円)
- 7月ころ:学科試験の前日に製図試験の問題発表
- 7月ころ:学科試験
- 9月ころ:学科試験の合格発表
- 10月ころ:製図試験
- 12月ころ:製図試験の合格発表
少々やっかいなのが、学科試験と学科試験の合格発表の間があることです。
明らかに不合格の場合は翌年の学科試験の勉強に取りかかれますが「合格か不合格か微妙」という場合は、合否がわからないまま10月の製図試験対策をしなければいけません。
学科試験では後で自己採点できるようにしておきましょう。
学科試験の前日に製図試験の問題が公表されるため、製図試験の対策は学科試験が終わったあとで大丈夫です。
学科試験までは製図試験のことは気にせず、学科試験の勉強だけに集中しましょう。
学科試験の免除制度
学科試験に合格した人は、その翌年から4年間のうち任意の2回は学科試験が免除されます。
理想的には、学科試験に合格した翌々年までに製図試験に合格したいところ。
- 1年目:学科試験に合格
- 2〜3年目:製図試験に合格
3年目までに製図試験に合格できないと、また学科試験を受け直しです。
一級建築士の出身大学からみる難易度

前述のとおり、大学卒業年に一級建築士試験を受験できるようになるため、大学はある程度関係してくるでしょう。
※もちろん、試験合格後に実務経験を積まなければ一級建築士の免許はもらえませんが。
合格者数は大学の規模にも関係しています。
受験者が多い大学ほど、合格者も多いです。
一級建築士の合格者数が多い大学TOP10は下記のとおり。
- 日本大学
- 東京理科大学
- 芝浦工業大学
- 近畿大学
- 早稲田大学
- 明治大学
- 千葉大学
- 工学院大学
- 京都工芸繊維大学
- 京都大学
一級建築士は有名大学にいかなくても合格できますが、数字で見ると有名大学出身者の合格が多くなっています。
有名大学出身者はゼネコンに就職する人も多く、二級建築士よりは一級建築士が必要な人も多く受験者・合格者が多くなっています。
大手ゼネコンに就職する人は、二級建築士を受けずに一級建築士から受験する人も珍しくありません。
前述のとおり、今後は実務経験の前に受験することになるため、高校生は進学する大学の参考にしてください。
一級建築士の合格者数が多い大学については、建築学科が強い大学をまとめてみた【夢を叶えるために情報収集】にまとめてます。
一級建築士の偏差値からみる難易度ランキング【頭の良さはどれくらい必要?】
他の資格試験との偏差値を比較すると下記のとおりです。
| 資格 | 偏差値 | 合格率 |
| 医師 | 75 | 約91% |
| 税理士 | 68 | 約18% |
| 弁護士 | 66 | 約33% |
| 一級建築士 | 66 | 約11% |
| 公認会計士 | 65 | 約10% |
| 1級建築施工管理技士 | 57 | 約19% |
| 建築設備士 | 55 | 約32% |
一級建築士は、税理士・弁護士・公認会計士などの士業試験に比べると難易度は低くなっています。
※医師免許の試験の合格率が高い理由は、確認試験だから。
一級建築士の難易度は昔より上がった【試験範囲が広がっている】
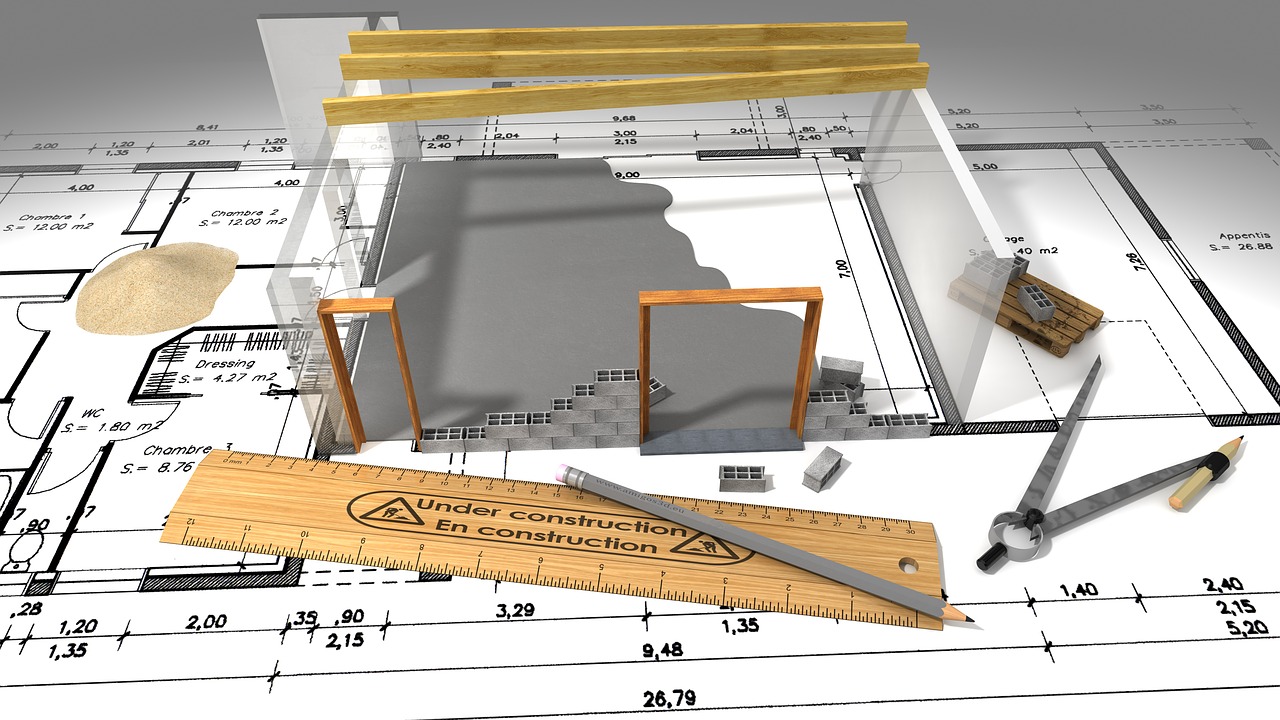
一級建築士試験でよく話題に上がるのが「2005年の耐震偽装の姉歯事件をきっかけに一級建築士試験が難しくなったか?」です。
2005年の耐震偽装の姉歯事件があったことを受けて、2009年から一級建築士試験の内容が大きく変わっています。
| 旧試験 | 現行の試験 | |
| 学科の科目数 | 4科目 | 5科目 |
| 学科の出題数 | 100問 | 125問 |
| 学科の選択肢 | 5択 | 4択 |
| 合格基準 | 60~67点くらい | 90点くらい |
| 合格に必要な正答率 | 60~67%くらい | 90%くらい |
| 出題範囲 | ー | バリアフリー法などが追加 |
合格基準と合格に必要な正答率は上がっているため、たしかに試験の難易度は上がったのかもしれませんね。
バリアフリー法など、試験範囲も広がっている傾向です。
一級建築士試験に合格するための勉強方法や勉強時間の目安
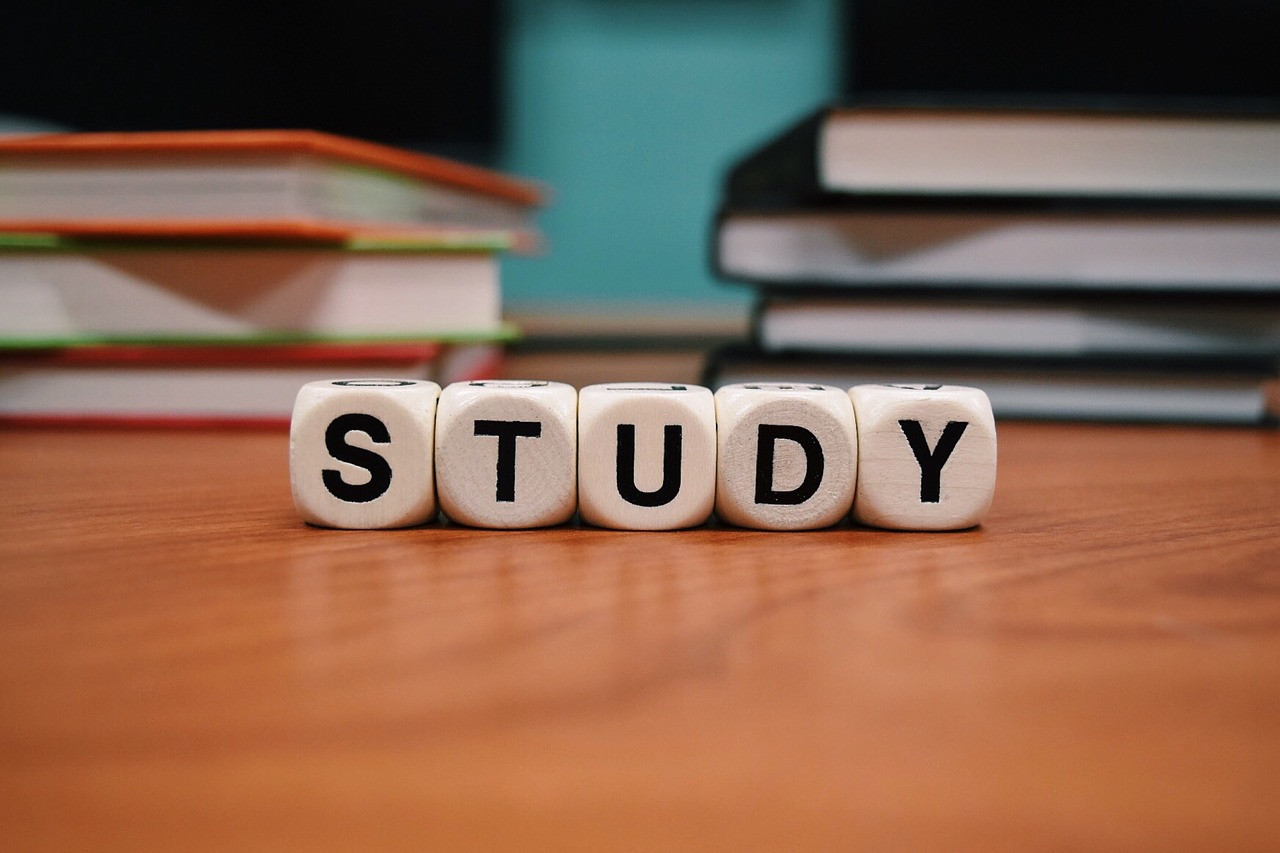
一級建築士試験に合格するための勉強方法や勉強時間を紹介します。
前述のとおり、一級建築士の学科試験は独学可能ですが、製図試験は学校に通わないと合格は難しいです。
もちろん学科試験の勉強で学校に通えるなら通っても良いと思います。
学校に通うメリットは「一級建築士合格のプロ講師に教えてもらうことで勉強時間を短縮して効率的に合格できること」だからです。
ただし注意点は、学校に通う時間がかかる場合は独学を検討しましょう。
学校に行く時間が片道1時間半であれば往復3時間ということです。
移動で3時間使うなら、自宅で3時間勉強する方が良いと思います。
製図試験の対策は学校に通うのが必須ですが、学科試験の勉強で学校に通うかどうかは、下記などで総合的に判断してください。
- 費用
- 仕事をしながら受験する人は学校に行く時間があるか
- 自宅から学校への通学時間
一級建築士に合格するために必要な勉強時間【いつから勉強を始めるべきか?】
一級建築士に合格するために必要な勉強時間は、1000~1500時間といわれています。
もし1年前から勉強を始めた場合、1日3〜4時間ほど勉強が必要です。
一般的な勉強期間は6ヶ月~1年。
できれば、1年前(7月頃)から勉強を始めましょう。
1年目で学科、2年目で製図の合格を目指すのもアリ
一級建築士試験の難易度は高いので、1年目は学科、2年目は製図に集中するのもアリです。
前述のとおり学科試験の免除制度もあるので、有効活用しましょう。
学科試験終了後、製図試験までの期間は3ヶ月です。
なかなか勉強時間をとれない人は3ヶ月だと製図合格が難しいかもしれないので、割り切って翌年の製図試験に向けて1年準備するのも立派な作戦です。
【勉強のコツ①】疲れ切る前に休憩をとる
勉強は時間の長さよりも質が大切です。
集中していない状態で1時間勉強するよりも、集中して30分勉強する方がはるかに効率的です。
特に学科試験は暗記問題が多いため、集中力が低下した状態で勉強しても頭に入らなければ意味がありません。
質の良い勉強を長時間続けるコツは、勉強に疲れ切る前に休憩することです。
疲れ切ってから休憩すると、復活するまでに3時間も4時間もかかります。
「もうちょっと勉強を続けられるかな」というところで休憩しましょう。
そうすると短時間で復活できます。
上手な人は「30分勉強したら休憩」「45分勉強したら休憩」というように勉強する時間を区切っています。
30分や45分など時間がきたら音が出るタイマーを設定して、音がなったら強制的に15分休憩するなども有効です。
こまめに休憩する方が、集中力が高い状態を長時間維持できます。
【勉強のコツ②】眠いときは15分寝る
どうしても眠い場合は15分睡眠がおすすめです。
ウトウトしながら勉強すると暗記できないので、寝たほうが良いです。
ただし、2時間や3時間寝てしまうと大切な勉強時間が大幅に削られてしまいます。
また、長時間の睡眠はかえって疲れてしまいます。
頭も寝ている状態なので、起きてから勉強できる状態になるまでにさらに時間がかかります。
15分睡眠は想像以上に頭がスッキリして、集中力を高めることができます。
【勉強のコツ③】電車通勤の人はアプリで勉強
電車通勤している人は通勤時間も勉強に有効に使いましょう。
立って電車に乗っている場合や満員電車だと、なかなか本を開いて勉強できないですよね。
今は一級建築士の勉強向けにアプリがあるため便利です。
無料アプリもあるため、まずは気軽にダウンロードしてみましょう。
アプリであれば片手で指一本で勉強できるので、電車通勤に向いています。
特におすすめのアプリは下記のとおり。
【勉強のコツ④】構造計算と法規から勉強する
理由は、配点が大きいから。
特に法規は得点稼ぎができるので、最新に勉強することをおすすめします。
独学で学科試験の勉強するならテキスト・参考書と過去問集を両方勉強する
前述のとおり、近年の学科試験は過去問の勉強だけでは合格できません。
過去に出題されたことがないような、新しい問題が多くなっているからです。
独学で勉強するなら過去問だけでなく、テキスト・参考書で基礎を勉強しましょう。
テキスト・参考書で基礎を勉強しておけば、過去問にない問題でも基礎知識から応用して問題を解くことができます。
勉強するときは知的探求心を大切にしましょう。
テキスト・参考書に書いてある基礎から「こういう場合はどうなんだろう?」と興味・疑問を持つことが重要です。
興味・疑問をもったことは調べて知識を深めましょう。
過去問中心で勉強している人はこうした応用問題が解けないため、ライバルに差をつけることができます。
学科試験の勉強の流れは下記がおすすめ。
- まずはテススト・参考書を読む
- 過去問をくりかえす(過去5年~7年分)
- 過去問を解いていてわからないところは教科書に戻って再度勉強
- 教科書で興味・疑問をもったところを自分で調べながら勉強
- 試験が近づいたら過去問を繰り返して問題と答えを覚える
過去問はみんなが勉強することなので、過去問できちんと点数をかせげるようにしておくことも大切です。
一級建築士合格におすすめの学校
一級建築士合格におすすめの学校は下記などです。
- 日建学院
- 総合資格学院
前述のとおり学科試験は独学でも合格できますが、製図試験は学校に行かないと合格できません。
製図試験の合格者のほとんどが日建学院と総合資格学院だと思って良いでしょう。
一級建築士試験合格のノウハウが多くたまっているため、合格するためのコツをわかりやすく教えてくれます。
もちろん費用がかかりますが、学科試験に合格したら製図試験で落ちたくないですよね。
費用に余裕がある人は学科試験対策も日建学院や総合資格学院を検討してください。
過去問から今年出題される問題の予測も素晴らしいです。
学校に通うメリットは下記の2つでしょう。
- 独学より多くの費用がかかるため合格しないともったいない
- ライバルがいるため競争原理がはたらき点数が伸びる
①も②も独学にはないメリットです。
独学よりもストレス・プレッシャーがかかりますが、合格率は高くなります。
一級建築士の勉強はモチベーションの維持が重要
一級建築士の試験勉強は長期戦なので、モチベーションの維持が重要です。
人によっては5年以上かけて資格を取得するので、モチベーションが下がりがち。
「なぜ一級建築士になりたいと思ったのか?」を紙に書いて、目につくところに貼っておくのをおすすめします。
どうしても勉強がキツいときは休んでもいいので、モチベーションが切れないように注意しましょう。
一級建築士にどうしても合格したい人へ
本気で一級建築士に合格したい人は「できる理由」を考えるものです。
- 仕事が忙しいから、どうやって勉強時間を作るか?
- 勉強する時間がないから、どこか削れる時間はないか?
場合によっては、一級建築士に合格するに、一時的に何かを捨てなければいけないかもしれません。
飲みに行く回数を減らしたり、休日にゆっくり休む日を減らしたり、何かを捨てないと一級建築士資格は手に入らないかも。
最後まであきらめずに「合格するまで続けた人」が一級建築士に合格する人です。
勉強すれば合格できる資格なので、あきらめずに合格を目指しましょう。
一級建築士と二級建築士の違い

下記の項目で一級建築士と二級建築士の違いを解説していきます。
- 年収
- 就職先
- 業務範囲
- 試験内容
- 受験資格
- 勉強時間
一級建築士と二級建築士の年収の違い
あくまで平均値ですが、一級建築士と二級建築士の年収の違いは下記のとおり。
- 一級建築士:642万円くらい
- 二級建築士:500万円くらい
一級建築士の方が年収が高いです。
後述しますが、一級建築士は大手に就職しやすいため、年収も高くなりがちです。
ちなみに、資格手当の相場は下記のとおりです。
- 一級建築士:約1万円/月
- 二級建築士:5000~8000円/月
ちなみに、一級建築士の月給とボーナスは下記の内訳はこんな感じです。
- 平均月給:423,400円
- 平均ボーナス:1,345,200円
勤務する企業の規模で給料は変わります。
| 企業規模 | 平均月給 | 平均ボーナス | 平均年収 |
| 10~99人 | 41万円 | 105万円 | 591万円 |
| 100~999人 | 42万円 | 135万円 | 640万円 |
| 1000人以上 | 48万円 | 222万円 | 800万円 |
1000人以上のゼネコン・スーパーゼネコンともなると平均年収800万円になります。
前述のとおり一級建築士が不足しているため、今後はさらに年収が上がるかもしれません。
参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
一級建築士の年収のついては、一級建築士の年収や給料!収入を上げる方法は?にまとめてます。
一級建築士と二級建築士の就職先の違い
就職先のイメージは下記のとおりです。
- 一級建築士:ゼネコン、大手ハウスメーカー、有名設計事務所、公務員など
- 二級建築士:中小の建設会社、工務店など
一般的には、一級建築士の方が大手に就職しやすいです。
後述しますが、一級建築士の方が大きい建物を設計できるので、大規模な設計を行う大手に就職できるイメージです。
一級建築士と二級建築士の業務範囲の違い【何ができるか知っておこう】
設計できる業務範囲の違いは下記のとおりです。
※木造建築士も併せて紹介します。
| 一級建築士 | すべての建築物の設計が可能 |
| 二級建築士 |
|
| 木造建築士 |
|
一級建築士はすべての設計ができるので、需要が大きいです。
ちなみに、一級建築士の仕事内容は、一級建築士の仕事内容を解説【将来、建築士として活躍するために】に詳しくまとめてます。
一級建築士と二級建築士の試験内容の違い
一級建築士と二級建築士の試験内容の違いは下記のとおりです。
※木造建築士も併せて紹介します。
| 一級建築士 | 学科:マークシート、四肢択一式
設計製図 |
| 二級建築士 | 学科:マークシート、五肢択一式
設計製図 |
| 木造建築士 | 学科:マークシート、五肢択一式
設計製図 |
一級建築士の学科試験のみ「四肢択一式」です。※二級と木造は五肢択一式。
ですが、試験範囲や難易度は一級建築士が上です。
一級建築士と二級建築士の受験資格の違い
受験資格の違いは下記のとおりです。※木造建築士も併せて紹介します。
| 受験資格 | 免許登録に必要な実務経験年数 | |
| 一級建築士 |
|
|
| 二級建築士木造建築士 |
|
|
受験資格のハードルは一級・二級・木造ともに低いですが、免許登録に必要な実務経験年数は一級建築士のハードルが高いです。
また、二級と木造の免許は都道府県から、一級は国土交通省から発行されます。
一級建築士と二級建築士の勉強時間の違い
試験の1年前から勉強を始めた場合の「勉強時間の目安」は下記のとおりです。
※木造建築士も併せて紹介します。
| 資格 | 勉強時間 | 1日の勉強時間 |
| 一級建築士 | 1000~1500時間 | 3~4時間 |
| 二級建築士 | 500~1000時間 | 2~3時間 |
| 木造建築士 | 300~400時間 | 1時間 |
二級建築士と木造建築士については、下記の記事にまとめてます。
一級建築士と他の資格の難易度比較

一級建築士と比較される資格の難易度比較を紹介します。
一級建築士資格は国内のあらゆる資格の中でも難しい方で、建設系資格の中ではトップクラスの難易度です。
「受験する順番」などの参考にしてみてください。
一級建築士と1級土木施工管理技士を比較すると一級建築士の方が難易度が高い
一級建築士と1級土木施工管理技士を比較すると、一級建築士の方が難易度が高いです。
理由は出題範囲です。
1級土木施工管理技士は土木のことが出題されますが、一級建築士は計画・環境・設備・法規・構造・施工と出題範囲が広いです。
より広い範囲の勉強が必要になる分、一級建築士の方が難易度が高いです。
難易度のイメージですが、1級土木施工管理技士と近い難易度は二級建築士です。
一級建築士はさらに難易度が高いです。
1級土木施工管理技士の難易度をくわしく知りたい場合は、1級土木施工管理技士の合格率や過去問から見る難易度を参考にどうぞ。
一級建築士と1級建築施工管理技士を比較すると一級建築士の方が難易度が高い
一級建築士と1級建築施工管理技士を比較すると、一級建築士の方が難易度が高いです。
一級建築士は製図試験があることと、1級建築施工管理技士よりも受験資格のハードルが高いです。
ちなみに、建設業界での評価も一級建築士の方が高いです。
「1級建築施工管理技士に合格した」というよりも「一級建築士に合格した」という方がすごい!と評価されます。
1級建築施工管理技士の難易度をくわしく知りたい場合は、1級建築施工管理技士の合格率や過去問や受験資格から見る難易度を参考にどうぞ。
一級建築士と第三種電気主任技術者(電検三種)を比較すると一級建築士の方が難易度が高い
一級建築士と第三種電気主任技術者(電検三種)を比較すると、一級建築士の方が難易度が高いです。
理由は受験資格です。
第三種電気主任技術者は合格率が低いですが、受験資格は「誰でも受験できる」です。
一級建築士の方が受験資格からみて難易度が高いといえるでしょう。
ただし、第三種電気主任技術者の合格率は10%くらいなので、一級建築士と同じくらいの合格率です。
第三種電気主任技術者の試験問題はかなり難しいので有名。
電気主任技術者の試験の難易度は、電気主任技術者・電験試験の難易度や年収!三種二種一種のコツにまとめています。
一級建築士と技術士を比較すると技術士の方が難易度が高い
一級建築士と技術士を比較すると、技術士の方が難易度が高いです。
技術士の合格率は4%台、一級建築士の合格率は11%台なので、合格率からみて技術士の方が難易度が高いです。
技術士の詳細は、建設部門の技術士の合格率や難易度【おすすめの勉強方法も紹介します】にまとめてます。
一級建築士と建築設備士を比較すると圧倒的に一級建築士の方が難易度が高い
一級建築士と建築設備士を比較すると、圧倒的に一級建築士の方が難易度が高いです。
建築設備士の合格率は50%台です。
一級建築士の合格率10%台とは大きな違いですね。
ちなみに、建築設備士の試験の難易度については、建築設備士の受験資格や試験の難易度!独学でも合格できるのか?にまとめています。
一級建築士を取得するメリット5選【なぜ人気なのか】
一級建築士を取得するメリットは下記のとおりです。
- 希少な人材になれる
- キャリアアップできる
- 業務の幅が広がる
- 構造設計一級建築士や設備設計一級建築士を目指せる
- 独立できる
1つずつ解説します。
【メリット①】希少な人材になれる【一級建築士は人数が少ない】
一級建築士は希少です。
- 一級建築士:約37万人
- 二級建築士:約77万人
- 建設業就業者数:約503万人
設計は建築士しかできず、すべての設計ができるのは一級建築士だけです。
転職するときもひっぱりだこになるので、手に職がついて食いっぱぐれもないでしょう。
【メリット②】キャリアアップできる
一級建築士を取得すると、下記のようにキャリアアップも可能です。
- 社内で昇進できる
- 大きい会社に転職できる
客観的に見てわかりやすい評価をもらえるため、キャリアアップに有益な資格です。
【メリット③】業務の幅が広がる
前述のとおり、一級建築士はすべての設計が可能です。
二級建築士や木造建築士のように設計に制限がないので、業務の幅は広がります。
より大きな設計ができる大手に転職して、さらに経験値を上げることもできるでしょう。
【メリット④】構造設計一級建築士や設備設計一級建築士を目指せる
一級建築士の先には「構造設計一級建築士」と「設備設計一級建築士」があります。
「一級建築士で5年以上の実務経験」がないと受験できないので、かなりハードルが高いです。
ですが、希少性は一級建築士より上。
- 構造設計一級建築士:約1万人
- 設備設計一級建築士:約5000人
さらに希少な人材になって活躍したい人は、いずれ目指してみましょう。
構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の詳細は、下記の記事にまとめてます。
【メリット⑤】独立できる
一級建築士には、設計事務所をつくって独立起業する人もいます。
独立できるのも大きなメリットかと。
ただし、独立起業は十分な顧客基盤がないと仕事がないので注意しましょう。
また、下記のような知識・スキルも必要です。
- 建築基準法の深い知識
- 依頼主の要望を聞き出すスキル
- 依頼主の予測を上回る技術
- 時代の流れを読む力
- センス・柔軟な思考
- グローバルな視野
「一級建築士を取得すれば成功」ではありません。
特に、独立するなら常に変化を成長を続けていく必要があります。
もちろん、資格を取得後も継続的な勉強が必要です。
この辺は、一級建築士になるだけでは勝ち組じゃない【勝てる3つの方法も解説】も参考にどうぞ。
一級建築士に向いてる人の特徴
一級建築士に向いてる人の特徴は下記のとおりです。
多く当てはまる人ほど、一級建築士に向いています。
| 向いてる人の特徴 | 理由 |
| ①注意深い人 | ミスは少ない方がいいから |
| ②体力のある人 | 忙しいときもあるから |
| ③想像力がある人 | 設計は想像する仕事だから |
| ④集中力がある人 | 設計業務は集中力が必要だから |
| ⑤責任感がある人 | 依頼主の期待に応えるため |
| ⑥ルールを守れる人 | 法律を守る仕事だから |
| ⑦常に学び続ける人 | 設計は学ぶことが多いから |
| ⑧論理的思考ができる人 | 設計は論理的に業務を進めていくから |
| ⑨プレッシャーに強い人 | 設計には納期があるから |
| ⑩逆算して行動できる人 | 納期に間に合うように仕事を進める必要があるから |
| ⑪大規模工事に魅力を感じる人 | 一級建築士は大規模プロジェクトもあるから |
| ⑫コミュニケーションスキルがある人 | 現場監督や職人さんと話す必要もあるから |
まとめ【一級建築士になるにはあきらめずに勉強するのが重要。難しいけど頑張ろう】

一級建築士は合格率が低く、受験資格のハードルも高く、難易度も高い試験です。
ですが、建設業界で上を目指すなら必ず取得しておきたい資格です。
一級建築士はきちんと勉強すれば合格できる資格です。
途中であきらめずに勉強すれば取得できる資格なので、合格するまでトライしましょう。
今後は受験資格が変わるため、合格しやすくなる可能性があります。
時代の流れに乗って一級建築士を取得しましょう。
あなたの一級建築士合格の参考になればうれしいです!