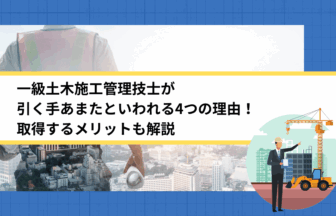平成30年12月8日の参議院本会議で建築士法が一部改正され、実務経験がなくても建築士試験を受験できることになりました。
建築士の高齢化や不足が問題になっているため、受験資格を緩和することで建築士を増やすための法改正です。
建築士試験に合格してから実務経験を積むことで免許登録できるようになります。
今回の建築士法改正の内容について、くわしく見ていきましょう(^^)
目次
建築士法改正の背景

平成30年12月8日の参議院本会議で「建築士法の一部を改正する法律案」が可決されました。
一級建築士の約65%は50歳以上です。
ベテランの建築士が引退してしまうと、国内の建築士の数は一気に不足してしまいます。
※30代以下の一級建築士は10%台しかいません。
建築士の高齢化が進み、このままいったら建築士が大幅に不足してしまいます。
2005年に社会問題になった「耐震偽装問題」をきっかけに、2008年の建築士法改正で建築士の受験資格が難しくなりました。
ところが、2008年の法改正で建築士の受験資格のハードルが上がり、建築士の受験者数が減少しています。
一級建築士試験の受験者数はここ10年で約40%減っており、建築士の高齢化・建築士不足になっています。

今回の改正は不足する建築士の数を増やすため、若い建築士を増やすために受験資格のハードルを下げる法改正です。
日本建築士事務所協会連合会、日本建築士会連合会、日本建築家協会が2018年6月の自民党建築設計議員連盟総会で建築士資格制度の改善の提案したことがきっかけになり今回の建築士法改正になり、建築士試験の内容(受験資格など)が一部改正されました。
建築士試験の改正は、
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
の試験が対象で、早ければ2020年の試験から適用される可能性があります。
建築士試験の改正内容

今回の建築士試験の改正内容は、簡単にいうと、
- 従来、受験資格に必要だった実務経験がなくても受験できる
- 試験合格後に従来の実務経験年数を積めば建築士の免許登録ができる
の2点です。
具体的な変更内容を見ていきましょう。
一級建築士の新受験資格
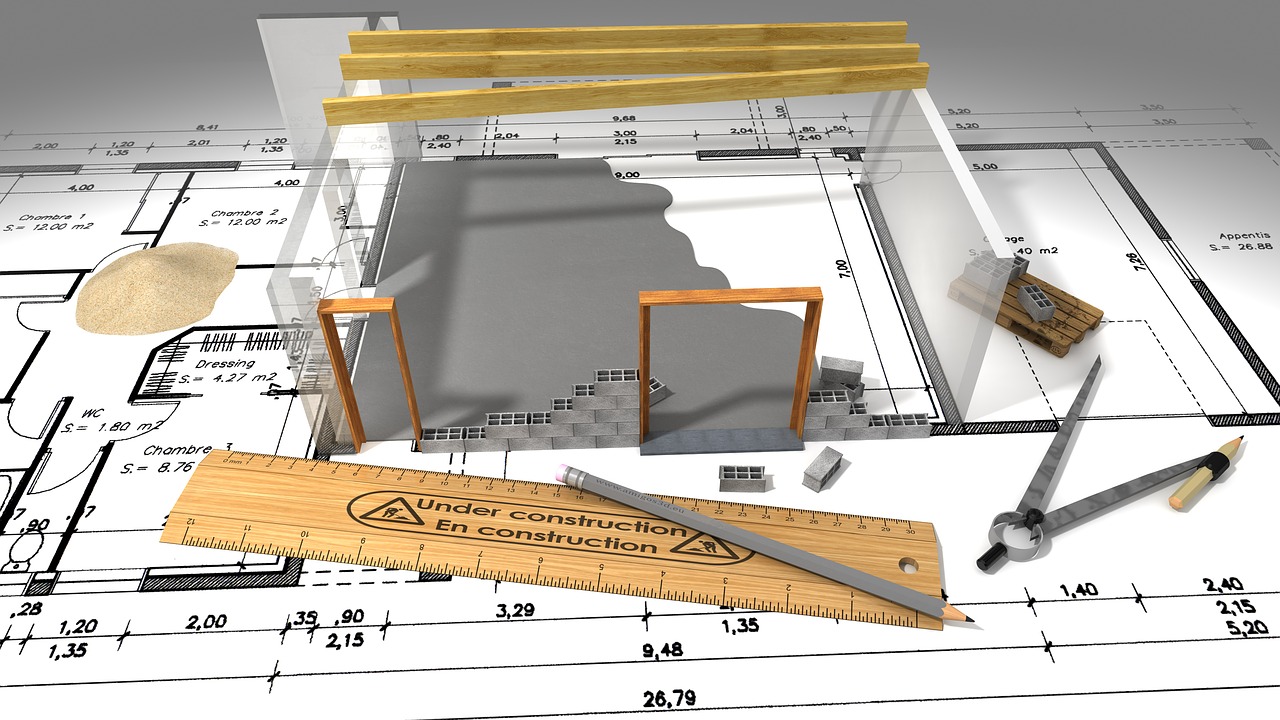
一級建築士の新受験資格をご紹介します。
| 改正前の受験資格 | 改正後の受験資格 |
| 大学で指定科目を卒業して実務経験が2年以上 | 大学で指定科目を卒業年に受験できる。合格後、実務経験を2年以上積めば免許登録。 |
| 3年制短大で指定科目を卒業して実務経験が3年以上 | 短大で指定科目を卒業年に受験できる。合格後、実務経験を3年以上積めば免許登録。 |
| 2年制短大か高専で指定科目を卒業して実務経験が4年以上 | 短大か高専を指定科目を卒業年に受験できる。合格後、実務経験を4年以上積めば免許登録。 |
| 二級建築士として実務経験が4年以上 | すぐに受験可能。合格後、実務経験を4年以上積めば免許登録。 |
大学卒業後に一級建築士を取得するパターンを4つご紹介します。
- 大学卒業⇒試験合格⇒実務経験2年⇒免許登録
- 大学卒業⇒実務経験2年⇒試験合格⇒免許登録
- 大学卒業⇒実務経験1年⇒試験合格⇒実務経験1年⇒免許登録
- 大学卒業⇒大学院に在学中に試験合格⇒実務経験2年⇒免許登録
というパターンが考えられます。
③のパターンからわかるとおり、受験前に実務経験がある人は、その実務経験も免許登録に必要な実務経験年数に含むことができます。
また、④のパターンのように大学院在学中に試験に合格することもできることになります。
二級建築士の新受験資格

二級建築士の新受験資格をご紹介します。
| 改正前の受験資格 | 改正後の受験資格 |
| 大学・短大・高専で指定科目を卒業後 | 大学・短大・高専で指定科目を卒業後(変わらず) |
| 高校・中学で指定科目を卒業して実務経験が3年以上 | 高校か中学を指定科目を卒業年に受験できる。合格後、実務経験を3年以上積めば免許登録。 |
建築士試験を受けられるタイミングを前倒しにしている改正だとわかりますね。
木造建築士の新受験資格

木造建築士の新受験資格をご紹介します。
| 改正前の受験資格 | 改正後の受験資格 |
| 大学・短大・高専で指定科目を卒業後 | 大学・短大・高専で指定科目を卒業後(変わらず) |
| 高校・中学で指定科目を卒業して実務経験が3年以上 | 高校か中学を指定科目を卒業年に受験できる。合格後、実務経験を3年以上積めば免許登録。 |
改正内容は二級建築士と同じですね。
建築士試験の改正のメリット

今回の建築士試験の改正は、受験者と設計事務所など雇用主側の両方にメリットがあります。
受験者は実務経験が後でもよくなったことで、建築士資格取得のスケジュールの自由度が高まりました。
「試験に合格してから働くか」「働いてから試験に臨むか」を選択できるメリットがあります。
設計事務所など雇用主側は、将来建築士を取得する可能性のある若い人材を確保しやすくなります。
建築士不足が問題になっているため、建築士の卵を青田刈りできるメリットがあります。
免許登録に必要な実務経験の範囲拡大?

2018年12月8日の参議院本会議の建築士法改正の段階では、免許登録に必要な実務経験の範囲がまだ決まっていません。
「実務経験が〇年必要」といっても、具体的にどんな実務経験を積めば免許登録になるかはこれから決めるということです。
「受験資格から実務経験が消える」といっても、学科試験と製図試験の両方とも実務経験が不要なのかどうかはまだ決まっていません。
完全に「受験資格から実務経験が消える」とは限らない部分があるのです。
前回2008年の建築士試験改正から10年以上経っているため、現在の情勢を踏まえた実務経験内容にすると思われます。
2008年改正で除外された実務経験が復活する可能性もあります。
建築士試験を受験しやすくする方向で、早期の具体的な改正案の作成が進められています。
今後の動向に注目ですね(^^)
まとめ

今回の建築士法改正で、多くの若者が建築士を目指しやすくなり、建築士の増加・若年齢化につながると良いですね(^^)
建築士を目指している人にはチャンスの時代といえるでしょう。
建築士資格は今後も需要がなくなることがないでしょう。
一生食っていける資格ですので、今回の法改正は自身のキャリア形成にとって追い風です。
実務経験の業務範囲がどうなるかなど、まだ未確定の部分もありますので今後の情報をチェックするようにしましょう。
試験の難易度が変わるのかも注目です。
ちなみに、一級建築士と二級建築士の試験の難易度を知りたい人は、下記の2記事を読んでみてください(^^)