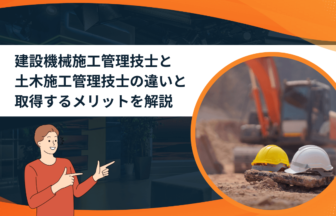合格率はどれくらい?
キャリアアップのために施工管理技士を取得したいけど、どんな種類があるんだろう?
僕には受験資格があるんだろうか?
あと、試験に合格するにはどうやって勉強すればいいの?
こういった疑問に答える記事です。
この記事でわかることは下記のとおり。
- 施工管理技士の種類
- 施工管理技士にできること
- 施工管理技士を取得するメリット
- 合格率など試験の難易度
- 施工管理技士の試験内容や出題範囲
- 各種施工管理技士の受験資格
- 施工管理技士の勉強方法
私たちワット・コンサルティングは、施工管理の転職サポートを行う会社です。
施工管理技士は施工管理職の国家資格です。
工事現場には施工管理技士を置かなければいけないと法律で決まっているため、施工管理技士の資格を持っている人は建設会社にとっては超貴重な人材といえます。
結論、施工管理技士は必ず取得しましょう。
施工管理技士が不足していることもあり、資格を保有している人は給料が高くなったり、転職が有利になるからです。
この記事では施工管理技士を取得するコツも解説するので、キャリアアップしたい人は最後まで読んでみてください!
この記事の監修者
施工管理の技術者派遣を行う会社。これまで1500名以上の未経験者を施工管理として育成した実績あり。
- 労働者派遣事業許可番号 派13-304593
- 有料職業紹介事業許可番号 13- ユ-304267
- 特定建設業 東京都知事許可 (特-1) 第150734号
目次
- 1 施工管理技士とは
- 2 施工管理技士の種類|取得するメリットは大きい
- 3 施工管理技士の1級と2級の違い
- 4 施工管理技士資格の試験の難易度|種類別
- 4.1 【基礎】第一次検定と第二次検定がある
- 4.2 1級土木施工管理技士の合格率と難易度
- 4.3 2級土木施工管理技士の合格率と難易度
- 4.4 1級建築施工管理技士の合格率と難易度
- 4.5 2級建築施工管理技士の合格率と難易度
- 4.6 1級管工事施工管理技士の合格率と難易度
- 4.7 2級管工事施工管理技士の合格率と難易度
- 4.8 1級電気工事施工管理技士の合格率と難易度
- 4.9 2級電気工事施工管理技士の合格率と難易度
- 4.10 1級造園施工管理技士の合格率と難易度
- 4.11 2級造園施工管理技士の合格率と難易度
- 4.12 1級電気通信工事施工管理技士の合格率と難易度
- 4.13 2級電気通信工事施工管理技士の合格率と難易度
- 4.14 1級建設機械施工管理技士の合格率と難易度
- 4.15 2級建設機械施工管理技士の合格率と難易度
- 4.16 施工管理技士の合格基準
- 4.17 施工管理技士試験の難易度を難しい順にランキングで紹介
- 5 施工管理技士の試験内容|出題範囲も解説
- 5.1 1級土木施工管理技士の試験内容
- 5.2 2級土木施工管理技士の試験内容
- 5.3 1級建築施工管理技士の試験内容
- 5.4 2級建築施工管理技士の試験内容
- 5.5 1級管工事施工管理技士の試験内容
- 5.6 2級管工事施工管理技士の試験内容
- 5.7 1級電気工事施工管理技士の試験内容
- 5.8 2級電気工事施工管理技士の試験内容
- 5.9 1級造園施工管理技士の試験内容
- 5.10 2級造園施工管理技士の試験内容
- 5.11 1級電気通信工事施工管理技士の試験内容
- 5.12 2級電気通信工事施工管理技士の試験内容
- 5.13 1級建設機械施工管理技士の試験内容
- 5.14 2級建設機械施工管理技士の試験内容
- 5.15 施工管理技士試験の実施機関
- 5.16 受験手数料
- 6 施工管理技士の受験資格
- 7 施工管理技士の学習ノウハウ|仕事をしながら勉強して合格に近づくコツ
- 8 施工管理技士と他の資格の難易度を比較
- 9 施工管理技士についてよくある質問
- 9.1 施工管理技士以外で施工管理技術者におすすめの建設系資格の一覧は?
- 9.2 施工管理技士以外で施工管理技術者におすすめの設備系資格の一覧は?
- 9.3 施工管理技士以外で施工管理技術者におすすめの電気系資格は?
- 9.4 一級建築施工管理技士のすごいところは?
- 9.5 2級を飛ばしていきなり1級建築施工管理技士を受験してもいい?
- 9.6 一級建築施工管理技士と一級建築士は両方取得した方がいい?
- 9.7 2級土木施工管理技士は一夜漬けでも合格できる?
- 9.8 一級土木施工管理技士のすごいところは?
- 9.9 一級土木施工管理技士の経験記述はネットや参考書を丸写ししていい?
- 9.10 2級土木施工管理技士の実務経験のごまかしは危険?
- 9.11 施工管理技士の実務経験の重複はバレる?
- 10 まとめ:施工管理技士の資格は難易度高いけど、取得すれば稼げる
施工管理技士とは

施工管理技士は、工事現場での施工管理の専門家としての知識や技術を証明する国家資格です。
資格を取得することで工事を受注できたり、年収アップしやすくなります。
施工管理の仕事内容
施工管理は建設物が予定通りに安全に完成するために、工事全体を管理監督する仕事です。
施工管理職の主な仕事内容は、下記のとおり。
- 工程管理:施主との契約に合った工事ができているか、スケジュール管理
- 安全管理:現場作業員の安全を守るための管理
- 品質管理:部材の規格や寸法の管理、建設物の品質の管理
- 原価管理:工事の原価計算をして利益を管理
- 出来形管理:施主の希望する規格基準に限りなく近い精度で完成させるための管理
- 行政への申請
施工管理は工事全体の管理監督を行う仕事であり、下記のような存在です。
- スポーツチームの監督
- 料理場の料理長・コック長
工事現場では必ず計画どおりにいかない事態が起きます。
あらゆる仕事で使われている「PCDAサイクル」が施工管理にも大切です。
下記の繰り返しで、施主が望む工事・会社が儲かる工事を期限内に終わらせる仕事です。
- Plan:工事の計画
- Do:工事現場での指示・監督
- Check:工程確認
- Action:改善・計画修正
ちなみに施工管理の仕事内容は、施工管理(現場監督)の13の仕事内容【あなたに向いてるかも診断】にくわしくまとめています。
施工管理技士の種類|取得するメリットは大きい

建設業法第27条第1項に基づき、国土交通大臣指定機関が実施する国家試験「施工管理技術検定試験」に合格すると「施工管理技士」の国家資格が与えられます。
施工管理技士の資格には、下記の7種類があります。
- 土木施工管理技士
- 建築施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 造園施工管理技士
- 建設機械施工管理技士
- 電気通信工事施工管理技士
上記7種類に、それぞれに1級と2級があります。
ちなみに施工管理技士の7種類については、施工管理(現場監督)の11の職種を解説【仕事内容・やりがいも紹介】にもまとめています。
施工管理技士の資格を取得すると、下記の資格も付与され、できる業務の幅が広がります。
- 専任技術者
- 主任技術者
- 監理技術者
- 現場代理人(現場監督)
これら4つの仕事内容を解説していきます。
専任技術者にできること
施工管理技士の資格を取得すると専任技術者の資格も得られます。
建設会社は営業所に常勤の専任技術者を置かなければ工事を受注することができません。
建設会社は専任技術者の人数が減ってしまうと受けられる工事の数が減ってしまい、売上が下がってしまいます。
そのため、建設会社にとって専任技術者は重要な人材です。
主任技術者にできること
施工管理技士の資格を取得すると主任技術者の資格も得られます。
現場に主任技術者を配置しないと一般建設業範囲の工事を行うことができません。
主任技術者が少ない建設会社は、受けられる工事の数も少ないため売上が低くなってしまいます。
そのため、主任技術者は建設会社に必要不可欠な人材です。
監理技術者にできること
1級の施工管理技士の資格を取得すると監理技術者の資格も得られます。
現場に監理技術者を配置しないと、特定建設業範囲の工事(4500万円以上の工事)を受けることができません。
建設会社は監理技術者の数が多いほどたくさん大型の工事を請けることができます。
監理技術者は主任技術者の上位資格であるため、主任技術者よりも高く評価され、給料も高くなる会社が多いです。
現場代理人(現場監督)にできること
現場代理人はいわゆる現場監督のことです。
現場代理人の業務は下記のとおり。
- 工事現場の工程管理
- 安全管理
- 原価管理
- 品質管理
- 施工計画や図面の作成
- 人材管理、人材補充
- 下請け業者との打ち合わせ
- 書類作成
- 現場でのクレーム対応
現場代理人は1現場に1人ではなく、現場を掛け持ちすることもあります。
建設会社は現場代理人の人数が少ないと多くの工事を請けることができないため、現場代理人は重宝されます。
ちなみに「施工管理」と「現場監督」の違いは、施工管理と現場監督の4つの違い【求人情報を見るときの注意点】を参考にどうぞ。
専任技術者・主任技術者・監理技術者・現場代理人になれる施工管理技士は貴重
施工管理技士の資格を取得すると、下記のすべてをできるため、建設会社からかなり重宝される人材になれます。
- 専任技術者
- 主任技術者
- 監理技術者(1級のみ)
- 現場代理人
建設会社は施工管理技士の人数と売上が比例していますから、資格を取得することを喜びます。
建設会社によっては資格取得の勉強のお金を出してくれたり、受験料を払ってくれたりします。
また、資格を取得すると、資格手当を支給してくれたり、給料が大幅にアップする会社が多いです。
建設会社は常勤で雇用している施工管理技士によって点数が与えられます。
この点数は「経営事項審査」といい、下記が加算されます。
- 2級の施工管理技士:2点
- 1級の施工管理技士:5点
- 監理技術者講習を受けたらさらに1点追加
経営事項審査の点数が高い建設会社は公共工事の受注を受けやすくなるなど大きなメリットがあります。
だから、建設会社は施工管理技士を採用したいですし、まだ資格をとっていない社員には施工管理技士資格をとってほしいのです。
施工管理技士の資格を取得すると給料が上がるわけですよね。
施工管理技士の資格をとることで大きくキャリアアップできますので、取得することをおすすめします。
施工管理技士を取得するメリット
施工管理技士を取得する主なメリットは、以下の2つです。
- 昇給や資格手当で年収アップしやすい
- 転職先の選択肢が増える|大手に転職しやすい
1つずつ解説していきます。
施工管理技士があると昇給や資格手当で年収アップしやすい
前述のとおり、専任技術者・主任技術者・監理技術者を配置しないと工事ができないため、会社にとって施工管理技士は売上に直結する資格です。
前述のとおり、昇進や資格手当で年収アップしやすくなります。
年収アップしたい人は、施工管理技士を取得しましょう。
転職先の選択肢が増える|大手に転職しやすい
どの会社も、専任技術者・主任技術者・監理技術者になれる施工管理技士を採用したいと思っています。
そのため、施工管理技士を取得すると転職が有利になります。
特に1級の施工管理技士は、大手ゼネコンに転職できるチャンスが広がります。
建設業界は、会社規模が大きいほど年収が高くなる傾向なので、稼ぎたい人は1級の施工管理技士に挑戦しましょう。
施工管理技士を取得すると転職できる会社
施工管理技士を取得すると、下記のような会社に転職できます。
- ゼネコン
- サブコン
- ハウスメーカー
- 技術系公務員
建設業界は、大きい会社ほど給料が高い傾向にあります。
施工管理技士を取得するほど大きい会社に転職できるので、たくさん稼ぎたい人は施工管理技士を取得しましょう。
特に1級の施工管理技士だと、より大きな会社に転職できます。
ちなみに、1級と2級の平均年収の差は下記のとおり。
- 1級:550万円
- 2級:450万円
施工管理技士取得後の年収については、施工管理技士の平均年収は500万円くらい【試験に合格する3つのコツ】にまとめてます。
施工管理技士を取得しなくても仕事はできる【でも取得すべし】

結論、施工管理技士がなくても施工管理の仕事はできます。
後述しますが、施工管理技士を受験するには実務経験が必要なので、施工管理技士をもたずに働いている人はたくさんいます。

と思うかもですが、実務経験を積んで受験資格を得たら施工管理技士を取得しましょう。
前述のとおり、稼げるしキャリアアップできるからです。
仕事のやりがいにもつながるところなので、施工管理の仕事を続けたいなら施工管理技士は取ったほうがいいですよ。
ちなみに、施工管理技士なしで働くことについては、現場監督(施工管理)は資格なしでも働ける【ブラックを避ける方法】を参考にどうぞ。
【ちなみに】統括安全衛生責任者や元方安全衛生責任者にも有効
施工管理技士の資格を取得することで統括安全衛生責任者や元方安全衛生責任者も兼ねることができます。
現場の安全性を高めるために、常に50人以上の労働者をつかう特定元方事業者(元請会社)は統括安全衛生責任者と元方安全衛生責任者を配置しなければいけません。
施工管理技士=統括安全衛生責任者・元方安全衛生責任者ということではないのですが、無資格者は統括安全衛生責任者と元方安全衛生責任者になれません。
施工管理技士資格の保有者が統括安全衛生責任者や元方安全衛生責任者を兼ねることが多いです。
建設会社からすれば、施工管理技士が1人いることで統括安全衛生責任者と元方安全衛生責任者を兼ねることもできるため、やはり施工管理技士は重宝される存在です。
施工管理技士の1級と2級の違い

施工管理技士には1級と2級があるわけですが、1級と2級では受けられる工事の大きさが違います。
下請け専門業者であれば2級の施工管理技士でも工事を請けられますが、元請け会社や公共工事の受注をする場合は1級の施工管理技士が必要です。
1級の施工管理技士は監理技術者になれるため、特定建設業(下請に出す工事の総額が4500万円以上、建築一式工事の総額が7000万円以上の工事)と一般建設業、両方の建設業許可を得ることができます。
2級の施工管理技士は一般建設業(特定建設業の工事規模未満の工事)のみの建設業許可を得ることができます。
簡単にいうと、1級の施工管理技士の方が請けられる工事の規模や金額を大きいということです。
また、施工管理技士の試験は第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)があるのですが、下記の違いもあります。
- 1級:第一次検定試験と第二次検定試験が別日
- 2級:第一次検定試験と第二次検定試験が同日
1級の試験で第一次検定だけ合格して、第二次検定が不合格だったとしても、1年間は第一次検定合格の権利を持っていられます。
よって、翌年は第二次検定試験だけ受ければいいということですね。
また、前述の「経営事項審査」があるため、企業は2級よりも1級を高く評価します。
1級の方が給料が高くなりやすいです。
【追記】2021年から「技士補」が追加されました
2021年から、施工管理技士の資格の中に「技士補」という資格が追加されました。
簡単にいうと、下記の人に「技士補」が付与されます。
- 第一次検定試験:合格
- 第二次検定試験:不合格
施工管理技士の2級と1級の間の資格だと思ってください。
技士補については、技士補はいつから?【答え:2021年から!どんな資格かも解説】にまとめています。
施工管理技士資格の試験の難易度|種類別

では、施工管理技士の試験の難易度を種類別に解説していきます。
あなたが受験を考える施工管理技士の難易度をチェックしてみてください。
【基礎】第一次検定と第二次検定がある
すべての施工管理技士試験には、第一次検定と第二次検定があります。
- 第一次検定:マークシート
- 第二次検定:記述式
特徴は第二次検定の記述式試験です。
あなたが実際に経験した工事について記述していくもので、独特の書き方があります。
※記述式問題の書き方の勉強方法は後述します。
基本的には第一次検定に合格したら、第二次検定を受験します。
それでは、各施工管理技士試験の合格率や難易度を見ていきましょう。
1級土木施工管理技士の合格率と難易度
1級土木施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 56.5% | 34.5% | 19.5% |
| 令和元年 | 54.7% | 45.3% | 24.8% |
| 令和2年 | 60.1% | 31% | 18.6% |
| 令和3年 | 60.6% | 36.6% | 22.2% |
| 令和4年 | 54.6% | 28.7% | 15.7% |
| 平均 | 57.3% | 35.2% | 20.2% |
合格率は20%くらいで難易度は高めです。
第二次検定の方が合格率が低いですが、要因の1つは前述の「記述式問題」でしょう。
あなたの実務経験を書く問題がありますが、コツは1級土木施工管理技士の合格率や過去問から見る難易度にまとめたので参考にしてみてください。
2級土木施工管理技士の合格率と難易度
2級土木施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 63.4% | 35% | 18.1% |
| 令和元年 | 61.9% | 39.7% | 24.6% |
| 令和2年 | 72.6% | 42.2% | 30.6% |
| 令和3年 | 73.6% | 35.7% | 26.3% |
| 令和4年 | 65.3% | 37.9% | 24.7% |
| 平均 | 67.4% | 38.1% | 24.9% |
第一次検定の合格率が高いのが特徴です。
2級土木施工管理技士の第一次検定は年2回あるため、第一次検定に慣れていく人も多いでしょう。
第一次検定で勉強したことが第二次検定にも活かせるため、第二次検定も割と合格率が高めになっており、そこまで難易度は高くないといえます。
詳しくは、2級土木施工管理技士の難易度!合格率や過去問から分析してみたを参考にどうぞ。
1級建築施工管理技士の合格率と難易度
1級建築施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 36.6% | 37.1% | 13.6% |
| 令和元年 | 42.7% | 46.5% | 19.9% |
| 令和2年 | 51.1% | 40.7% | 20.8% |
| 令和3年 | 36% | 52.4% | 18.9% |
| 令和4年 | 46.8% | 45.2% | 21.2% |
| 平均 | 42.6% | 44.4% | 18.9% |
平均の合格率が20%を切っているため、難易度は高めです。
第一次検定の合格率も低めなので、しっかりと勉強が必要でしょう。
一般財団法人地域開発研究所で2日間の講習会が開催されているので、参加するのもおすすめです。
詳しくは、1級建築施工管理技士の合格率や過去問や受験資格から見る難易度にまとめています。
2級建築施工管理技士の合格率と難易度
2級建築施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 25.9% | 25.2% | 6.5% |
| 令和元年 | 33.3% | 27.1% | 9% |
| 令和2年 | 34.5% | 28.2% | 9.7% |
| 令和3年 | 49% | 52.9% | 25.9% |
| 令和4年 | 42.3% | 53.1% | 22.5% |
| 平均 | 37% | 37.3% | 14.7% |
年度によって合格率が大きく変わるのが特徴です。
2級建築施工管理技士を何度か受験している人の中には「今年は難しかった」「今年は簡単だった」などの声があるようです。
勉強のコツは、2級建築施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度にまとめています。
1級管工事施工管理技士の合格率と難易度
1級管工事施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 33.2% | 52.7% | 17.5% |
| 令和元年 | 52.1% | 52.7% | 27.5% |
| 令和2年 | 35% | 61.1% | 21.4% |
| 令和3年 | 24% | 73.3% | 17.6% |
| 令和4年 | 42.9% | 57% | 24.5% |
| 平均 | 37.4% | 59.4% | 21.7% |
特徴的なのは、第一次検定より第二次検定の合格率が高いことです。
第一次検定の出題科目の中に「施工管理法」があり、第二次検定の出題科目も同じく「施工管理法」があります。
第一次検定に合格できる人は、第二次検定にも合格しやすい傾向です。
詳しくは、1級管工事施工管理技士の合格率や難易度!効率的な勉強方法も解説にまとめています。
2級管工事施工管理技士の合格率と難易度
2級管工事施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 57% | 40.4% | 23% |
| 令和元年 | 69.3% | 44.1% | 30.6% |
| 令和2年 | 63.6% | 43.5% | 27.7% |
| 令和3年 | 48.6% | 46.2% | 22.5% |
| 令和4年 | 56.6% | 59.7% | 33.8% |
| 平均 | 59% | 46.8% | 27.5% |
第一次検定・第二次検定ともに合格率が高めであり、難易度は低めです。
当然ですが、1級管工事施工管理技士よりは難易度が低い試験です。
詳しくは、2級管工事施工管理技士の合格率から見る難易度!勉強方法も解説にまとめています。
1級電気工事施工管理技士の合格率と難易度
1級電気工事施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 56.1% | 73.7% | 41.3% |
| 令和元年 | 40.7% | 66.3% | 27% |
| 令和2年 | 38.1% | 72.7% | 27.7% |
| 令和3年 | 53.3% | 58.8% | 31.3% |
| 令和4年 | 38.3% | 59% | 22.6% |
| 平均 | 45.3% | 66.1% | 30% |
参考:CIC日本建設情報センター「施工管理技士の合格率[全国平均]」、国土交通省「令和4年度1級建築・電気工事施工管理技術検定「第一次検定」合格者の発表」「令和4年度 建築・電気工事施工管理技術検定(1級・2級) 「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表」
合格率は高めです。
特徴なのは、第一次検定の方が合格率が低いこと。
第一次検定は暗記系の問題が多く、過去問をくりかえし解いて勉強しないと合格は難しいです。
詳しくは、1級電気工事施工管理技士の合格率や難易度!効率的な勉強方法にまとめています。
2級電気工事施工管理技士の合格率と難易度
2級電気工事施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 61.6% | 43.2% | 26.6% |
| 令和元年 | 58.7% | 45.4% | 26.6% |
| 令和2年 | 58.5% | 45% | 26.3% |
| 令和3年 | 57.1% | 68.7% | 39.2% |
| 令和4年 | 55.6% | 61.8% | 34.3% |
| 平均 | 58.3% | 52.8% | 30.6% |
参考:CIC日本建設情報センター「施工管理技士の合格率[全国平均]」・令和2年度2級建築・電気工事施工管理技術検定「学科のみ試験(後期)」合格者の発表・令和3年度 建築・電気工事施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表・令和4年度 建築・電気工事施工管理技術検定(1級・2級) 「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表
1級と同じく、2級も合格率は高めです。
難易度はそこまで高くなく、きちんと勉強すれば合格できる試験です。
詳しくは、2級電気工事施工管理技士の合格率から見る難易度!勉強方法も解説にまとめています。
1級造園施工管理技士の合格率と難易度
1級造園施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 41.2% | 35.9% | 14.8% |
| 令和元年 | 37% | 39.6% | 14.7% |
| 令和2年 | 39.6% | 41% | 16.2% |
| 令和3年 | 35.9% | 40% | 14.4% |
| 令和4年 | 44% | 46% | 20.2% |
| 平均 | 39.5% | 40.5% | 16.1% |
参考:国土交通省「造園施工管理技術検定「実地試験」(1級・2級)の合格者の発表」「令和元年度 電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)合格者の発表」「令和2年度 管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)合格者の発表」「令和3年度 1級管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定「第一次検定」合格者の発表」「令和3年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表」「令和4年度 1級管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定 「第一次検定」合格者の発表」「令和4年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級) 「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表」
合格率は低めです。
合格率だけで見れば、難易度は高い試験といえるでしょう。
詳しくは、1級造園施工管理技士の難易度を合格率や過去問から解説【独学のコツ】にまとめています。
2級造園施工管理技士の合格率と難易度
2級造園施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 58.1% | 38% | 22.1% |
| 令和元年 | 48.9% | 37.6% | 18.3% |
| 令和2年 | 58.3% | 43% | 25.1% |
| 令和3年 | 49.8% | 42.6% | 21.2% |
| 令和4年 | 56.7% | 40.6% | 23% |
| 平均 | 54.3% | 40.4% | 21.9% |
参考:国土交通省「造園施工管理技術検定「実地試験」(1級・2級)の合格者の発表」「令和元年度 電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)合格者の発表」「令和2年度 管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)合格者の発表」「令和3年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表」「令和4年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級) 「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表」
2級よりは合格率が上がります。
第一次検定は合格率が高めなので、まずはきちんと第一次検定の対策をしましょう。
第一次検定で勉強したことは、第二次検定にも活かせます。
詳しくは、2級造園施工管理技士の合格率や難易度【過去問を中心に勉強しよう】を参考にどうぞ。
1級電気通信工事施工管理技士の合格率と難易度
1級電気通信工事施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 令和元年 | 43.1% | 49.5% | 21.3% |
| 令和2年 | 49.1% | 49.3% | 24.2% |
| 令和3年 | 58.6% | 30.1% | 17.6% |
| 令和4年 | 54.5% | 37.4% | 20.4% |
| 平均 | 51.3% | 41.6% | 20.9% |
参考:国土交通省「令和元年度 電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)合格者の発表」「令和2年度 管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)合格者の発表」「令和3年度 1級管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定「第一次検定」合格者の発表」「令和3年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表」「令和4年度 1級管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定 「第一次検定」合格者の発表」「令和4年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級) 「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表」
電気通信工事施工管理技士は、令和元年から始まった新資格です。
第一次検定・第二次検定ともに合格率は高めですが、過去問がまだ少ないため、過去問の丸暗記だけでなく知識を覚えていきましょう。
詳しくは、1級電気通信工事施工管理技士の難易度を合格率や過去問題から解説にまとめています。
2級電気通信工事施工管理技士の合格率と難易度
2級電気通信工事施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 令和元年 | 57.7% | 57.1% | 32.9% |
| 令和2年 | 63.9% | 42.9% | 27.4% |
| 令和3年 | 70% | 35% | 24.5% |
| 令和4年 | 59.1% | 35.6% | 21% |
| 平均 | 62.7% | 42.7% | 26.5% |
参考:国土交通省「令和元年度 電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)合格者の発表」「令和2年度 管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)合格者の発表」「令和3年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表」「令和4年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級) 「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表」
全体的に合格率は高めです。
特に第一次検定はかなり合格しやすいでしょう。
当然ですが、1級に比べると難易度は低めになっています。
詳しくは、2級電気通信工事施工管理技士の難易度を過去問や合格率から分析を参考にどうぞ。
1級建設機械施工管理技士の合格率と難易度
1級建設機械施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 28% | 63.3% | 17.7% |
| 令和元年 | 25.1% | 63.8% | 16% |
| 令和2年 | 20.3% | 80.2% | 16.2% |
| 令和3年 | 26.6% | 64.9% | 17.3% |
| 令和4年 | 26.4% | 52.7% | 13.9% |
| 平均 | 25.3% | 65% | 16.2% |
参考:国土交通省「建設機械施工技術検定試験 合格者の発表について」「令和元年度建設機械施工技術検定試験 合格者の発表について」「令和2年度1級建設機械施工技術検定「学科試験」合格者の発表について」「令和2年度建設機械施工技術検定試験 合格者の発表について」「令和3年度建設機械施工管理1級、2級第一次検定合格者の発表について」「令和3年度建設機械施工管理1級、2級第二次検定合格者の発表について」「令和4年度建設機械施工管理1級、2級第一次検定合格者の発表について」「令和4年度建設機械施工管理1級、2級第二次検定 合格者の発表について」
特徴は第二次検定の合格率が高いことです。
第二次検定は記述式試験と建設機械の実技試験がありますが、建設機械の実技試験は事前に講習会があるため合格しやすいです。
しかも、2級建設機械施工管理技士に合格している人には実技試験の免除制度もあるため、さらに合格しやすくなっています。
そのため、第一次検定に合格できるかが重要です。
詳しくは、1級建設機械施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度にまとめています。
2級建設機械施工管理技士の合格率と難易度
2級建設機械施工管理技士の近年の合格率は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 合計の合格率 |
| 平成30年 | 58.5% | 84% | 49.1% |
| 令和元年 | 42.4% | 83.9% | 35.6% |
| 令和2年 | 38.8% | 82.5% | 32% |
| 令和3年 | 54.7% | 75.2% | 41.1% |
| 令和4年 | 42.8% | 68.2% | 29.2% |
| 平均 | 47.4% | 78.8% | 37.4% |
参考:国土交通省「建設機械施工技術検定試験 合格者の発表について」「令和元年度建設機械施工技術検定試験 合格者の発表について」「令和2年度2級建設機械施工技術検定「学科試験」合格者の発表」「令和2年度建設機械施工技術検定試験 合格者の発表について」「令和3年度建設機械施工管理1級、2級第一次検定合格者の発表について」「令和3年度建設機械施工管理1級、2級第二次検定合格者の発表について」「令和4年度建設機械施工管理1級、2級第一次検定合格者の発表について」「令和4年度建設機械施工管理1級、2級第二次検定 合格者の発表について」
1級と同じく、第二次検定の合格率が高くなっています。
2級の第二次検定は建設機械の実技試験のみで、事前の講習会もあるため合格しやすいです。
詳しくは、2級建設機械施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度【勉強のコツ】にまとめています。
施工管理技士の合格基準
ちなみに、施工管理技士試験の合格基準は第一次検定・第二次検定ともに「60%以上の正答」です。
合格基準は他の資格試験と同等クラスといえるでしょう。
施工管理技士試験の難易度を難しい順にランキングで紹介
ちなみに、シンプルに合格率だけで施工管理技士の難易度を難しい順番に並べると下記のとおりです。
※難易度は人によって感じ方が違うので、あくまで参考として見てください。
| ランキング | 資格 | 近年の合格率 |
| 1位 | 2級建築施工管理技士 | 14.7% |
| 2位 | 1級造園施工管理技士 | 16.1% |
| 3位 | 1級建設機械施工管理技士 | 16.2% |
| 4位 | 1級建築施工管理技士 | 18.9% |
| 5位 | 1級土木施工管理技士 | 20.2% |
| 6位 | 1級電気通信工事施工管理技士 | 20.9% |
| 7位 | 1級管工事施工管理技士 | 21.7% |
| 8位 | 2級造園施工管理技士 | 21.9% |
| 9位 | 2級土木施工管理技士 | 24.9% |
| 10位 | 2級電気通信工事施工管理技士 | 26.5% |
| 11位 | 2級管工事施工管理技士 | 27.5% |
| 12位 | 1級電気工事施工管理技士 | 30% |
| 13位 | 2級電気工事施工管理技士 | 30.6% |
| 14位 | 2級建設機械施工管理技士 | 37.4% |
施工管理技士の試験内容|出題範囲も解説

それでは、各施工管理技士試験の内容や出題範囲を解説していきます。
受験する施工管理技士試験をチェックしてみてください。
1級土木施工管理技士の試験内容
第一次検定は問題A(午前)と問題B(午後)に分かれています。
すべて四肢択一のマークシートで回答します。
まず、問題A(午前)の試験内容は以下のとおり。※試験時間は2時間30分
| 科目 | 解答 |
| 土木一般 | 選択問題
15問中12問を選んで解答 |
| 専門土木 | 選択問題
34問中10問を選んで解答 |
| 法規 | 選択問題
12問中8問を選んで解答 |
続いて、問題B(午後)の試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間
| 科目 | 解答 |
| 共通工学・施工管理(知識) | 必須問題20問 |
| 施工管理法(応用能力) | 必須問題15問 |
第二次検定は記述式試験で、内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間45分
| 科目 | 解答 |
| 経験記述(安全管理・工程管理・品質管理など) | 必須問題 |
| コンクリート | |
| 施工計画 | |
| 土工 | 選択問題
2問を選んで解答 |
| 品質管理 | |
| 安全管理 | |
| 建設副産物 | |
| 土工 | 選択問題
2問を選んで解答 |
| コンクリート | |
| 安全管理 | |
| 施工計画 |
1級土木施工管理技士試験の特徴は、試験範囲が広いことです。
幅広いジャンルを勉強しなければいけないため、余裕をもったスケジュールが必要です。
できれば半年くらいの勉強期間を準備しましょう。
勉強のコツは、1級土木施工管理技士の合格率や過去問から見る難易度にまとめています。
2級土木施工管理技士の試験内容
2級土木施工管理技士には以下の3種類があり、それぞれ第一次検定と第二次検定があります。
- 土木
- 鋼構造物塗装
- 薬液注入
それぞれの試験科目は以下のとおり。
| 第一次検定 | 第二次検定 | |
| 土木 | 土木工学等
施工管理法 法規 | 施工管理法 |
| 鋼構造物塗装 | 土木工学等
鋼構造物塗装施工管理法 法規 | 鋼構造物塗装施工管理法 |
| 薬液注入 | 土木工学等
薬液注入施工管理法 法規 | 薬液注入施工管理法 |
例として「土木」の第一次検定の試験内容を解説します。
すべて四肢択一のマークシートで解答します。※試験時間は2時間10分
| 科目 | 解答 |
| 土木一般 | 選択問題
11問中9問を選んで解答 |
| 専門土木 | 選択問題
20問中6問を選んで解答 |
| 法規 | 選択問題
11問中6問を選んで解答 |
| 共通工学・施工管理 | 必須問題11問 |
| 施工管理法(基礎的な能力) | 必須問題8問 |
第二次検定は記述好き試験で、内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間
| 科目 | 解答 |
| 経験記述(安全管理・工程管理・品質管理など) | 必須問題5問 |
| 施工管理法、工程管理、コンクリートなど | |
| 施工管理法 | 選択問題
2問中1問を選んで解答 |
| 施工管理法 | 選択問題
2問中1問を選んで解答 |
1級に比べると全体的に問題数が少なくなっています。
その分、2級の方が難易度が低めです。
また、試験範囲も2級の方が限定的なので、2級→1級の順番で受験する人が多いです。
勉強のコツは、2級土木施工管理技士の難易度!合格率や過去問から分析してみたにまとめています。
1級建築施工管理技士の試験内容
第一次検定は午前の部と午後の部があります。
まず、午前の部の試験内容は以下のとおり。
すべて四肢択一式のマークシートです。試験時間は2時間30分。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 科目 | 解答 | |
| 建築学等 | 建築学(環境工学、力学、一般構造、建築材料) | 選択問題
15問中12問を選んで解答 |
| 建築学(設備その他積算、契約) | 必須問題5問 | |
| 施工管理法 | 施工共通
施工(躯体) | 選択問題
10問中7問を選んで解答 |
| 施工共通
施工(仕上げ) | 選択問題
9問中7問を選んで解答 | |
| 施工計画 | 必須問題5問 | |
続いて、第一次検定の午後の部の試験内容は以下です。試験時間は2時間。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法(工程管理、品質管理、安全管理) | 必須問題10問
四肢択一式 |
| 躯体、仕上げ | 必須問題6問
五肢択二式 |
| 法規(建築基準法、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、その他関連法令) | 選択問題
12問中8問を選んで解答 四肢択一式 |
続いて第二次検定の試験内容は以下のとおりです。試験時間は3時間。
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法(経験記述、施工計画、工程管理、品質管理、安全管理など) | 必須問題
記述式 |
| 施工管理法 | 必須問題
マークシート 五肢択一式 |
1級建築施工管理技士の試験問題は「五肢択一式」「五肢択二式」の問題もあります。
四肢択一式より難易度が上がるため、しっかりと勉強しておく必要があるでしょう。
勉強のコツは、1級建築施工管理技士の合格率や過去問や受験資格から見る難易度にまとめています。
2級建築施工管理技士の試験内容
2級建築施工管理技士は3つの区分に分かれています。
- 建築
- 躯体
- 仕上げ
第一次検定の試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間30分
すべてマークシートで解答します。
| 科目 | 解答 |
| 建築学(環境工学、一般構造、構造力学、建築材料) | 選択問題
14問中9問を選んで解答 四肢択一式 |
| 建築学(設備その他) | 必須問題3問
四肢択一式 |
| 施工(建築、躯体、仕上げ) | 選択問題
11問中8問を選んで解答 四肢択一式 |
| 施工管理法(施工計画、工程管理、品質管理、安全管理) | 必須問題10問
四肢択一式 |
| 応用能力問題(躯体、仕上げ) | 必須問題2問
四肢択二式 |
| 法規 | 選択問題
8問中6問を選んで解答 四肢択一式 |
続いて第二次検定の試験内容は以下のとおりです。試験時間は2時間。
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法or躯体施工管理法or仕上施工管理法(経験記述、用語、工程管理など) | 必須問題
記述式 |
| 法規 | 必須問題
マークシート 四肢択一式 |
| 施工など
建築・躯体・仕上げごとに選択 | 必須問題
マークシート 四肢択一式 |
1級に比べると記述式が少なかったり、問題の選択肢が少ない傾向で難易度は低めです。
こちらも2級→1級の順番に受験する人が多いです。
勉強のコツは、2級建築施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度にまとめています。
1級管工事施工管理技士の試験内容
1級管工事施工管理技士の第一次検定は、午前と午後に分かれています。
午前は「機械工学等」の試験で、内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間30分
すべて四肢択一式のマークシートです。
| 科目 | 解答 |
| 原論 | 必須問題10問 |
| 電気工学 | 必須問題2問 |
| 建築学 | 必須問題2問 |
| 空調・衛生 | 選択問題
23問中12問を選んで解答 |
| 設備 | 必須問題5問 |
| 設計図書 | 必須問題2問 |
そして、第一次検定の午後試験は以下のとおりです。※試験時間は2時間
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法 | 必須問題10問
四肢択一式 |
| 法規 | 選択問題
12問中10問を選んで解答 四肢択一式 |
| 施工管理法(応用能力) | 必須問題7問
四肢択二式 |
第二次検定は記述式試験で、内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間45分
| 科目 | 解答 |
| 施工要領図 | 必須問題1問 |
| 空調or衛生 | 選択問題
2問中1問を選んで解答 |
| 工程管理or法規 | 選択問題
2問中1問を選んで解答 |
| 施工経験記述 | 必須問題1問 |
1級管工事施工管理技士は選択問題が少ないので「苦手分野を捨てる」という戦略をとりにくいです。
まんべんなく勉強しなければいけない点では、難易度が高いといえるでしょう。
勉強のコツは、1級管工事施工管理技士の合格率や難易度!効率的な勉強方法も解説にまとめています。
2級管工事施工管理技士の試験内容
第一次検定の試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間10分
すべてマークシートです。
| 科目 | 解答 |
| 一般基礎(原論) | 必須問題4問
四肢択一式 |
| 電気工学 | 必須問題1問
四肢択一式 |
| 建築学 | 必須問題1問
四肢択一式 |
| 空調・衛生 | 選択問題
17問中9問を選んで解答 四肢択一式 |
| 設備 | 必須問題4問
四肢択一式 |
| 設計図書 | 必須問題1問
四肢択一式 |
| 施工管理法 | 選択問題
10問中8問を選んで解答 四肢択一式 |
| 法規 | 選択問題
10問中8問を選んで解答 四肢択一式 |
| 施工管理法(能力問題) | 必須問題4問
四肢択二式 |
第二次検定は記述式試験で、内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間
| 科目 | 解答 |
| 設備全般 | 必須問題1問 |
| 設備全般 | 選択問題
2問中1問を選んで解答 |
| 工程管理or法規 | 選択問題
2問中1問を選んで解答 |
| 施工経験記述 | 必須問題1問 |
管工事施工管理技士に合格するためには、機械工学・施工管理法・法規の基礎知識が必要です。
| 必要な知識 | 内容 |
| 機械工学 | 建築学
電気工学 機械工学 衛生工学 給排水設備 空調設備 冷暖房 設計図 |
| 施工管理法 | 工程管理
安全管理 品質管理 設計図書の読み方・作成方法 機材の選び方や使い方 |
| 法規 | 施工の法令 |
第一次検定の施工管理法(能力問題)は、四肢択二式になっている点も難しいポイントです。
勉強のコツは、2級管工事施工管理技士の合格率から見る難易度!勉強方法も解説にまとめています。
1級電気工事施工管理技士の試験内容
1級電気工事施工管理技士の第一次検定は、午前と午後に分かれています。
午前の試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間30分
すべて四肢択一式のマークシートです。
| 科目 | 解答 |
| 電気工学(電気通信工学、土木工学、機械工学、建築学など) | 選択問題
15問中10問を選んで解答 |
| 電気設備(発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備など) | 選択問題
32問中14問を選んで解答 |
| 関連分野(施工管理に必要な知識や設計図書の知識など) | 選択問題
8問中5問を選んで解答 必須問題2問 |
続いて、午後の第一次検定の内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法(施工管理法の応用能力問題) | 必須問題6問
五肢択一式 |
| 施工管理法(施工管理計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理など) | 必須問題6問
選択問題9問中6問に解答 四肢択一式 |
| 法規(施工管理の法令の知識) | 選択問題13問中10問に解答
四肢択一式 |
続いて、第二次検定の内容は以下のとおりです。※試験時間は3時間
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法(安全管理、工程管理、品質管理、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備など) | 必須問題6問
記述式 |
| 施工管理法(監理技術者の業務に必要な知識) | 必須問題6問
五肢択一式 |
試験範囲が広いだけでなく、計算問題もあるので難易度は高めです。
早めに勉強を始めるのがおすすめです。
勉強のコツは、1級電気工事施工管理技士の合格率や難易度!効率的な勉強方法にまとめています。
2級電気工事施工管理技士の試験内容
第一次検定の試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間30分
すべてマークシートです。
| 科目 | 解答 |
| 電気工学(電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学、建築学など) | 選択問題
12問中8問を選んで解答 四肢択一式 |
| 電気設備(発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備など) | 選択問題
19問中10問を選んで解答 四肢択一式 |
| 関連分野 | 必須問題1問
選択問題6問中3問に解答 四肢択一式 |
| 施工管理法(能力問題) | 必須問題4問
五肢択一式 |
| 施工管理法(施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理など) | 選択問題
10問中6問を選んで解答 四肢択一式 |
| 法規 | 選択問題
12問中8問を選んで解答 四肢択一式 |
続いて、第二次検定の内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法(能力問題) | 必須問題3問
記述式 |
| 施工管理法 | 必須問題2問
四肢択一式 |
第二次検定はすべて必須問題なので、苦手分野を避けることができません。
まんべんなく勉強していく必要があるでしょう。
勉強のコツは、2級電気工事施工管理技士の合格率から見る難易度!勉強方法も解説にまとめています。
1級造園施工管理技士の試験内容
1級造園施工管理技士の試験は、午前の部と午後の部に分かれています。
午前の部の試験内容は以下のとおりです。
すべて四肢択一式のマークシートです。※試験時間は2時間30分
| 科目 | 解答 |
| 土木工学等
施工管理法 | 必須問題36問 |
続いて、午後の部の試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間30分
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法
法規 | 必須問題23問
四肢択一式 |
| 施工管理法(能力問題) | 必須問題6問
四肢択多式 |
第二次検定は記述式試験で、試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間45分
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法(経験記述、造園工事など) | 必須問題2問 |
| 施工管理法(工程管理、品質管理、安全管理など) | 選択問題
3問中1問を選んで解答 |
1級造園施工管理は必須問題が多いです。
苦手分野を避けられないので、漏れがないように勉強していきましょう。
第一次検定の施工管理法(能力問題)は、四肢択多式なので難易度が高くなっています。
勉強のコツは、1級造園施工管理技士の難易度を合格率や過去問から解説【独学のコツ】にまとめています。
2級造園施工管理技士の試験内容
第一次検定の試験内容は以下のとおりです。
すべてマークシートです。※試験時間は2時間10分
| 科目 | 解答 |
| 土木工学等
施工管理法 法規 | 必須問題36問
四肢択一式 |
| 施工管理法(能力問題) | 必須問題4問
四肢択多式 |
第二次検定は記述式問題で、内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法(経験記述、応用能力、施工計画など) | 必須問題3問 |
1級と同様、造園施工管理技士は必須問題が多いのが特徴です。
参考書と過去問題集をつかって、網羅的に勉強していきましょう。
勉強のコツは、2級造園施工管理技士の合格率や難易度【過去問を中心に勉強しよう】にまとめています。
1級電気通信工事施工管理技士の試験内容
1級電気通信工事施工管理技士の第一次検定は、午前の部と午後の部に分かれています。
午前の部の試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間30分
| 科目 | 解答 |
| 電気通信理論 | 選択問題
16問中11問を選んで解答 |
| 電気通信設備 | 選択問題
28問中14問を選んで解答 |
| 法規 | 選択問題
14問中8問を選んで解答 |
続いて、午後の部の試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間
| 科目 | 解答 |
| 設計 | 必須問題2問 |
| 関連分野 | 選択問題
8問中5問を選んで解答 |
| 施工管理法 | 選択問題
22問中20問を選んで解答 |
第二次検定は記述式問題で、内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間45分
| 科目 | 解答 |
| 経験記述、施工管理法(施工法、工程管理、安全管理、用語、法令など) | 必須問題6問 |
第二次検定の6問すべてが必須問題なので、難易度が高くなっています。
ですが、5人に1人くらい合格できる試験なので、きちんと勉強していけば合格を狙えるでしょう。
勉強のコツは、1級電気通信工事施工管理技士の難易度を合格率や過去問題から解説にまとめています。
2級電気通信工事施工管理技士の試験内容
第一次検定の試験内容は以下のとおりです。
すべて四肢択一式のマークシートです。※試験時間は2時間10分
| 科目 | 解答 |
| 電気通信理論 | 選択問題
12問中9問を選んで解答 |
| 電気通信設備 | 選択問題
20問中7問を選んで解答 |
| 法規 | 選択問題
12問中7問を選んで解答 |
| 契約 | 必須問題1問 |
| 関連分野 | 選択問題
7問中3問を選んで解答 |
| 施工管理法 | 必須問題13問 |
第二次検定は記述式で、試験内容は以下のとおりです。※試験時間は2時間
| 科目 | 解答 |
| 経験記述、施工管理法(施工全般、法規など) | 必須問題5問 |
1級に比べると問題数が少なく、当然ながら難易度は下がります。
ですが、令和元年に新設された資格であることから、まだまだ過去問が少ないなど勉強しにくいこともあるでしょう。
勉強のコツは、2級電気通信工事施工管理技士の難易度を過去問や合格率から分析にまとめています。
1級建設機械施工管理技士の試験内容
第一次検定の試験内容は以下のとおりです。
すべて四肢択一式のマークシートです。※試験時間は2時間25分
| 科目 | 解答 |
| 土木工学 | 選択問題
12問中10問を選んで解答 |
| 施工管理法、建設機械原動機、石油燃料、建設機械、建設機械施工法 | 必須問題34問 |
| 法規 | 選択問題
5問中3問を選んで解答 |
| 選択問題
5問中3問を選んで解答 |
第二次検定は以下の2つがあります。
- 記述式の筆記試験(2時間)
- 実技試験
記述式の筆記試験の試験内容は以下のとおり。
| 科目 | 解答 |
| 組合せ施工法 | 必須問題 |
| 施工管理法 | 選択問題
3問中1問を選んで解答 |
| 建設機械施工法 | 選択問題
3問中1問を選んで解答 |
実技試験は以下の6種別のうち、2種別を選択して受験します。
| 種別 | 科目 |
| 第1種 | トラクター系建設機械操作施工法 |
| 第2種 | ショベル系建設機械操作施工法 |
| 第3種 | モーター・グレーダー操作施工法 |
| 第4種 | 締め固め建設機械操作施工法 |
| 第5種 | 舗装用建設機械操作施工法 |
| 第6種 | 基礎工事用建設機械操作施工法 |
1級建設機械施工管理技士の大きな特徴は、第二次検定で実技試験があることです。
実際に建設機械を運転する試験です。
ただし、事前に講習会があるため、講習会に参加するとかなり合格率が上がります。
さらに、2級建設機械施工管理技士に合格している人は、実技試験の免除制度があるため合格しやすくなっています。
- 2級で1つの種別に合格してる人は、1種別は免除
- 2級で2つの種別に合格してる人は、2種別が免除
詳しくは、1級建設機械施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度にまとめています。
2級建設機械施工管理技士の試験内容
2級建設機械施工管理技士の第一次検定は「共通問題」と「種別問題」に分かれています。
すべて四肢択一式のマークシートです。
まず「共通問題」の内容を解説します。※試験時間は1時間
| 科目 | 解答 |
| 土木工学 | 選択問題
12問中9問を選んで解答 |
| 施工管理法 | 必須問題6問 |
| 建設機械原動機 | 必須問題2問 |
| 石油燃料 | 必須問題1問 |
| 潤滑剤 | 必須問題1問 |
| 法規 | 選択問題
5問中3問を選んで解答 |
| 選択問題
5問中3問を選んで解答 |
続いて「種別問題」の内容は以下のとおり。※試験時間は1時間
| 種別 | 科目 | 解答 |
| 第1種 | トラクター系建設機械
トラクター系建設機械操作施工法 | 必須問題20問 |
| 第2種 | ショベル系建設機械
ショベル系建設機械操作施工法 | 必須問題20問 |
| 第3種 | モーター・グレーダー
モーター・グレーダー施工法 | 必須問題20問 |
| 第4種 | 締め固め建設機械
締め固め建設機械操作施工法 | 必須問題20問 |
| 第5種 | 舗装用建設機械
舗装用建設機械操作施工法 | 必須問題20問 |
| 第6種 | 基礎工事用建設機械
基礎工事用建設機械操作施工法 | 必須問題20問 |
第二次検定は四肢択一式の筆記試験(マークシート)と、建設機械の実技試験があります。
筆記試験の内容は以下のとおり。※試験時間は40分
| 科目 | 解答 |
| 施工管理法 | 必須問題10問 |
実技試験の内容は以下のとおりです。
| 種別 | 科目 |
| 第1種 | トラクター系建設機械操作施工法 |
| 第2種 | ショベル系建設機械操作施工法 |
| 第3種 | モーター・グレーダー操作施工法 |
| 第4種 | 締め固め建設機械操作施工法 |
| 第5種 | 舗装用建設機械操作施工法 |
| 第6種 | 基礎工事用建設機械操作施工法 |
施工管理技士試験の第二次試験で唯一、記述式試験がありません。
実技試験も、事前に講習会があるので合格しやすくなっています。
詳しくは、2級建設機械施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度【勉強のコツ】にまとめています。
施工管理技士試験の実施機関
施工管理技士の種類によって実施機関が違います。
受験申込の先が資格によって変わりますので、確認しておきましょう。
| 資格名 | 実施機関 |
| 土木施工管理技士
管工事施工管理技士 造園施工管理技士 電気通信工事施工管理技士 | 一般財団法人全国建設研修センター |
| 建築施工管理技士
電気工事施工管理技士 | 一般財団法人建設業振興基金 |
| 建設機械施工管理技士 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 |
受験申込は原則、簡易書留郵便で申込書を郵送ですが、試験によってはインターネット申込が可能な試験もあります。
申込用紙は1枚600円です。
申込方法は各実施機関のホームページで確認しましょう。
受験手数料
各施工管理技士の受験手数料を見てみましょう。
| 資格名 | 第一次検定試験受験手数料 | 第二次検定試験受験手数料 |
| 1級土木施工管理技士 | 10500円 | 10500円 |
| 2級土木施工管理技士 | 5250円 | 5250円 |
| 1級建築施工管理技士 | 10800円 | 10800円 |
| 2級建築施工管理技士 | 5400円 | 5400円 |
| 1級管工事施工管理技士 | 10500円 | 10500円 |
| 2級管工事施工管理技士 | 5250円 | 5250円 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 13200円 | 13200円 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 6600円 | 6600円 |
| 1級造園施工管理技士 | 14400円 | 14400円 |
| 2級造園施工管理技士 | 7200円 | 7200円 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 13000円 | 13000円 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 6500円 | 6500円 |
| 1級建設機械施工管理技士 | 14700円 | 37800円 |
| 2級建設機械施工管理技士 | 14700円 | 27100円 |
施工管理技士の受験資格

続いて、各施工管理技士の受験資格を紹介します。
該当するかチェックしてみてください。
1級土木施工管理技士の受験資格
1級土木施工管理技士の第一次検定試験の受験資格は下記の表のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 最終学歴or資格 | 土木施工の実務経験年数 | ||
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| 大卒、専門卒(高度専門士) | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | |
| 短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | 卒業後5年以上 | 卒業後7年6ヶ月以上 | |
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後10年以上 | 卒業後11年6ヶ月以上 | |
| その他 | 15年以上 | ||
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後8年以上の実務経験に指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上の実務経験後に専任の監理技術者に2年以上の指導を受けている者 | – | |
| 専任の主任技術者の実務経験1年以上 | 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後8年以上 | 卒業後9年6ヶ月以上 |
| その他 | 13年以上 | ||
| 2級合格者 | |||
続いて、第二次検定試験の受験資格は下記のとおり。
| 最終学歴or資格 | 土木施工の実務経験年数 | ||
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| 2級合格後3年以上 | 合格後1年以上の指導監督的実務経験および専任の監理技術者に2年以上の指導を受けた実務経験が3年以上 | ||
| 2級合格後5年以上 | 合格後5年以上 | ||
| 2級合格後5年未満 | 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後9年以上 | 卒業後10年6ヶ月以上 |
| その他 | 14年以上 | ||
| 専任の主任技術者の実務経験が1年以上の2級合格者 | 合格後3年以上 | 合格後1年以上、専任の主任技術者実務経験を含む3年以上 | |
| 合格後3年未満の短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | – | 卒業後7年以上 | |
| 合格後3年未満の高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後7年以上 | 卒業後8年6ヶ月以上 | |
| 合格後3年未満のその他 | 12年以上 | ||
詳しくは、1級土木施工管理技士の合格率や過去問から見る難易度をどうぞ。
2級土木施工管理技士の受験資格
2級土木施工管理技士の第一次検定試験の受験資格は「17歳以上」です。
第二次検定試験の受験資格は下記の表のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 最終学歴 | 土木施工の実務経験年数 | |
| 指定学科 | 指定学科以外 | |
| 大卒、専門卒(高度専門士) | 卒業後1年以上 | 卒業後1年6ヶ月以上 |
| 短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | 卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 |
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 |
| その他 | 8年以上 | |
詳しくは、2級土木施工管理技士の難易度!合格率や過去問から分析してみたにまとめています。
1級建築施工管理技士の受験資格
1級建築施工管理技士の受験資格は大きく4つの区分があります。
- 最終学歴による受験資格
- 2級建築士の合格者
- 2級建築施工管理技士の合格者(合格後5年以上)
- 2級建築施工管理技士の合格者(合格後5年未満)
詳しい受験資格は、一般財団法人建設業振興基金のサイトに記載されているので必ずチェックしましょう。
また、1級建築施工管理技士の合格率や過去問や受験資格から見る難易度も参考にどうぞ。
2級建築施工管理技士の受験資格
2級建築施工管理技士の受験資格は、下記の2つに分けられます。
- 学歴による区分
- 職業能力開発促進法による技能検定(職業訓練)を受けた人
詳しい受験資格については、一般財団法人建設業振興基金のサイトで確認してみてください。
また、2級建築施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度も参考にどうぞ。
1級管工事施工管理技士の受験資格
1級管工事施工管理技士の第一次検定試験の受験資格は下記の表のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 最終学歴or資格 | 管工事の実務経験年数 | ||
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| 大卒、専門卒(高度専門士) | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | |
| 短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | 卒業後5年以上 | 卒業後7年6ヶ月以上 | |
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後10年以上 | 卒業後11年6ヶ月以上 | |
| その他 | 15年以上 | ||
| 技能検定合格者 | 10年以上 | ||
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後8年以上の実務経験に指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上の実務経験後に専任の監理技術者に2年以上の指導を受けている者 | – | |
| 専任の主任技術者の実務経験1年以上 | 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後8年以上 | 卒業後9年6ヶ月以上 |
| その他 | 13年以上 | ||
| 2級合格者 | |||
続いて、第二次検定試験の受験資格は下記のとおり。
| 最終学歴or資格 | 管工事の実務経験年数 | ||
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| 2級合格後3年以上 | 合格後1年以上の指導監督的実務経験および専任の監理技術者に2年以上の指導を受けた実務経験が3年以上 | ||
| 2級合格後5年以上 | 合格後5年以上 | ||
| 2級合格後5年未満 | 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後9年以上 | 卒業後10年6ヶ月以上 |
| その他 | 14年以上 | ||
| 専任の主任技術者の実務経験が1年以上の2級合格者 | 合格後3年以上 | 合格後1年以上、専任の主任技術者実務経験を含む3年以上 | |
| 合格後3年未満の短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | 卒業後5年以上 | 卒業後7年以上 | |
| 合格後3年未満の高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後7年以上 | 卒業後8年6ヶ月以上 | |
| 合格後3年未満のその他 | 12年以上 | ||
詳しくは、1級管工事施工管理技士の合格率や難易度!効率的な勉強方法も解説にまとめてます。
2級管工事施工管理技士の受験資格
2級管工事施工管理技士の第一次検定試験の受験資格は「17歳以上」です。
第二次検定試験の受験資格は下記の表のとおり。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 最終学歴 | 管工事の実務経験年数 | |
| 指定学科 | 指定学科以外 | |
| 大卒、専門卒(高度専門士) | 卒業後1年以上 | 卒業後1年6ヶ月以上 |
| 短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | 卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 |
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 |
| その他 | 8年以上 | |
| 技能検定合格者 | 4年以上 | |
詳しくは、2級管工事施工管理技士の合格率から見る難易度!勉強方法も解説にまとめてます。
1級電気工事施工管理技士の受験資格
1級電気工事施工管理技士の受験資格は、大きく5つの区分に分かれています。
- 最終学歴による受験資格
- 2級電気工事施工管理技士の合格者(合格後実務経験5年以上)
- 2級電気工事施工管理技士の合格者(合格後5年未満)
- 第一種・第二種・第三種電気主任技術者免状の交付を受けた人
- 第一種電気工事士免状の交付を受けた人
詳しい受験資格については、一般財団法人建設業振興基金のサイトに記載されているので必ずチェックしましょう。
また、1級電気工事施工管理技士の合格率や難易度!効率的な勉強方法も参考にどうぞ。
2級電気工事施工管理技士の受験資格
2級電気工事施工管理技士の受験資格は、大きく4つの区分に分かれています。
- 最終学歴による受験資格
- 第一種・第二種・第三種電気主任技術者免状の交付を受けた人
- 第一種電気工事士免状の交付を受けた人
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた人
詳しい受験資格については、一般財団法人建設業振興基金のサイトに記載されているのでチェックしてください。
また、2級電気工事施工管理技士の合格率から見る難易度!勉強方法も解説も参考にどうぞ。
1級造園施工管理技士の受験資格
1級造園施工管理技士の第一次検定試験の受験資格は下記の表のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 最終学歴or資格 | 造園工事の実務経験年数 | ||
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| 大卒、専門卒(高度専門士) | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | |
| 短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | 卒業後5年以上 | 卒業後7年6ヶ月以上 | |
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後10年以上 | 卒業後11年6ヶ月以上 | |
| その他 | 15年以上 | ||
| 技能検定合格者 | 10年以上 | ||
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後8年以上の実務経験に1年以上の指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上の実務経験後に専任の監理技術者に2年以上の指導を受けている者 | – | |
| 専任の主任技術者の実務経験1年以上 | 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後8年以上 | 卒業後9年6ヶ月以上 |
| その他 | 13年以上 | ||
| 2級合格者 | |||
続いて、第二次検定試験の受験資格は下記のとおり。
| 最終学歴or資格 | 造園工事の実務経験年数 | ||
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| 2級合格後3年以上 | 合格後1年以上の指導監督的実務経験および専任の監理技術者に2年以上の指導を受けた実務経験が3年以上 | ||
| 2級合格後5年以上 | 合格後5年以上 | ||
| 2級合格後5年未満 | 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後9年以上 | 卒業後10年6ヶ月以上 |
| その他 | 12年以上 | ||
| 専任の主任技術者の実務経験が1年以上の2級合格者 | 合格後3年以上 | 合格後1年以上、専任の主任技術者実務経験を含む3年以上 | |
| 合格後3年未満の短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | – | 卒業後7年以上 | |
| 合格後3年未満の高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後7年以上 | 卒業後8年6ヶ月以上 | |
| 合格後3年未満のその他 | 12年以上 | ||
詳しくは、1級造園施工管理技士の難易度を合格率や過去問から解説【独学のコツ】にまとめてます。
2級造園施工管理技士の受験資格
2級造園施工管理技士の第一次検定試験の受験資格は「17歳以上」です。
第二次検定試験の受験資格は下記の表のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 最終学歴 | 造園工事の実務経験年数 | |
| 指定学科 | 指定学科以外 | |
| 大卒、専門卒(高度専門士) | 卒業後1年以上 | 卒業後1年6ヶ月以上 |
| 短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | 卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 |
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 |
| その他 | 8年以上 | |
| 技能検定合格者 | 4年以上 | |
詳しくは、2級造園施工管理技士の合格率や難易度【過去問を中心に勉強しよう】にまとめています。
1級電気通信工事施工管理技士の受験資格
1級電気通信工事施工管理技士の第一次検定試験の受験資格は下記の表のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 最終学歴or資格 | 電気通信工事の実務経験年数 | ||
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| 大卒、専門卒(高度専門士) | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | |
| 短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | 卒業後5年以上 | 卒業後7年6ヶ月以上 | |
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後10年以上 | 卒業後11年6ヶ月以上 | |
| その他 | 15年以上 | ||
| 電気主任技術者 | 6年以上 | ||
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後8年以上の実務経験に1年以上の指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上の実務経験後に専任の監理技術者に2年以上の指導を受けている者 | – | |
| 専任の主任技術者の実務経験1年以上 | 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後8年以上 | 卒業後9年6ヶ月以上 |
| その他 | 13年以上 | ||
| 2級の実地試験に合格した人 | |||
続いて、第二次検定試験の受験資格は下記のとおり。
| 最終学歴or資格 | 電気通信工事の実務経験年数 | ||
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| 2級の実地試験に合格後3年以上 | 合格後1年以上の指導監督的実務経験および専任の監理技術者に2年以上の指導を受けた実務経験が3年以上 | ||
| 2級の実地試験に合格後5年以上 | 合格後5年以上 | ||
| 2級の実地試験に合格後5年未満 | 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後9年以上 | 卒業後10年6ヶ月以上 |
| その他 | 14年以上 | ||
| 専任の主任技術者の実務経験が1年以上の2級の実地試験合格者 | 合格後3年以上 | 合格後1年以上、専任の主任技術者実務経験を含む3年以上 | |
| 合格後3年未満の短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | – | 卒業後7年以上 | |
| 合格後3年未満の高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後7年以上 | 卒業後8年6ヶ月以上 | |
| 合格後3年未満のその他 | 12年以上 | ||
詳しくは、1級電気通信工事施工管理技士の難易度を合格率や過去問題から解説にまとめてます。
2級電気通信工事施工管理技士の受験資格
2級電気通信工事施工管理技士の第一次検定試験の受験資格は「17歳以上」です。
第二次検定試験の受験資格は下記の表のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 最終学歴 | 電気通信工事の実務経験年数 | |
| 指定学科 | 指定学科以外 | |
| 大卒、専門卒(高度専門士) | 卒業後1年以上 | 卒業後1年6ヶ月以上 |
| 短大卒、高専卒、専門卒(専門士) | 卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 |
| 高卒、中等教育学校卒、専門卒(高度専門士・専門士以外) | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 |
| その他 | 8年以上 | |
| 電気通信主任技術者 | 1年以上 | |
詳しくは、2級電気通信工事施工管理技士の難易度を過去問や合格率から分析をどうぞ。
1級建設機械施工管理技士の受験資格
続いて、1級建設機械施工管理技士の受験資格は、大きく分けて下記の2つの区分があります。
- 最終学歴
- 2級建設機械施工技士の合格者
受験資格の詳細は、建設管理センターのサイトで必ずチェックしてください。
また、1級建設機械施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度【乗れる機械も紹介】も参考にどうぞ。
2級建設機械施工管理技士の受験資格
受験資格の詳細は、建設管理センターのサイトで必ずチェックしておきましょう。
また、2級建設機械施工管理技士の合格率や過去問からみる難易度【勉強のコツ】も参考にどうぞ。
施工管理技士の学習ノウハウ|仕事をしながら勉強して合格に近づくコツ
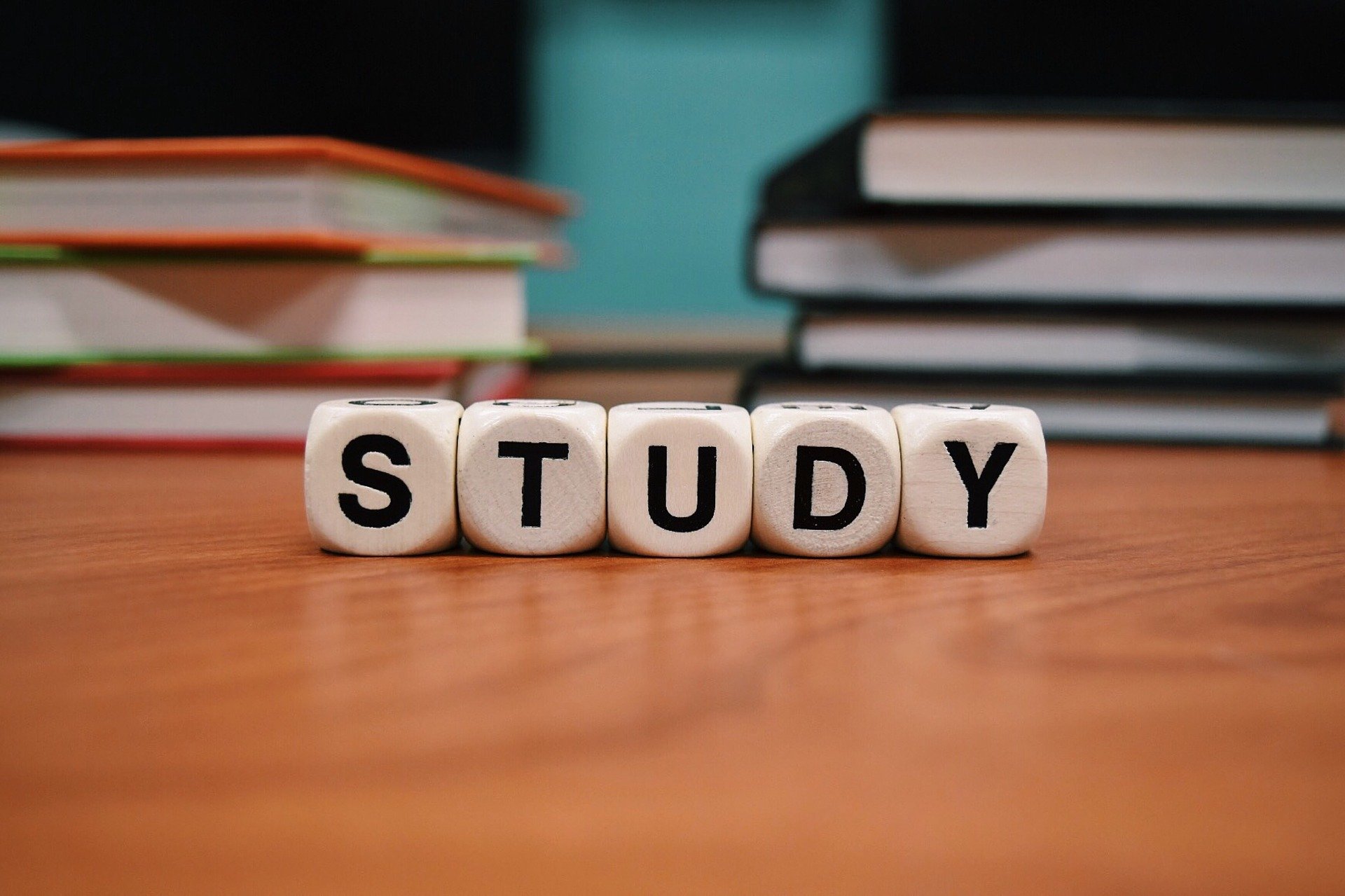
普段の仕事をしながら空き時間で勉強する人がほとんどです。
なかなかまとまった時間をとれないでしょうから、毎日少しずつ勉強するのが一番でしょう。
施工管理技士試験に合格するためにおすすめの勉強方法をご紹介します。
参考書と問題集と過去問題で独学
独学で勉強する場合は、下記の3点セットがおすすめです。
- 参考書
- 問題集
- 過去問
参考書で基礎を学習してから、簡単な問題集を繰り返し解きます。
できれば、問題集は何周か解いてみましょう。
問題と解答を記憶するくらい勉強すると安心です。
参考書と問題集になれたら、過去問で仕上げをします。
過去問も問題と回答を覚えるくらいになればかなり安心です。
過去問集も何周か解くことをおすすめします。
根気はいりますが、毎日少しずつ勉強することで合格率は高くなります。
予備校
施工管理技士の試験対策をする予備校もあるので、行ける人にはおすすめです。
ただし、独学より費用がかかるのと、時間的に授業に参加できない人もいるでしょう。
合格率の高い予備校は講師の説明がわかりやすいのでおすすめです。
通信講座やEラーニング|第二次検定の経験記述を添削
通信講座もおすすめです。
独学より費用がかかりますが、自分の空き時間で勉強しやすいメリットがあります。
合格率の高い通信講座を選びましょう。
テキストがわかりやすく、試験合格のためのポイントがわかりやすくなっています。
特に、第二次検定の「経験記述」は添削してもらった方が合格率が高いです。
自分では文章の良し悪しがわからないから。
通信講座で経験記述を添削してもらいましょう。
講習会に参加
試験が近くなると講習会を開催してくれる資格もあります。
積極的に活用しましょう。
企業によっては試験が近づくと企業内で試験対策講座をやってくれるところもあります。
試験前の確認のためにも参加するようにしましょう。
スキマ時間は施工管理技士アプリで効率よく勉強
スキマ時間や移動時間は、施工管理技士アプリで勉強すると良いでしょう。
おすすめのアプリは以下の記事にまとめています。
施工管理技士試験の勉強スケジュール例
施工管理技士試験の勉強スケジュールは、以下の手順で考えるのがおすすめです。
- 目標設定:試験日までの残りの日数を確認して、何をどれだけ勉強するかの目標を立てる
- 優先順位の決定:得意・不得意を把握して、不得意な部分を重点的に学習する
- 過去問の反復:過去問をくりかえし解いて覚える(できれば5年分×5周)
例えば、以下のようなスケジュールがおすすめです。
- 1ヶ月目:目標設定と優先順位の決定
- 2ヶ月〜6ヶ月目:過去問の反復
やみくもに勉強するのではなく、段取り良く勉強していきましょう。
施工管理技士試験の勉強時間の目安|すぐ始めるべし
あくまで目安ですが、施工管理技士試験の勉強時間は250時間はほしいところです。
難関試験や基礎知識がない場合は、400時間以上は勉強しないといけないでしょう。
仮に250時間だとすると、勉強を始めるタイミングは以下のイメージ。
- 1日2時間なら4ヶ月前から
- 1日1時間なら8ヶ月前から
また、仕事をしながら勉強するのは思ったより大変なので、すぐに勉強を始めるのをおすすめします。
「勉強する習慣」もつけていく必要があるため、今日から勉強を始めてみてください。
施工管理技士と他の資格の難易度を比較
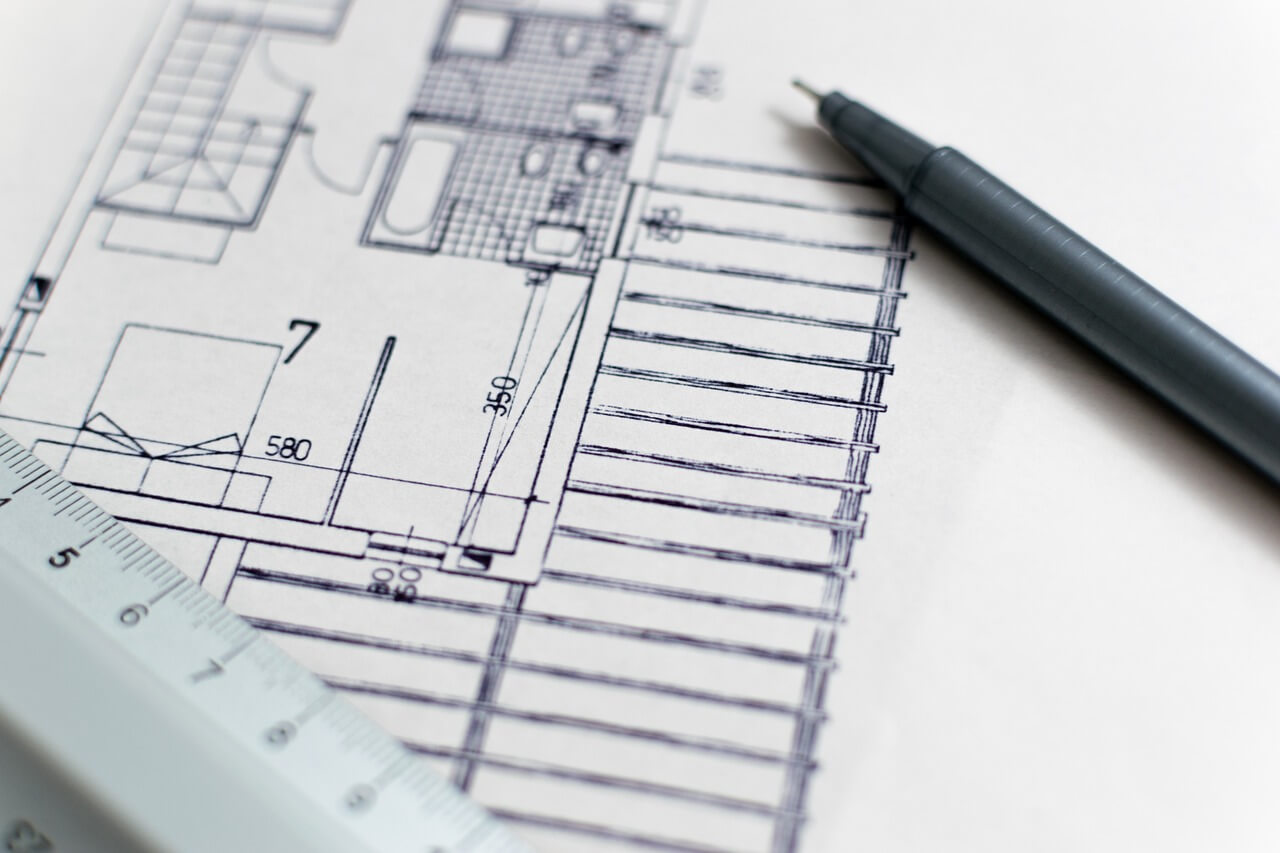

ここからは、各施工管理技士とよく比較される資格の難易度を見ていきましょう。
施工管理技士以外の資格も取得していくと思うので、資格を取る順番の参考にもなると思います。
1級建築施工管理技士と一級建築士の難易度を比較
結論、一級建築士の方が難しいです。
合格率の違いは以下のとおり。
| 資格 | 合格率 |
| 1級建築施工管理技士 | 約19% |
| 一級建築士 | 約10% |
一級建築士は製図試験が難しく、何年も合格できない人もいる難関資格です。
一級建築士については、一級建築士試験の合格率や受験資格からみる難易度【勉強時間の目安】に詳しくまとめています。
2級建築施工管理技士と二級建築士の難易度を比較
結論、二級建築士の方が難易度が高いです。
二級建築士には製図試験があり、独学での合格は難しいところ。
2級建築施工管理技士は製図試験がない分、試験対策しやすいです。
二級建築士については、二級建築士の難易度!合格率や受験資格から分析してみたにまとめています。
1級土木施工管理技士と建設部門の技術士の難易度を比較
建設部門の技術士の方が難しいです。
合格率の比較は以下のとおり。
| 資格 | 合格率 |
| 1級土木施工管理技士 | 約20% |
| 建設部門の技術士 | 約10% |
技術士は誰でも受験できますが、試験はかなり難易度が高いです。
建設部門の技術士については、建設部門の技術士の合格率や難易度【おすすめの勉強方法も紹介します】にまとめています。
電気工事施工管理技士と電気工事士の難易度を比較
結論、電気工事施工管理技士の方が難しいです。
合格率の比較は以下のとおり。
| 資格 | 合格率 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 約30% |
| 2級電気工事施工管理技士 | 約30% |
| 第一種電気工事士 | 約58% |
| 第二種電気工事士 | 約64% |
2つの資格の違いは、電気工事施工管理技士と電気工事士の違いを解説!にまとめています。
1級電気工事施工管理技士と電気主任技術者の難易度を比較
電気主任技術者の方が難しいです。
合格率の比較は以下のとおり。
| 資格 | 合格率 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 約30% |
| 第一種電気主任技術者 | 約2% |
| 第二種電気主任技術者 | 約5% |
| 第三種電気主任技術者 | 約10% |
合格率でもわかりますが、圧倒的に電気主任技術者の方が合格しにくいです。
電気主任技術者は「電気系資格の最難関」といわれており、当然ながら試験問題もかなり難しいです。
電気主任技術者の詳細は、電気主任技術者・電験試験の難易度や年収!三種二種一種のコツにまとめています。
管工事施工管理技士と配管技能士の難易度を比較
管工事施工管理技士の方が難しいです。
合格率の違いは以下のとおり。
| 資格 | 合格率 |
| 1級管工事施工管理技士 | 約22% |
| 2級管工事施工管理技士 | 約28% |
| 配管技能士 | 約50% |
配管技能士については、1級・2級・3級の配管技能士の試験内容【参考書や過去問の勉強方法】にまとめています。
造園施工管理技士と造園技能士の難易度を比較
造園施工管理技士の方が難しいです。
合格率の違いは以下のとおり。
| 資格 | 合格率 |
| 1級造園施工管理技士 | 約16% |
| 2級造園施工管理技士 | 約22% |
| 1級造園技能士 | 約40% |
| 2級造園技能士 | 約60% |
| 3級造園技能士 | 約65% |
2つの資格の違いは、造園技能士と造園施工管理技士の違い【あなたはどっちに向いてるか診断】にまとめています。
電気通信工事施工管理技士と工事担任者の難易度を比較
結論、電気通信工事施工管理技士の方が難しいです。
合格率の違いは以下のとおり。
| 資格 | 合格率 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 21% |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 27% |
| 工事担任者 | 36% |
2つの資格の違いは、電気通信工事施工管理技士と工事担任者の違いを解説にまとめています。
電気通信工事施工管理技士と電気通信主任技術者の難易度を比較
こちらも電気通信工事施工管理技士の方が難しいです。
合格率の違いは以下のとおり。
| 資格 | 合格率 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 21% |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 27% |
| 工事担任者 | 30% |
2つの資格の違いは、電気通信主任技術者と電気通信工事施工管理技士の違いを解説にまとめています。
施工管理技士についてよくある質問

最後に、施工管理技士についてよくある質問に答えていきます。
施工管理技士以外で施工管理技術者におすすめの建設系資格の一覧は?
以下がおすすめです。
- 建築士
- 構造設計一級建築士
- 建築仕上げ改修施工管理技術者
- マンション改修施工管理技術者
- 防水施工管理技術者
- 登録防水基幹技能者
- 建築コンクリートブロック工事士
- 免震部建築施工管理技術者
- 建築CAD検定
- 土木設計技士
- 建設部門の技術士
- 舗装施工管理技術者
- コンクリート技士
- プレストレストコンクリート技士
- 鋼管杭施工管理士
- のり面施工管理技術者
- 空港工事施工管理技術者
- 海上工事施工管理技術者
- 解体工事施工技士
- 造園技能士
もちろん、すべてを取得する必要はありません。
専門分野に必要な資格だけ取得していけばOKです。
詳しくは、現場監督の仕事に役立つおすすめ資格42選一覧【難易度も紹介】にまとめています。
施工管理技士以外で施工管理技術者におすすめの設備系資格の一覧は?
以下がおすすめです。
- 建築設備士
- 設備設計一級建築士
- 下水道管きょ更生施工管理技士
- 配管技能士
- ガス主任技術者
- 空調設備士
- ボイラー技士
- 厨房設備士
- 計装士
- エネルギー管理士
- 高圧ガス製造保安責任者
詳しくは、建築設備系のおすすめ資格53選一覧【難易度ランキングも紹介】にまとめています。
施工管理技士以外で施工管理技術者におすすめの電気系資格は?
電気工事士がおすすめです。
電気施工管理が工事をするわけではありませんが、電気工事士を勉強しておくことで、現場の電気工事士さんとコミュニケーションをとりやすいから。
知識を深める意味でも、電気工事士を勉強しておくと良いでしょう。
電気工事士の詳細は、電気工事士1種2種の資格難易度や合格率!勉強や技能試験のコツにまとめています。
一級建築施工管理技士のすごいところは?
すごいところは以下の4つです。
- 主任技術者・監理技術者になれる
- 転職先の選択肢が増える
- 年収アップしやすい
- 試験の難易度が高い
詳しくは、一級建築施工管理技士のすごいところ4選【メリットや価値が大きい】にまとめています。
2級を飛ばしていきなり1級建築施工管理技士を受験してもいい?
受験資格を満たしていれば、いきなり1級建築施工管理技士から挑戦してもOKです。
ただし、2級→1級の順に受験する人も多いです。
理由は以下の2つ。
- 施工管理技士の試験に慣れるため
- 2級で勉強したことが1級の試験でも出題されるから
1級建築施工管理技士については、1級建築施工管理技士の合格率や過去問や受験資格から見る難易度にまとめています。
一級建築施工管理技士と一級建築士は両方取得した方がいい?
できれば両方を取得するのがおすすめです。
理由は以下の4つ。
- 設計内容を理解して工事できるから
- 設計者の意図を理解できるから
- 資格手当で稼げるから
- 転職が有利になるから
結果、スムーズに工事が進みます。
詳しくは、一級建築士と一級建築施工管理技士は両方とった方がいい【勉強のコツ】にまとめています。
2級土木施工管理技士は一夜漬けでも合格できる?
さすがに難しいです。
2級土木施工管理技士の合格率は以下のとおり。
- 第一次検定:約67%
- 第二次検定:約38%
たしかに第一次検定の合格率は高めですが、3割以上の人が不合格になる試験なので、さすがに一夜漬けで合格は厳しいでしょう。
詳しくは、一夜漬けで2級土木施工管理技士に合格するのは不可能【甘くないです】にまとめています。
一級土木施工管理技士のすごいところは?
以下の5つです。
- 第二次検定試験の合格率が低い
- 監理技術者になれる
- 転職で引く手あまたになる
- 年収が高い
- 将来性がある
一級土木施工管理技士の経験記述はネットや参考書を丸写ししていい?
丸写しがバレると、合格は難しいでしょう。
参考書やネット上の例文と照合されたら、減点や失格の対象になると予想されます。
詳しくは、一級土木施工管理技士の経験記述の丸写しはデメリットが大きい【例文も紹介】を参考にどうぞ。
2級土木施工管理技士の実務経験のごまかしは危険?
ごまかしはNGです。
デメリットは以下の2つ。
- 試験に合格しても資格が取り消しになる
- 試験を最大3年は受けられなくなる
デメリットが大きすぎるので、くれぐれもごまかさないようにしましょう。
詳しくは、2級土木施工管理技士の実務経験のごまかしは危険すぎる【取消になる】にまとめています。
施工管理技士の実務経験の重複はバレる?
以下の2つでバレる可能性があります。
- 内部告発でバレる
- 取引業者に確認されてバレる
事実、これらでバレた事例があります。
バレれば、当然ながら資格を取得できません。
詳しくは、施工管理技士の実務経験の重複がバレる2つの経路【ペナルティも解説】にまとめています。
まとめ:施工管理技士の資格は難易度高いけど、取得すれば稼げる

建設業界でキャリアを積んでいくなら施工管理技士を取得しておくことをおすすめします。
前述のとおり、建設会社は施工管理技士の数によって売上が大きく左右されます。
施工管理技士がいることで、下記のメリットがあるため、施工管理技士は給料アップや昇進につながります。
- 専任技術者・主任技術者・監理技術者・現場代理人・統括安全衛生責任者・元方安全衛生責任者を兼ねることができる
- 工事を多く受けられるため売上が上がる
- 経営事項審査の点数が上がり公共工事受注の際に有利
今後は施工管理技士の人数が減っていく可能性もありますから、さらに年収が高くなる要素があります。
転職にも有利になるため、転職を機に給料の交渉をして年収を大きく上げる人もいます。
施工管理技士はまさに「手に職の資格」「稼げる資格」です。
あなたのキャリアアップに有効な資格といえるでしょう。
本気で施工管理技士を取得したいなら、独学でもいいので、さっそく勉強を始めましょう。
勉強を始めるのに「早すぎる」ということはありません。
本気なら、今日から少しずつ勉強を始めましょう。
まずはAmazonとかで、参考書や過去問を買ってみてください。
ちなみに、施工管理技士を取得して転職したい人は、施工管理(現場監督)の転職先の会社選びのコツ【転職活動方法も解説】にを参考にしてみてください。
あなたに合う会社を選ぶコツを解説しています。
あなたのキャリアの参考になればうれしいです!